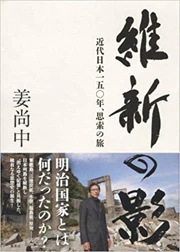一方で、日本の地がとても好きだという感情が強くなったと語る姜尚中氏
一方で、日本の地がとても好きだという感情が強くなったと語る姜尚中氏2月1日、ジュンク堂書店池袋本店において、姜尚中(カン・サンジュン)氏の新刊『維新の影──近代日本一五〇年、思索の旅』刊行の講演会が開催された。
同書は、近代日本を支えてきたエネルギー産業の基幹であった端島炭鉱(通称・軍艦島)をはじめ、過疎と高齢化に見舞われる熊本県球磨村、大震災直後の熊本、3.11から時間が経った福島第一原子力発電所など各地を巡り、この国の繁栄の歴史とその負の側面とを振り返った「思索の旅」の記録である。
この本に込められた姜氏の願いとはどのようなものなのか。「思索の旅」を通じてどのような思いを抱くようになったのか。満員の中、行なわれた講演会での内容を前編記事に続き、ダイジェストでお送りする。
* * *
山本義隆さんは書籍のタイトルで「科学技術総力戦体制」という言葉を使っています。これは戦前のみならず、戦後日本も平和という形を身にまといながらも、ある種の総力戦で戦っていたという発想ですね。
この考え方は、私が大学院時代にお世話になった山之内靖先生という方が「総力戦体制論」という名目で、比較的早くから唱えておられました。それに類することは、野口悠紀雄氏が『1940年体制』においても書いていますし、歴史家のジョン・W・ダワーも『昭和』というエッセイで触れています。いずれにせよ、三者に共通しているのは「戦前と戦後はかなりの点で地続きである」という見方です。
教科書的に言えば、軍閥や内務省は戦後に解体され、実質的には財閥も解体されたことになっています。私も若い時から、戦前と戦後の断絶というところに力点を置いた見方で多くのものを学んできました。「そのひとつの成果が戦後民主主義だ」、あるいは「平和憲法だ」と言われていましたし、それを信じていました。
しかしながら、別の一面から見ると、なぜ旧・優生保護法が1996年まで続いてしまったのだろうか、あるいは、らい予防法(ハンセン病患者や元患者を隔離することなどを定めた法律)もどうして1996年まで廃止されなかったのか。どうも現状を見る限りは、むしろ戦前から連続があるとしか思えませんし、そう考えたほうが、今という時代がよくわかる可能性があるかも知れない。
それ以外にも、いろいろな「負」の側面を持った物事が実は今に至るまで続いている。ひと言でいうと「冷たい」。その冷たさというものは何に由来するのか。国家というものが犯したネガティブなものが根本的に清算できないのはなぜなのか。あるいは日本という国が持っている、民というものに対する「恐れ知らず」な態度の根幹にあるものはなんなのだろうか。戦前と戦後で、確かにレジーム(体制)は変わったんだけれども、「恐れ知らず」の態度はどこか変わらずに今も残っているようにしか思えません。
私は一応、思想史をやってきたので、どうもやはり「不在だけれども、常に存在しているもの」はなんなのだろうか、という意識の向け方をします。やがてそれが像を結んだのですが、それは「国家」という問題ではないかと思ったのです。
近代日本では「国家」という存在が、常にその存在感を露(あら)わにしてきたわけではないものの、実に様々な事件・事象の鍵を握る存在として影響力を発揮し続けてきた。いわば、「不在の主役」として君臨している。その実態を解き明かした歴史記述を描き出すというのが、今回の「思索の旅」の主題であったのではないかと今は思っています。
■「知識人」たちの存在と、この国の希望
一方で、取材を通して痛切に感じるようになったもうひとつの思いというのは、私はこの日本の地がとても好きだという感情です。愛すべき対象だといえばいいのかな。現場に足を運んで、実にいろいろな方にお会いしているうちに、そういう気持ちがものすごく強くなったのです。
福島で出会った様々な方々、『田中正造大学』で活動を続けられている方々や、「希望の牧場・ふくしま」を運営されている方々…こんな方がいるのか、という驚きの出会いの連続でした。日本の社会はこれまで私が考えていた以上に豊かなものを持っている。そんな彼ら、彼女らを敢えて呼ぶとすれば「民」としか言いようがないと思います。なかなかメディアで取り上げられる機会はない存在ですけれども、そういう在野の人々を丸山眞男さんの言葉で「疑似知識人」というんですね。私は『維新の影』の中で、その言い方を真似て「疑似インテリ」という言葉を使いました。
しかしながら、そうした「民」には国家や国というものを大きく変えるだけの力が残念ながらなかなかないという現実もあります。ここでひとつ目の問題に戻りますが、結局、なぜ“国が民を恐れないんだろうか”と考えると、やっぱり近代日本における知識人という存在がいなかったことがネックになっていたのだろうと思います。
日本の可能性は個々の現場にしかない

知識人という言葉は今ではもう昔物語で、そんなのはいないと考えられているかも知れません。大物知識人などということを考えること自体が時代錯誤だと。あるいは、そうした存在自体が幻想だという立場もあるでしょう。ただ、間違いなく、その知識人と呼ばれている人々は様々な問題を普遍化していき、それを公共圏の中に投げ込むという役割を担ってきた。そのことによって社会が動いていくということがあったわけですね。
もちろん、今、全世界的に見るとなかなかそういう現象はもう見られなくなっている。しかし、フランスのドレフュス事件を扱ったエミール・ゾラのように、日本においても歴史的にそうした存在は複数いたわけですね。田中正造もそのひとりだったのかも知れません。そういう知識人というものが、残念ながら今の日本では階層横断的に存立し得ていない。
日本における知識人というのは企業であれ官公庁であれ、ある制度圏の中で、あるステータスを保証され、与えられているという形でしか成り立ち得ない。その制度圏の外にあるのは、いわば非常に傍系の、要するにクレーマーという程度の扱いなんですね。
かつて水俣病事件があった時には、色川大吉さんや宇井純さん、原田正純さんといった歴史家や医学者、あるいは精神科医も含めてそういう人々が調査団に入って、それであれだけのことができた。彼らはいわば「知識人」と呼べる存在でした。しかし、それでも今もって水俣病は完全には解決していません。
今はさらにそうなっているでしょう。実際問題、自分のジャンルを超えて知識人たちがボランティアで福島の中に入り、水俣と同様の調査をやっているのかというとできていない。残念なことに、社会にとってシリアスなテーマを常に公共圏に投げかけるという知識人の活動が、この150年で弱まっているのかもしれない。そんな不安がありました。
しかし、今回の取材を通して出会った方々は、決して学歴が高いわけでもなく、アカデミズムに身を置いていたわけでもないのですが、私にとっては間違いなく、ある種の「疑似知識人」としか言いようがありませんでした。そんな人々が今も現場でいかにいろいろなことをやっているかを知ったというのは、非常に心の支えになりました。
これからの日本の可能性はやはり、そういう個々の現場にしかないのではないかと思います。そういう方々へのエールとして、『維新の影』という本は書かれたのかも知れません。そういう気持ちとこれからの日本に向けた「希望」をこの本から読み取っていただければいいなあと感じております。