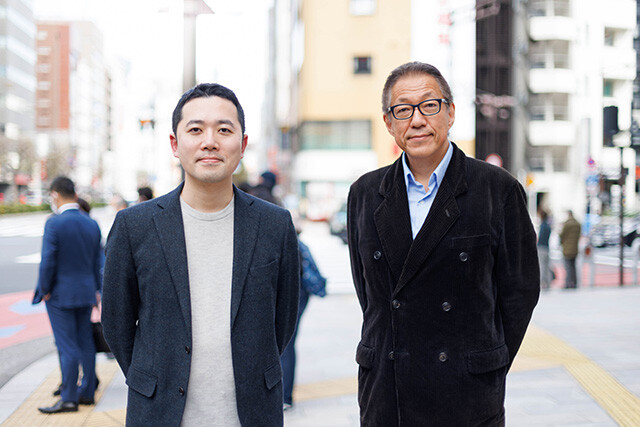 岩井圭也氏(左)とドリアン助川氏(右)
岩井圭也氏(左)とドリアン助川氏(右)
社会派エンタメ作家として注目される岩井圭也氏の最新刊『生者のポエトリー』が4月5日に刊行。今作のテーマはタイトルにある通り、まさに「詩」――緘黙(かんもく)の青年がライブハウスで自作の詩を叫ぶ第1話「テレパスくそくらえ」をはじめとした6編の連作で、年齢も立場も様々な登場人物が、今の時代を映し鏡として言葉の力に迫る意欲作だ。
そこで、パンクバンド「叫ぶ詩人の会」の活動でも知られる作家・ドリアン助川氏との対談が実現! 助川氏から何度となく「嫉妬です」という発言が出るほど、共感とともに高評価を頂戴する中、政治家の響かない言葉、社会問題に絡む対話と分断、若い世代への希望まで......この世界を生き抜くべく"言葉の力"を信じる作家同士ゆえの刺激的な語らいに!!
■「叫ぶ詩人の会」結成前夜の鬱屈した20代に重なる共感
――まずはドリアンさん、お読みになっていかがでしたか?
助川 まずはめちゃくちゃ共感しましてね。
僕は学生時代、将来はお茶の間にドラマを届ける仕事をしたいと思っていた。でも色弱でね、当時はテレビ局や映画会社からは門前払いで、鬱屈(うっくつ)した気持ちを抱えて、新宿の飲食店や塾の講師として働きながら放送作家の事務所に出入りするようになったんです。とはいえ、使い走りのような立場でストレスと苦悩の20代で、ある時から人前で話すこともできなくなってしまった。
でもその後、報道の仕事でカンボジアを歩いている時に、全身で表現したくなったんです。例えば、地雷を踏んで足を失くしたお父さんの気持ちとか......それでいきなりパンクバンドを始めた。話す勇気も持てない中、花開くとは思っていないけど、やらないと死んでしまう。そういったあの時の気持ちが、第1話の言葉が出てこない彼と重なったんです。
――「叫ぶ詩人の会」を結成した経緯と同じなんですね!
助川 第3話の塀の中を経験したラップをやる青年も、BLM(ブラック・ライヴズ・マター)運動のケンドリック・ラマーを思わせますよね。彼はコンプトンというデトロイト以上の犯罪都市で生まれ育ち、お父さんはギャングスターという中でエミネムに出会うわけですが、「オールライト」という曲では黒人として生きていく上での犯罪を含めたあらゆる問題、社会構造的な負の側面を歌っている。
岩井さんの文章には鮮烈な表現も各所にあり、日本のケンドリック・ラマーがここにいたと! 英語で言うとtwo thumbs-upというか、全面的に支持という......まあ正直、半分は嫉妬(笑)。
岩井 いやいや、嫉妬だなんてそんな! でもむちゃむちゃ嬉しいです。
助川 キリキリするような痛みを感じて読める小説だということは、書く側はもっと苦しいはずです。僕は辛い20代だったと話しましたが、やはりそういう鬱屈が?
岩井 ありました。会社に勤めながら作家をやっているんですけど、やりたい仕事ができなくて、でも社会人としての変な義務感もあって板挟みで苦しい時期もありましたし。作家としてもなかなか芽が出ず、ひたすら書いて応募しても音沙汰がない時期が6年くらいあったんです。その報われない中に「それでも書こう」と思った心理は、今作にも表れている気がします。
助川 そういう溜め込んだものや悲しみは登場人物に仮託できるとはいえ、本人にも真ん中に痛みがないと書けないものでしょう。
岩井 そういう意味では第1話の主人公に仮託したところはあります。「場面緘黙」を知った時、非常に苦しい症状だと思うと同時に、どこか自分と似た部分を感じたんです。彼は話すことができない人なんですけど、逆に私はなまじ話せてしまうので、嘘を重ねているように感じて逆コンプレックスがあったんです。これは対極にあるようで、私の中では表裏一体でした。
言いたいことが言えないことと、私のように上辺ばかりになってしまう気がすることは、本当の気持ちを表せないという意味で重なるのではと、書きたい衝動に駆られました。
――まず、緘黙症の主人公の物語ありきで、そこから詩が題材の連作にしたのはどういうきっかけが?
岩井 詩も同じ時期に書こうと思っていたんです。特にポエトリーリーディングは、声に出して発することで聴覚的にその人の声で聴いてもらえる。本当の気持ちや主張が伝わる手段はもしかしたらこれなのかな、と結実しました。
助川 バンドで伝える詩は、字に直すと単純な詩なんです。文字を読んで味わう詩と、1回聴いただけで入ってくる言葉の群れとはまた違うんですよね。これを同じ土俵で語ってしまう人は結構多くて。岩井さんが書かれた詩は、僕のようにステージもやる人間からすると、仏教でいう中道というか真ん中の一番いいところにある気がするね。
――ちなみに、今思えば「叫ぶ詩人の会」というのも、ド直球なネーミングですよね。
助川 難しいものにされてしまった詩を、一般の人側に引き付けたいというのがあったんです。
岩井 叫ぶというのは魂をぶつけていくスタイルですよね。最後はそこに行き着くし、最初の衝動もやっぱりそこなのかなという気がします。
助川 なおかつ詩ですから、読む側、聴く側にとって、新しい地平が広がらなきゃいけない。見たことのない風景があり、なおかつ共感があるという。難しいことですが、岩井さんは自然とやっておられますね。そこも嫉妬するというか(笑)。
岩井 いやいや(笑)。でも、見たことのない風景は描きたいと思っていました。というのは、エンタメ小説はある程度「理」に落ちないといけないのですが、そこに詩を入れたら、わからないものをわからないままエンタメとして昇華できると思ったんです。
先ほど共感と仰っていただきましたが、私もドリアンさんの『新宿の猫』は小説の中に詩が出てくる形式も含めて大好きですし、また『プチ革命 言葉の森を育てよう』の中では、詩に対して考えていたことを言語化してくださっています。
例えば「あの八百屋は黒いバナナを売っているね」というセンテンスが「黒い八百屋がバナナを売っているね」や「黒いバナナが八百屋を売っているね」になった時、面白みを感じられるかがその人の感性や詩の楽しみ方なんだと。
普通のエンタメ小説では校閲で直されますが、詩なら許されるだろうし、もしかしたら複雑で言いようのない感情を表現する手段になったり、新しい文学になるんじゃないかなと。
■「エモい」と「キモい」――日本の社会が奪う詩情とは
助川 特に、新聞小説だと校正には苦しめられますね(笑)。ある程度は必要でしょうけど、例えば宮沢賢治のあの文体に校正者がいなくて良かったなと思うわけですよ。「てにをは」もおかしいし、でも全部直されたら宮沢賢治じゃなくなってしまう。ひょっとしたら、日本語として破壊されていても、読む側にとって快感だったり伝わるのであれば、それはあり得るんじゃないかと。
その中にポエトリーを盛り込むことは、ある種、世の常識をひっくり返してくれるんじゃないかと。岩井さんの作品で楽しみなのは、今後こういう形では取り入れないにしても、ポエトリーが文章の中に地下茎のように入り込んでいって、いつか見たこともないような小説であり詩のようになっていくんじゃないかなと。その未来も嫉妬ですね。みんながやりたいことだから。
岩井 恐れ入ります(笑)。これは雑誌で2年ほどかけて書かせていただき、毎回この短編を書く中で、原点に戻るような気持ちがありました。同時に「新しい表現」を持って、また狩り場に行くようなサイクルをうまく作れたので、この数年でもその地下茎が伸び始めていると感じています。
助川 ポエジー(詩情)ということで語るなら、実はあらゆる表現者の核になる部分で、やはりそれがある人が国境や時代を超えて何かを手渡していくことができると思うんです。岩井さんは画家や建築家であったとしても自分の表現をされる方になったと思いますが、小説というものに決め込んだ理由はなんですか?
岩井 ひとりで自分の世界を表現し切りたいのと、言葉で表現したいというのが大きかったです。小説は100人いたら100人の読み方があり、映像による表現よりも文字のほうが想像の余地が大きく、より濃密なのかなと。言葉でイメージを喚起させる原初的な部分を一番にやれるのが小説というだけで、それが詩でなかったのは偶然かもしれません。
助川 よく言われることですけど、明治時代、西洋に追いつけ追い越せという富国強兵の流れの中で、日本の俳句や短歌が捨てられた時代があるんですよね。それで坪内逍遥なんかが西洋の詩を翻訳して。しかし西洋の詩には、韻(いん)を踏むとか賛美歌のシラブル(音節)の数が決まっているとか、音楽としてのルールがある。その音楽的な部分までは訳せないから結局、日本人は詩がなんなのかをわからないまま、言語論だけで捉えがちなんです。
そして今、文科省の新学習指導要領では高校の現代国語から小説や詩歌が排除されるような方向で、論理国語のほうに流れている。メールの書き方や契約書の読み方ばかりの中で、詩とは何かを若い時分に考えないまま、詩が消えていこうとしている。だから僕はこの作品に共感も感動もしたんですけど、もうひとつはここに焦点を当てる若者がいたんだというね。
今はみんな本を読まない。たまに文庫本を読んでいる高校生を見つけると、行って激励の千円札を渡したくなるぐらいで(笑)。その中でこの作品を発信するというのは、どういう思いが?
岩井 実は、10代の頃はあまり詩を読まず、20代で「うわっ、もったいなかった!」と思ったんです。タイトル案の中には「青春と呼ぶには詩が足りない」というのもあって、要するに、青春時代に詩があればもっと豊かに時を過ごせたのにという後悔があるんです。詩を読むことが高尚だったり、難しいイメージを持たれているのはもったいないですね。
あと、実は若い人もそれを感じる感性自体は持っていると思うんです。ここ数年「エモい」という言葉がありますが、言葉には言い表せないけどなんとなく気持ちいいという感性は、詩情に近いのではないかと。
助川 ああ、僕は大学の教員もやっているんですけど、2年生のゼミでは最初にタゴール(インドの詩人。アジア初のノーベル文学賞作家)を紹介し、2回目はいきなり詩を書かせるんです。詩なんて書いたことがないですってむちゃくちゃ恥ずかしがるんだけど、2回、3回と発表させるうちにものすごく生き生きしてくる。
だから仰る通りで、青春の器が変わったわけじゃないんです。大人たちが勝手に青春の場面から文芸や詩歌を奪おうとしているという感じがしますね。詩を読む・書くというと「キモい」とか言うコもいっぱいいます。でもそれは、そのコたちのせいじゃなくて、この日本の社会がそうなっているからです。
●岩井圭也(いわい・けいや)
1987年、大阪府出身。北海道大学大学院農学院修了。2018年「永遠についての証明」で第9回野性時代フロンティア文学賞を受賞し、デビュー。著書に『夏の陰』『文身』『プリズン・ドクター』『水よ踊れ』『この夜が明ければ』『竜血の山』など
●ドリアン助川(どりあん・すけがわ)
1962年、東京都出身。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒業。明治学院大学国際学部教授。日本ペンクラブ常務理事。1990年、パンクバンド「叫ぶ詩人の会」を結成し話題に。作家、詩人、歌手、ラジオパーソナリティと幅広く活動し、明川哲也名義も合わせ著書多数
