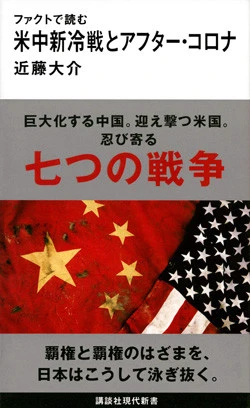「尖閣で武力衝突が起きる可能性はある。施行された「海警法」は完全に尖閣を取りにいくことを前提にした法律だと思います」と語る近藤大介氏
「尖閣で武力衝突が起きる可能性はある。施行された「海警法」は完全に尖閣を取りにいくことを前提にした法律だと思います」と語る近藤大介氏
アメリカと中国、超大国の対立が世界に大きな影響を与える「米中新冷戦」の時代、ふたつの覇権のはざまで日本はいかに生き残るのか?
反中や親中といった感情論ではなく、米中対立の構図をファクトに基づく「7つの戦争」で分析し、その答えを探るのが近藤大介氏の新刊『ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ』(講談社現代新書)だ。
バイデン政権の誕生で米中関係の今後は? 中国の「海警法」成立で尖閣諸島をめぐる日中の軍事衝突は起こりえるのか? 近藤氏を直撃した。
* * *
――トランプ政権下で急激に悪化した米中関係は、バイデン政権になってどう変わりますか?
近藤 バイデン大統領の基本的な政策は「トランプ時代の負の遺産」を全面的に否定し、ひっくり返すということですが、そのなかで唯一、トランプ政権の政策をそのまま受け継いでいるのが対中政策で、米政権が共和党から民主党に代わっても対中政策の基本は変わりません。
一方、今年7月に共産党創建100周年を迎えるなか、強権的な中国の習近平体制は盤石です。中長期的に見て「米中新冷戦」の構図は続くでしょう。
具体的には、私がこの本で「7つの戦争」と呼んでいる、①貿易②技術③人権④金融⑤疫病⑥外交⑦軍事をめぐる両国の対立が複雑に絡み合いながら展開するのだと思います。
ただし、バイデン政権が抱える当面の課題を考えると、短期的には米中対立が小休止するかもしれません。コロナ対策には中国製のマスクが欠かせませんし、経済復興には中国向けの輸出拡大が鍵になる。
また、国民の多様性と融和を強調するバイデン政権にとって、ユダヤ系に次ぐ経済力を持つ約400万人の中国系アメリカ人の存在は無視できない。気候変動など、環境問題への取り組みでも中国との協力は不可欠です。
――新型コロナの問題は、今後の米中関係にどのような影響を与えるのでしょう?
近藤 今年はワクチン戦争が活発化していきます。欧米系のワクチンと中国製のワクチンが世界を二分していく構図です。
最新の遺伝子技術を使ったファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンが先進国に行き渡る一方で、より安価で扱いやすい中国製の不活化ワクチンは、東南アジアなどの発展途上国に行き渡るようになる。ワクチンをめぐり、先進国と発展途上国を二分する疫病戦争です。
特に中国が今、最重要視するのが東南アジアです。ASEAN(東南アジア諸国連合)は今や中国最大の貿易相手で、中国はアメリカの強い影響下にあったASEANを自国の影響下に置こうと戦略的に考えている。そこで都合がいいのは、近年ASEAN諸国が「中国化」し始めていることです。
最近では軍事クーデターが起きたミャンマー、事実上の軍事政権のタイ、それにカンボジア、ベトナム、ラオス、フィリピン、ブルネイも実態は独裁的な強権政治です。中国はこれらの国を味方につけたいわけで、ワクチンを積極的に供給して東南アジアを「中国の庭にしよう」というのが中国の描いている疫病戦争だと思います。
――そこで気になるのが、尖閣諸島の問題です。先日、中国が「海警法」を制定しましたが、この先、尖閣をめぐって武力衝突が起きる可能性はありますか?
近藤 私はあると思います。施行された「海警法」の全84条を読みましたが、これは完全に尖閣を取りにいくことを前提にした法律だと思います。
日本の政治団体が1978年に尖閣に建てた灯台の撤去、日本の漁船や海保の船の拿捕(だほ)、またその際に武器使用も許されるとある。さらに「押収物を競売にかけてもいい」とまで書いてあります。押収された漁船を中国漁民が買ってしまったら、日本の船を中国の漁師が使い始めるということになる。ビックリです。
今回の海警法はそうしたことに法律的なお墨付きを与えているわけで、これからは日本の漁船が尖閣海域で漁業をすることはかなりのリスクを伴ってくると思います。
――中国は本気で「尖閣を取りにくる」のでしょうか?
近藤 習近平政権の歴史観では、尖閣諸島は「日清戦争で日本に奪われた台湾の一部」というとらえ方なんですね。そして、その台湾は中国の一部だと考える習政権にとっては当然、尖閣も中国のものだという認識なのです。これが尖閣を日本から取り返すという主張の政治的な根拠になっているわけです。
19世紀の中頃まで「世界一の大国」だった中国(清朝)がアヘン戦争で英米に敗れて没落を始め、その流れを決定づけたのが日清戦争の敗戦だと考える習近平にとって、台湾や尖閣に象徴される「日清戦争の負の遺産」の清算は重要な課題です。
強硬な姿勢の人民解放軍を味方につけ、さらなる長期政権を目指すためにも、尖閣をめぐる緊張がさらにエスカレートするのは目に見えている。そういう事実を踏まえて日本は対処していかなければならないと思います。
――尖閣をめぐって「衝突」という事態になったとき、アメリカは助けてくれますか?
近藤 私はアメリカをあてにしないほうがいいと思います。もちろん、米軍と自衛隊の関係は兄弟分のように良好ですし、日米安保条約の第5条もあるので、もし尖閣で自衛隊が戦うようなことがあれば、米軍としても友軍を助けたいと思いますよ。しかし米軍の最高司令官は大統領で、バイデン大統領がOKしなければ攻撃はできない。
これは台湾に関しても同じで、アメリカが尖閣諸島や台湾のために中国と戦争をするかといえば、少なくともこの4年間はないと思うんですね。
一方で日本の国益を考えたとき、アメリカとの日米同盟はとても大切ですが、同時に中国との貿易関係も大事です。昨春、中国製のマスクがなくなっただけでパニックになったわけですし、日本の産業の多くは中国なくして成り立ちません。
ですから現実にはアメリカにもいい顔をしつつ、中国にもある程度ビジネスではいい顔をするという「戦略的曖昧(あいまい)性」を発揮することが重要です。
日本はすでにかつてのような経済大国から、縮小段階に入っている国だという現実を直視した上で、深まる米中対立の間で100か0かといったどちらかに軸足を置くのではなく、日本人の得意な「曖昧さ」を生かしながら生き延びていく以外に道はないと思いますね。
●近藤大介(こんどう・だいすけ)
1965年生まれ、埼玉県出身。東京大学卒業、国際情報学修士。講談社『週刊現代』特別編集委員。明治大学国際日本学部講師(東アジア国際関係論)。2009年から2012年まで、講談社(北京)文化有限公司副社長。近著に『アジア燃ゆ』(MdN新書)、『中国人は日本の何に魅かれているのか』(秀和システム)、『ファーウェイと米中5G戦争』(講談社+α新書)など
■『ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ』
(講談社現代新書 900円+税)
トランプ政権下で突入した「米中新冷戦」は、バイデン新政権になってどう展開していくのか。毛沢東を崇拝してやまない習近平政権は、アメリカとどう対峙していこうとしているのか。日本を取り巻く東アジア情勢を30年以上にわたってウオッチし続けてきた著者が、アフター・コロナ時代のアメリカと中国の動向、ふたつの超大国と日本はどう付き合っていくべきかを徹底解説する