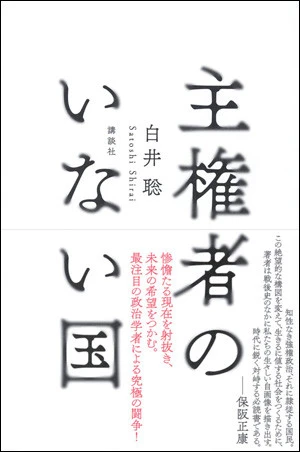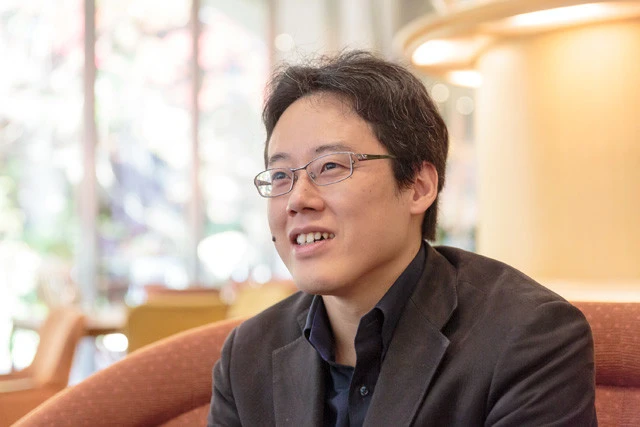 「深刻な危機に直面すると、主体的に考える力のない国の『フェイクな近代性』が露呈してしまう。政府のコロナ対応を『先進国とはいえないレベル』だと感じてしまうのも、そのためです」と語る白井聡氏
「深刻な危機に直面すると、主体的に考える力のない国の『フェイクな近代性』が露呈してしまう。政府のコロナ対応を『先進国とはいえないレベル』だと感じてしまうのも、そのためです」と語る白井聡氏
戦後の日本が経験した最大の厄災ともいえる、東日本大震災と福島第一原発事故から10年が過ぎた。しかし、3・11を契機に大きく変わるかと思われた日本社会は、その後、ズルズルと後退を続けながら分断を深め、今また新型コロナの流行という新たな厄災のなかで、迷走と混乱を繰り返しているように見える。
なぜ日本社会は過去の悲劇や失敗から学び、変わることができないのか? 3・11からコロナ禍に至る、この10年の日本の歩みをさまざまな角度で検証しながら、その答えを探るのが白井聡氏の新刊『主権者のいない国』(講談社)だ。
* * *
――2013年に発売されベストセラーとなった白井さんの『永続敗戦論』は、3・11をきっかけに書かれた一冊でした。これまでの日本の歩みをどんなふうに感じていますか?
白井 福島の原発事故と、それから今のコロナ禍に至る約10年のなかでハッキリと露呈したのは「近代日本のフェイク性」です。より具体的に言えば、日本社会が大切にしてこなかった国民の「主体性」の欠如です。
――主体性の欠如とは?
白井 本書の冒頭にも書きましたが、福島第一原発の事故で4号機の燃料プールが空になり、核燃料がむき出しになって「東日本壊滅」という最悪の事態に至らなかったのは、当時、燃料プールに隣接する「原子炉ウェル」に、工事のため一時的に張ってあった水が偶然、燃料プールに流れ込んだという幸運があったからでした。
ひとつ間違えば、「日本が終わる」といった事態もありえたわけで、その認識があれば「なぜこんなことが起きたのか?」と考えるのが当然でしょう。
――実際、そう考えた人は少なくなかったと思います。
白井 ところが原発事故後も、原発をめぐる議論は「曖昧(あいまい)」なままですし、その後の10年間の大半を占めた安倍政権の時代も、戦後日本の劣化を象徴するような政治やモラルの問題が起きても、多くの人は一時的に批判的になるだけで、結局、選挙になれば、与党が勝ち続けてきました。
安倍政権の末期や今のコロナ禍での菅政権に対する批判を見れば、この10年で国民の政府に対する「不信や不満」は間違いなく高まっています。
では、なぜそうした不満や怒りが「こんな政治は自分たちで変えよう」という動きにつながらず、その時々の目の前の出来事への「反応」や「気分」だけで終わってしまうのか?
それは憲法の上ではこの国の「主権者」であるはずの国民に、「この国の今と未来を決めるのは、ほかならぬ自分たちなのだ」という主体性が決定的に欠けているからで、それがこの本のタイトルである「主権者のいない国」に込めた思いです。
――なぜ日本人には、主体性が欠けているのでしょう?
白井 明治維新以降、日本は西欧列強に追いつこうと「促成栽培」で近代化を進めました。そのとき、国家としての求心力を保つために利用されたのが「日本という国は天皇を中心としたひとつの家族である」という一種のフィクションです。
それはある面で近代化の成功を支えたわけですが、一方で本来、西洋的な「近代」を支える重要な要素だった人間の「自由」や「主体性」が軽視され、戦前、戦中は天皇を頂点に、戦後はその天皇に代わって事実上「アメリカ」を頂点とした従属を続けたことで、戦後憲法の下でこの国の主権者となったはずの日本人から「主体性」を奪い続けてきたのだと思います。
戦後に関してさらに言えば、経済成長が続き、米ソ冷戦下でアメリカに隷属(れいぞく)していれば済んだ時代なら、まだなんとかなったかもしれませんが、大きな時代の変化や、深刻な危機に直面すると、主体的に考える力のない国の「フェイクな近代性」が露呈してしまう。
政府の新型コロナ対応を「もはや先進国とはいえないレベル」だと感じてしまうのも、そのためです。
――一方で、反原発運動や安保法制、森友・加計(かけ)への抗議や沖縄の基地問題などで政治に関心を持ち、抗議の声を上げる人も以前より増えている気がします。それでも現実は何も変わっていません。ならば「主体性」など発揮しても無駄なのでは?
白井 僕は何も変わっていないとは思いません。例えば原発に関しては、どんどん再稼働を推し進めたいというのが政府与党や経産省の本音でしょうが、原発の存続や再稼働に対する根強い反対の声があることで、いまだに多くの原発が止まったままで、これは「曖昧なままジリジリと脱原発に進んでいる状況」だともいえる。
また、コロナ禍で国民に愛想を尽かされた安倍政権が「病気」を理由に事実上の退陣に追い込まれたのも、実際には大きな「民意」に押し出されたからだとみるべきでしょう。
一方で、安倍首相の「病気による辞任」がその典型ですが、自分たちの政策の失敗や世論の圧力に屈したことを認めたくない政権側は、メディアなどを利用しながら、巧みに自分たちの「失敗」や「敗北」を否認し続けることで、なんとか表面を取り繕(つくろ)おうとしています。
だから何も変わっていないわけではないんです。僕はむしろ「声を上げたって意味がない」「無駄だ」と、政治に対して主体性を発揮しようとする人たちを冷笑する人たちのほうが問題だと思います。
――「政治に関心を持て」とか「主権者意識を持て」と言われても、「日々の仕事と暮らしに精いっぱいで、そんな時間があったら自分や家族のために使いたい」という人も多いのでは?
白井 これは「想像力」の問題だと思います。例えば冒頭でお話ししたように、福島の原発事故は幸運な偶然がなければ福島とその近隣地域だけでなく、東日本を壊滅させていた可能性がありました。そして日本にはまだ多くの原発が存在しています。
また先日、都内で米軍のヘリが危険な飛行を繰り返していることが報じられましたが、それは沖縄で起きた米軍ヘリの墜落事故が、東京のど真ん中でも起こりえることを示しています。
そうやって想像力を働かせれば、あなたが「自分には関係ない」と思っている問題が、実は自分や自分の家族にも無関係ではないことがわかるはずです。だから、自分の暮らしを守るために「主権者」である、あなた自身が主体性を取り戻さなくてはならないのです。
●白井 聡(しらい・さとし)
思想史家。政治学者。京都精華大学教員。1977年生まれ、東京都出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。一橋大学大学院社会学研究科総合社会科学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(社会学)。『永続敗戦論――戦後日本の核心』(太田出版)により、第35回石橋湛山賞、第12回角川財団学芸賞などを受賞。そのほかの著書に『未完のレーニン――〈力〉の思想を読む』(講談社選書メチエ)、『国体論――菊と星条旗』(集英社新書)、『武器としての「資本論」』(東洋経済新報社)などがある。
■『主権者のいない国』
(講談社 1870円)
2013年の著書『永続敗戦論』で、アメリカには従いつつ敗戦を否認し続ける日本のいびつな構造を明らかにした白井氏。その端緒となった3・11から10年、これまでの論考を一冊にまとめ、「なぜ私たちは、私たちの政府はどうせロクでもないと思っているのか。その一方で、なぜ私たちは、決して主権者であろうとしないのか」を問う。