 政治社会学者・堀内進之介氏(右)と文筆家・吉川浩満氏(左)の対談が実現
政治社会学者・堀内進之介氏(右)と文筆家・吉川浩満氏(左)の対談が実現
第三次人工知能(AI)ブームと呼ばれて久しい昨今、AIに仕事を奪われるのではないかといった「脅威論」や、反対にバラ色の未来がもたらされるといった「楽観論」が展開されている。
こうした議論に疑問を投げかけ、そのどちらでもない未来のビジョンを描いた新刊『人工知能時代を〈善く生きる〉技術』(集英社新書)が刊行された。著者は注目の政治社会学者・堀内進之介氏だ。
そこで今回、文筆家の吉川浩満氏との対談が実現、人工知能の議論であまり語られていない「人間と技術の関係」について語っていただいた。
●AIには関心がなかった
吉川 AIについては、近年、多くの関連本が出版されています。その中で、今回の『人工知能時代を〈善く生きる〉技術』は、これまでにない切り口という点で非常に意義深い1冊ではないでしょうか。
堀内 そう言っていただけて、とても嬉しいです。この本の構想を練り始めた時、吉川さんと稲葉振一郎さんとの対談(「〈人間〉の未来/人間の〈未来〉」『atプラス32号 人間の未来』所収)を読んで、これ以上、何を言えるだろうかと思いながら進めていました。
吉川 いや、全く新しい内容になっていると思います。堀内さんがこの本で指摘しているのは、本来考えられるべきことなのに世間一般では驚くほど考えられていない、非常に重要な問題です。それにしても、なぜ政治社会学者の堀内さんが人工知能についての本を出そうということになったんですか。
堀内 僕自身は元々、人工知能になんの関心もなかったんです。それが3年ほど前、「自分たちが開発中の人工知能について説明させてほしい」と大手メーカーの技術開発チームから連絡をもらい、共同研究をすることになりました。
どうして僕なのか、最初はよくわからなかったんですが、どうやらその会社の偉い人が2007年に出した『幸福論~〝共生〟の不可能と不可避について』を読んで、僕に「話を聞いてくるように」ということになったらしいんですね。
吉川 宮台真司さん、鈴木弘輝さんとの鼎談という形で出された本ですね。これまでの技術の歴史においても、開発する人たちだけではなく、その技術に社会的な意味やビジョンを結びつける存在が必要とされてきたことを考えると、堀内さんを引き入れたその偉い人はなかなか勘が鋭かったですね。
堀内 ただ最初のうちはなんの知識もありませんから、共同研究といっても技術者たちの話を聞いているだけでした。でも、そうやって話を聞いていくうちに彼らが開発中の技術は、マーケティングひとつとっても、これまでの枠組みに収まらないものなんじゃないか、ということがだんだん見えてきたんですね。
場合によっては、非常に危ない方向に行ってしまうものかもしれないのに、技術を開発する側は自分たちがつくった技術がどう社会の中で使われていくのかというイメージをほとんど持っていない。だとしたら、そこをつなぐための言葉や考え方が必要ではないかと思うようになりました。
吉川 これは人工知能に限りませんが、では実際にどうすればいいのかということを考えるのが、たぶん一番難しいんです。テクノロジーの進化を人類の夢と捉える楽観論、あるいは人工知能によって未来はディストピアになると考える悲観論や脅威論、こういった話はいくらでもできてしまう。遠い未来の話であればSF的に自由に考えられるし、今ある社会の仕組みを前提にして考えるのもそれほど難しくない。
でも、今の状態から少し何かを発展させた未来を考えようとすると、どんな新たな問題が起こって、その時にはどういう選択肢があるのかということを想像していかないといけない。堀内さんはその困難な道を進もうとしていますね。
堀内 この本では2045年くらいの社会を構想してみたのですが、こういうちょっと先の未来についての話は、そもそも当たるかどうかもわからないし、いわばやるだけ損という役回りかもしれません。でも、僕にはSF的な大きな話をする才能はありませんし、日々の現実にはイヤでも巻き込まれるとなると、苦しくても難しい道を進まざるを得ないという感じです。どうして、もっと違うものに関心が向かなかったのか、とよく思いますが(笑)。
吉川 でも、「堀内、AIの本を書くなんて、うまいことやりやがって」と思っている人もいるかもしれませんよ(笑)。実際、『知と情意の政治学』や『感情で釣られる人々』など、ここ数年のお仕事を見ていると、AIブームと呼ばれるテクノロジーも含めた今の時代の流れとぴったり合流していると感じます。 
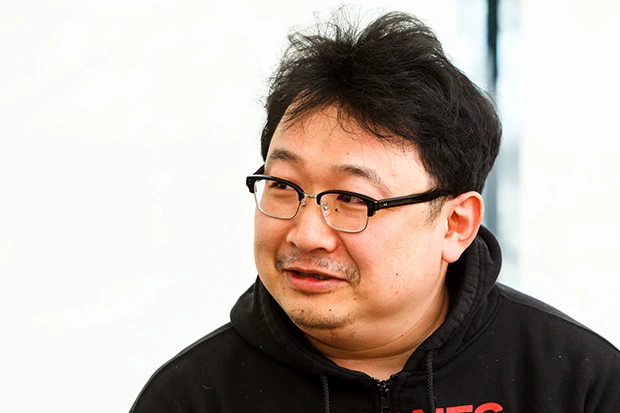
●「つながりっぱなし」の解決法
吉川 最近、日本にも続々と上陸しているAIスピーカーは常にプラグインされている社会の象徴と言えますし、世の中の流れもそうした「足し算」の方向にどんどん向かっているように思います。けれども、常にプラグインされていることが本当にいいことかどうかはわからない。
例えばスマホやSNSに対する「つながりっぱなし」のストレスは多くの人が感じているはずです。どうにかしないといけないということはわかっていても、ITの断捨離みたいなことは事実上不可能でしょう。その解決策として堀内さんがこの本で提唱されているのが、「アンプラグド・コンセプト」です。
ただ、「アンプラグド・コンセプト」は厳密には「引き算」というわけではなくて、技術にアウトソーシングできるところは思い切りハイテクにして、それによって「つながらない」環境をつくり出すという点が非常にユニークです。
堀内 たぶん、技術をどんどん「足し算」していく世の中の流れはこのまま続くでしょう。けれども、そうした過剰さを推し進めるだけでは、やはり耐えられないということになっていくと思います。「アンプラグド・コンセプト」は、いわば「足し算」の大きな流れの中でどうバランスを取るか、という試みです。
バランスを取るためには、どこか一点にウエイトを置くのではなく、過剰な部分をちょっと置き換えてみる。僕はいつも「砂漠にも日陰はある」と思っていて、自分の人生の中でずっとやってきたことでもあるんですが、それだけでも随分楽になります。
ミシェル・フーコーが「ローカルな抵抗が大事だ」と言っているように「アンプラグド・コンセプト」はAI時代における実践的かつローカルな抵抗という発想なんです。そういうことを頭でっかちになりすぎないで、実践的に考えていきたいと思っています。
吉川 そのスタンスは、本書のタイトルにある〈善く生きる〉ということにもつながっていきますね。
●パーソナルデータと個人の利得
吉川 ところで、AIをめぐる議論の中で、グーグルなどに自分のパーソナルデータを勝手に活用されることをイヤがる人もいますが、僕にはその感覚はあまりないんです。
堀内 僕も同じです。何かでそのデータが悪用されて、不正に預金を引き出されたりするなどの実害がなければ、パーソナルデータを取られることで自分の何かが侵害されたとは感じません。
吉川 もちろん、プライバシーの問題は存在するわけで、法制度も「個人情報が取られるのはイヤだ」という気持ちを前提にして一応つくられつつあります。それで本当に大丈夫なのかどうかはわからないですが(笑)。
堀内 今は、パーソナルデータを分析して、よりその人にふさわしいリコメンドをするというサービスが増えてきていますよね。サービスを提供する企業の側は、最終的にはそのサービスを利益に還元しなければいけないわけですが、今の時代は企業の利得ばかりを追求していたら、企業イメージが悪くなって、結果的にはその商品が売れなくなってしまいます。
そうなると、企業利得ではなくユーザー個人の利得を追求するということになりますが、何が個人の利得になるかということについては、実は誰も明確な答えが出せていないんです。
吉川 例えば、ある人の購入履歴をAIが分析して、「この人は堀内さんの新書を買うはずだ」と判断し、ドローンでその人の家の玄関前まで本を配達しておいて、ショッピングサイトの購入ボタンを押した瞬間にもう届いているということが、いずれは可能になっていくでしょう。それを「気持ち悪い」と思うか、「便利だ」と思うかは、こう言ってはなんですが、その人が自分の人生を自分でハンドルしているという感覚がどのようなものであるかに依存するのではないかと思います。
堀内 今後、リコメンド機能のJISマークのような統一規格をつくって、社会的に「これはやってもいいが、それはだめ」という線引きをする必要が出てくると思います。あとは、仰るように個人のレベルでどう考えるかですね。
自分でハンドルできているかどうかの感覚ということでは、AIスピーカーは本来、ユーザーにとっては「スピーカー」ではなく自分のコマンドを入力する「マイク」なんです。しかし、こうした捉え方は自分が主体的な行為者でありたいという意識が根底にあるんですね。
吉川 それは興味深い話ですね。ただ、この地球の生物自体がわけのわからない偶然の中で勝手に進化させられてきただけだと考えれば、あんまり純粋に主体性を追求してしまうと、そんなふうにつくられたこの世界そのものを認めないということになりかねない。主体性については、ありなしではなく程度と種類、そこから得られる感覚を繊細に考えなくてはなりませんね。
 ●人間中心主義を見直す
●人間中心主義を見直す
堀内 「ホモ・デウス」という、やがて人間はAIと融合し、人間を超えた存在になるという議論がありますが、そうしたトランス・ヒューマンの世界はなかなか僕の想像力では及びません。一方、ポスト・ヒューマンということであれば考えてみてもいいのではないかと思っています。つまり、人間中心主義という、今の社会を支えている価値観を見直すということですが、吉川さんはどうお考えですか。
吉川 結論から言うと、見直さざるを得ないと思います。人間中心主義が想定するような自立した人間など実際はいないとしても、一応その理念に基づいて社会の制度はつくられてきたわけです。ところが、20世紀後半以降、テクノロジーの進展によってそうした人間中心主義を基盤とする社会の矛盾が明らかになってきたというのが、今に至る流れでしょう。
堀内 大きな社会的なビジョンとしては、もう人間が中心ではないという流れがあって、AIスピーカーのようにそれを踏まえて構想されたサービスであっても、ユーザーは「自分が中心」と思って使っているというところに、今は過渡期なのだなと感じますね。
吉川 おそらく今後は人間中心主義を少し捨てる、ということになると思います。全面的に捨てるわけにはいかないから、少し捨てる。その捨てた部分を埋めるために技術を使おうというのが堀内さんの提案ですよね。でも、「捨てる」ことはそんなに悪いことじゃない。
「自立」ということを人間中心主義の理念で純粋に考えていくと、自分以外のものに頼ってはいけないということになりますが、これからの時代であれば、例えばAIアシスタントのようなテクノロジーに依存することで、より自由になれる部分が出てくるはずです。
それは、まさしくテクノロジーが進化したおかげで生活の中に技術を有機的に入れやすくなっているわけですから、それを利用すればいい。
堀内 僕は儒教の『大学』にある「修身斉家治国平天下」という言葉が好きなんですが、これは「天下を治めるには修身から」という話です。実は、修身の前にもいくつか段階があって「格物致知誠意正心」、つまり正しく物事を見極めるところから始まって、知識を得て、誠実になって心を正すと、やっと修身ができる。
でも、そんな大変なことをひとりではできそうもないわけで、それをどうやって解決するのかということは以前から考えていたんです。技術の分野と関わるようになって、「あれ、『格物~』の部分は全部AIで補ってもらえるんじゃないか」と気づいたんですね。特に「物事を適切に判断する」という「格物」なんて、AIの得意分野じゃないですか。
「致知」にしても、もうAIのほうが優れていますし、人間は感情に流されて誠意をもって振る舞おうとしてもできないこともある。それに、心を正しく持つなんて、そう簡単にはできません。こういう、人間ではうまくいかないところを技術に補完してもらえたらいいなと思うんです。一般的には「修身」以降を技術に任せるという議論になりがちですが、順番を逆にしたほうがいい。
吉川 それがファイナルアンサーかもしれませんね。そのためのAIアシスタントだと。確かにそう考えるとジレンマは解消されますね。ホモ・デウス的な議論も面白いですし、おそらくその中のいくつかは実際に未来を変えていくことになると思いますが、不確実な予想にすぎない未来論とは違う次元で、これからの我々の生活や社会をどう考えていくかということは非常に大事です。
30年後も楽観的でいたいなら、この本で書かれていることをよくよく考えないといけない。読者には「この本を読めば、少しでも賢く、少しでも楽しく生きていけるビジョンが見つかります」と本書を勧めたいですね。
※この対談は「青春と読書」4月号に掲載された記事を転載したものです。
(構成/加藤裕子 撮影/三輪憲亮)
■堀内進之介(ほりうち・しんのすけ) 1977年大阪府生まれ。博士(社会学)。首都大学東京客員研究員。現代位相研究所・首席研究員ほか。朝日カルチャーセンター講師。専門は、政治社会学・批判的社会理論。単著に『知と情意の政治学』、『感情で釣られる人々』、共著に『AIアシスタントのコア・コンセプト』、『人生を危険にさらせ!』、『悪という希望』など多数。
■吉川浩満(よしかわ・ひろみつ) 1972年鳥取県生まれ。文筆家。慶應義塾大学総合政策学部卒業。国書刊行会、ヤフーを経て、フリーランス。関心領域は哲学/科学/芸術、犬/猫/鳥、デジタルガジェット、映画、ロックなど。主な著書に『理不尽な進化─遺伝子と運のあいだ』、『脳がわかれば心がわかるか─脳科学リテラシー養成講座』(山本貴光氏との共著)ほか。
『人工知能時代を〈善く生きる〉技術』(集英社新書、720円+税)
