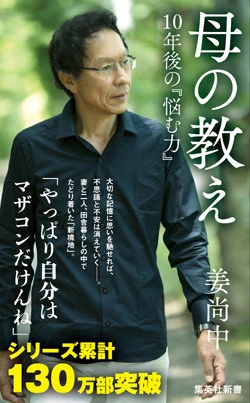「母の教え 10年後の『悩む力』」の刊行記念トークイベントをする姜 尚中氏
「母の教え 10年後の『悩む力』」の刊行記念トークイベントをする姜 尚中氏
2018年10月31日(水)、姜 尚中(カン・サンジュン)氏の最新刊『母の教え 10年後の「悩む力」』(集英社新書)の刊行を記念して、福岡県博多市でトークイベントが開催された。
ミリオンセラーとなった『悩む力』の刊行から10年。その間の出来事を振り返りつつ、現在の心境について姜氏が語ったトークの内容を、ダイジェストでお届けしたい。
* * *
■『悩む力』は高校時代の着想がきっかけ
本日はお集まりいただき、有り難うございます。このトークイベントは最新刊『母の教え』の出版を記念した催しということですが、ここで最初に今までのことを振り返ってみたいと思います。
10年前に『悩む力』というタイトルで本を書いた時には、実はベストセラーになるとは夢にも思っていませんでした。何しろ、私が人生で最初に自分で本を出したのは学術書で、初版が500部でした。この学術書を出した時には、印税をもらうどころかこちらからお金を出して、本屋さんに「こういう学術書を出して欲しい」とお願いをしたんですね。それが増刷がかかって、2刷で1000部まで売れました。
その時には、もう天に昇るぐらいに喜びました。それがちょうど、30代の初めごろだったでしょうか。だから、『悩む力』がベストセラーになった時は、あまりのことに現実感がありませんでした。そして同時に、どうしてだろうかと不思議に感じたものです。
実は『悩む力』は高校時代の思いつきがもとになっています。私は小学生の時に、春のセンバツで優勝したことがあるほどの野球少年でした。どういうわけか、母親も強く期待を寄せていて、私に「野球でとにかく名をなしなさい」と繰り返していました。「お前の場合は頭も悪いし、大学に行っても職は無いだろう」と。もう「グラウンドには金が落ちている」と言わんばかりの勢いでした。まあ、さすがにそこまであからさまには言わなかったのですが(笑)。
ところが、高校時代になると、挫折をしてしまいます。そして私は引っ込み思案になり、不登校ぎみになってしまったのです。そういう時期に、前々から好きだった夏目漱石の小説をかなり読みました。
そうして、どんどん読み進めていく中で、ふと思ったわけです。「あっ、この人は"悩める人"だな」と。それが、悩んでいる自分の姿にも重なったのでしょう。それで、「そもそも悩むとはどういうことなのだろうか」と考えるようになりました。色んな本を手に取るようにもなりました。いま振り返れば、そうした蓄積から生まれたのが『悩む力』だということになります。
『悩む力』の根底にある思想は、"悩める人間の方が、悩みの無い人間よりも充実した生を送っているのではないか"というものでした。これはある意味では、「悩みの海」の中でもがいていた高校時代の自分に向けたメッセージにもなっていたのかも知れません。
後に知ったことですが、実は非常に似たことをV.フランクルという、20世紀の戦争中から戦後にかけてウィーンで神経症の専門医として活躍した人物が言っています。皆さんは彼のことを、『夜と霧』という本の著者としてご存じかもしれません。
ちょうど彼の本を読んでいる時に、合点がいったんですね。古今東西、お医者さんであれ、文学者であれ、皆が人生の悩みをそれぞれの立場で考え抜いてきたのだ、と。『悩む力』というのは、そうやって高校以来ずっと考えてきたことをまとめた一冊でした。
■「不確実な現代は「悩みの時代」である
なぜ『悩む力』を出版したのが10年前だったのかと言えば、それは時代背景とも重なっているように思えます。戦後日本の歩みを要約すると、国民が一丸となって努力をして、豊かな社会をつくろうという目標に向かってきた。その豊かな社会というのは、安心・安全・快適という言葉で言い表されると思います。
そして、今はその快適さを極限まで求めることが当たり前になっています。でも、それは本当に我々を幸せにしたのだろうか、という疑問がようやく浮かんでくるようになってきたのではないでしょうか。
振り返れば、1995年には阪神淡路大震災が起きました。その2年後、1997年には北海道拓殖銀行、山一證券に長期証券銀行が次々と破綻・廃業しています。10年前の2008年にはリーマンショックが起こり、突然の経済的な落ち込みが日本を襲いました。そして7年ほど前に、阪神淡路大震災よりもさらに大きい、東日本大震災が起こりました。2016年の熊本地震では、私も被災をしています。
そうした大きな出来事の連続にさらされていると、これまで揺るがないと思っていた足元がぐらつくような感覚にとらわれます。私は1950年に生まれ、日本の高度経済成長とともに思春期を送り、そして安心・安全・快適というものが社会の目指すべき方向であり、自分もその恩恵に与ってきた身です。
かつては「ずっとこういう方向に進めば良いんだ」と思っていた時期もありました。しかしそんな自分の足元が、いわば液状化のようにぐらついている。そうした感覚が10年前に強まっていたからこそ、「悩む」ということを主題に本を出そうと思ったのでしょう。
現代をひと言でまとめるならば、「不確実性の時代」ということになるでしょうか。戦後の、いわば高度成長期の申し子のような私は、「今日は昨日よりも良い」「1年後は半年後よりもずっと良い」というような、確実に自分たちはこうなるはずだ、というビジョンがある程度共有し合えた時代を生きていました。
それはつまり、皆が安心・安全・快適を求めて頑張ることができた時代です。それが、70年も経つと大きく変わってしまった。言ってみれば、明治以来目指していた「坂の上の雲」の中へやっとたどり着いたと思ったら、雲の中で晴れ間が見えない、そして身動きが取れないという状況にあるのではないかと思うんですね。確かなものが考えられなくなってしまった。
そうなると、何か強い信仰や、確固として信じているものがあれば話は別ですが、そうでない方々は心のなかに不安を抱えて生きざるを得なくなります。そして、そんな日々の不安から多くの方が「悩んで」しまう。そうした現代人の心に響いたことで、『悩む力』は驚くほどのベストセラーになったのだろうと私は分析しています。

■最後の拠りどころになった「母の教え」
そうした不確実性の時代の中で、私自身も個人的に色々なことを経験しました。姜 尚中という戦後の申し子のような人間が、これまで何を信じて生きてきたのか。そしてその信じたものは、間違いなくこれから先も永続するのか、と問いかけられているような錯覚にも陥りました。そうした中で、自らの来し方を見つめ直してみたいと思うようになりました。
これまでの前例があまり当てにならない。そして他人の言うことをただ聞いていれば良い時代は、もう終わってしまった。そういう時代の中で、最後に私の拠りどころになったものが、母の教えだったわけです。
彼女が遺してくれた言葉のひとつひとつが、中高年の時期を過ぎて、あらためてリアリティを持って迫ってくるようになった。それを私自身はこの歳になって噛み締めながら、同時にどうやったら今のこの世界の中で起きている出来事を見て、解釈したら良いのかを考えながら書いたのが、今回の『母の教え』という本です。
母の教えというのは、大きく言えばいくつかに集約できるように思います。そのひとつが「食」に関するメッセージです。私はこの歳になるまで、大病を患ったことが一回もありません。唯一、入院したのは自然気胸ぐらいです。それだけで、後はどんなに無理をしても大病を患っていません。その健康を支えているのは、「どんなに忙しくても、旬のものを3食しっかりとるようにする」という母の哲学だと信じています。今でも、朝食から夕食に至るまで、たとえ予定が詰まっていても欠かすことはありません。
約5年前に軽井沢に引っ越したのも、母の言葉の影響だと思います。今では東京から1~2時間ほどの距離を置いた場所に居を構えています。東京に出る場合は、そこから新幹線に乗って通っている。つまり、東京からまったく離れた場所ではないのですが、1時間で行ける長野県に身を置いている。そうすると、ほどよい距離感のもとで東京がよく見えてきます。
現在の日本を知るためには、東京について知ることが不可欠です。東京を知るためには、遠くに離れ過ぎてはいけません。しかし、近過ぎても却って客観的に見ることが難しくなる。私は若いころは首都圏に住み、その中で暮らしていたので、冷静な眼差しで東京を見つめることができませんでした。ほど良い距離を取って、相手を見つめなければいけないのですが、その間合いというのがこの歳になって、やっとわかってきたように感じています。
同時に、距離をとって自分の人生を眺め、そして世界に起きている出来事を見つめることができるようになりました。この、距離感覚ということは、人間関係に気を配り続けていた母親の「生きた知恵」が参考になっています。
■人生は最後の瞬間まで「継続中」である
私は古稀に近い歳になって、やっと静かな生活を送れるようになったと思っています。終の住処になるところを見つけ、心の準備を始めつつ、自然に親しみながら穏やかな日々を送っています。そうした現在の境地や暮らしぶりについて、今回の『母の教え』では綴りました。
これだけ自らの私生活を明かしたことは無いので、そうした意味では新鮮な一冊に仕上がったのではないかと思います。ただし、今回の本の中では「終活」という表現を使っていません。そもそも、私は「終活」という言葉が好きではありません。
漱石は第一次世界大戦の戦間期に『硝子戸の中』というエッセイを書いています。晩年、彼は大病を患っています。色々な人が心配して、お見舞いの手紙を寄越してくる。そのうち、ひとつひとつ返事を書くのも面倒だと言って、最後はどう言うようになったか。「病気はまだ継続中です」。そして、「私は丁度独乙(注:ドイツ)が聯合軍と戦争しているように、病気と戦争をしているのです。(中略)私の身体は乱世です。何時どんな変が起らないとも限りません」。そう表現しています。
つまり、人間にはある一点ですべてが完結してしまうような「終わり」は無い、最後まで継続していく。そういうような生き方について、彼は述べているんですね。漱石は「継続中」という表現が気に入ったようで、同じ『硝子戸の中』でこの言葉に出逢ったときの心持について、「好い事を教えられたような気がした」と綴っています。
私もこの言葉が大好きです。だからこそ、「終活」という言葉に違和感を覚えます。人生は最後の一秒まで、生きている限り、すべてが「継続中」なのです。ある瞬間にすべてが終わるような終端を設定して、そこに向かっていくという見方はどうも好きになれません。
これを前半でお話しした「悩む」ということに結びつけるならば、「悩む」ということもまた、問いをある瞬間に手放してしまうのではなく、最後の瞬間まで粘り強く知性を働かせるということではないでしょうか。
私にとって最もうれしいことのひとつは、私の言葉を受け取ってくれる方がいることです。私にとってそれは、読者の皆さんです。特にうれしいのは、3世代にわたっておいでになった方がいらっしゃる時ですね。「ああ、そうか、自分が仮にいま亡くなっても、この人たちは100年にわたって自分のことを忘れずにいてくれる」と思えると、非常に心が晴れがましくなります。
そして同じようなことを、母親も言っていました。「我々は縦の流れの中に生きていて、決してひとりではない」という言い方でした。そのことを最近になって、つくづく考えるようになりました。私は筑紫哲也さんという人物に、ずいぶん仲良くしていただいていました。彼が最晩年に書いた本が『旅の途中』(朝日新聞出版)というものですが、ここでもやはり「途中」になっています。漱石はこれを「継続中」と表現したわけです。つまり、人生に終わりは無く、すべてが途中だという思想です。
筑紫さんの『旅の途中』には、「自分はこれまで出会って来たもの全ての部分」(I am a part of all I have met)という格言が引用されています。これはイギリスのテニスンという詩人の言葉です。この言葉には私も強く感銘を受けました。筑紫哲也という人もまた、私が出会ったすべての人の中の、非常に重要なひとりです。私の母親もそうした大切な一人です。
人間の生命というのは、あるところで途絶えてしまうにしても、必ずそれまで出会った人々から色々なものを受け取っている。そんなことをつらつら考えながら、私がこれまでたくさんのものを受け取ってきた「母」と、その言葉を噛み締めながら生きている現在の私について、総括のつもりで書いたのが今回のエッセイです。是非、ご一読ください。
※『硝子戸の中』の引用は、岩波文庫版の表記を基にしました。