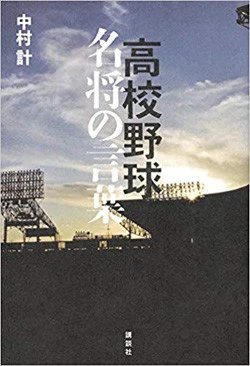この10年、春夏合わせて6度の全国制覇を果たした大阪桐蔭の西谷監督。「最強世代」と呼ばれるメンバーを擁する今夏は果たして?
この10年、春夏合わせて6度の全国制覇を果たした大阪桐蔭の西谷監督。「最強世代」と呼ばれるメンバーを擁する今夏は果たして?
勝利に執着する男、奇想天外な練習で常識を覆した男、選手起用の神髄を知り尽くした男、先攻めにこだわる男、10-0を理想とする男、大阪の野球にこだわる男......高校野球に取りつかれた男たちの珠玉の名言集がここに!
■「雪あんだったらどけりゃいいじゃない」
日本で2番目に高い山は何か――。答えは、3193mの北岳(きただけ)だ。日本一の山、富士山の名前は言えても、2番目の山を言える人はそうはいない。そんな前フリをしながら「だから優勝しなければ意味はないのだ」と高校野球の関係者はよく口にする。
この夏、全国高等学校野球選手権大会、通称「夏の甲子園」は100回目を迎える。これまでの99の優勝校に比べ、記憶されることの少ない99の準優勝校のうちのひとつに、04年夏、駒大苫小牧(北海道)に10-13で敗れた済美(愛媛)がある。
「球運、われに味方せず......」
済美の監督、上甲(じょうこう)正典(故人)は試合後、ベンチ前で、ほうけたようにそうつぶやいた。
この年のセンバツで「初出場初優勝」を果たした済美は、続く夏の甲子園でも決勝まで駒を進め、勝てば春夏連続で「初出場初優勝」という大記録がかかっていた。ここまでくれば準優勝でも十分と考えるのは凡人、上甲はどこまでも貪欲だった。
「優勝と準優勝の違いは天と地よ。ただ、いつもは『決勝であることは忘れろ』と言ってきたのに、この試合の前に『4000校の中で不世出の記録に挑戦できるのはおまえたちだけだ!』と言ってしまった......。ちょっと欲が強すぎたわい」
甲子園において、優勝という最良の結果を出せるのは約4000分の1。甲子園が今日まで100年間も続いた理由は、一校の歓喜ではなく、約4000校分の、この悔しさがあったからだ。
* * *
球運といえば、こんなにツイていた男はほかにいない。
「地面が茶色いか白いかの違いだけだから」
04年夏、前述の上甲率いる済美を破り、東北・北海道勢として初めて全国制覇を遂げた駒大苫小牧の元監督・香田誉士史(こうだ・よしふみ)(現・西部ガス監督)の言葉だ。その年の冬、苫小牧を訪れると、軽い吹雪の中選手らは平然と紅白戦を行なっていた。おそらく雪上でここまで本格的な試合をしたチームは史上初ではないか。
「トンボでならして、その上にうっすらと雪が積もるくらいがちょうどいいんだよ」
吹雪の中、当時、1年生だった田中将大(現・ヤンキース)がものすごいボールを投げていたのが印象的だ。
香田が続ける。
「雪の上で練習しない理由なんて探そうと思えばいくらでもある。でも無理だって言わなければ、なんでもできる」
雪国として初めて夏の甲子園優勝を果たした香田は、チームを翌年も優勝、翌々年は準優勝に導く。香田のように不可能を可能にする男は、常人とどこが違うのか。
「月を見てウサギが住んでると思った人はそこまでの人。なんとかすれば行けると思った人がいたから、人類は月に行けるようになった。最初に行けるって言った人はバカにされたと思うよ。野球も同じ。できるはずだって信じた人間が道を切り開いてきた」
そう語るのは、興南(沖縄)の監督、我喜屋優(がきや・まさる)だ。「北の暴れん坊」と恐れられた企業チーム・大昭和製紙北海道(93年に休部)の元監督でもある。我喜屋は北海道時代に香田と出会い、「雪あんだったら、どけりゃいいじゃない」と雪上練習を促した人物である。
我喜屋もこれまでいくつもの歴史の扉を開いてきた。高校時代は興南の主将として68年夏の甲子園に出場し県勢初のベスト4、社会人時代は74年に道勢初の都市対抗制覇、そして母校、興南の監督となり10年に春夏連覇を達成した。
我喜屋は沖縄に戻ってきたばかりの頃、地元の方言「なんくるないさ(なるようにしかならない)」という言葉を引き合いに出し、こう話していたものだ。
「38年ぶりに戻ってきて、『なんくるならないんだよ』って言ってたら、おまえは沖縄の人間じゃないって言われた。それは沖縄の文化だぞって。でも勝負は『なんくるないさ』じゃ勝てないよ。内地の電車は待ってくれないよ」
■「育てて勝つより、勝って育てるほうが簡単」
名言といえば、取手二や常総学院(共に茨城)で監督を務めた木内幸男はその宝庫だった。木内は選手のことを「鵜飼(うかい)の鵜」にたとえた。
「ヒモつけてたほうが勝てるんだよ。でも、鵜飼いは今、はやらねーのよ。選手がヒモ、いやがるから。かといって『任せる』って言葉はきれいだけど、それじゃ誰も授業料、払わないでしょう。いろんなこと教えてもらえるから授業料払うんでさ」
木内が巧みだったのは、ヒモを握りつつも、選手にはその存在を忘れさせていたことだ。「伸び伸び野球」と評された木内野球は、実際は、伸び伸びと"見えた"野球だった。
高校野球は教育の一環だといわれる。しかし、木内は決して野球を「教育」の下に置くことはしなかった。取手二を率いて茨城勢として初めて優勝監督となった木内の言葉だ。
「それまで県内では高校野球は人間修養の場だという考えが主流だった。勝ち負けよりも立派な人間をつくるんだ、と。でも、勝って不幸になる人間はいないのよ。勝てばうれしい。だから我慢ができるようになる。勝てば何言ったってホントに聞こえてくるからな、ガハハハハ。育てて勝つより、勝って育てるほうがはるかに簡単なの。それに気づいちゃった!」
* * *
高校野球において、極端に先攻めが好きな監督もいれば、逆に後攻めを選びたがる監督もいる。智弁和歌山(和歌山)の髙嶋仁(ひとし)監督は前者の典型、先攻め至上主義者である。その理由を問うと、当然のようにこんな答えが返ってきた。
「そうやなきゃ、100安打、超えられんやろ」
チーム安打数の大会記録、100安打。これは00年夏、智弁和歌山が3度目の全国制覇を遂げたときに築いた金字塔だ。先攻めなら毎試合、9回攻撃できるから、その分、記録更新の確率は高まる。最初は冗談かと思ったが、髙嶋の目は笑っていなかった。
高校球界では有名な話だが、智弁和歌山は極端なスロースターターである。県大会の決勝前あたりから徐々に調整に入り、甲子園でピークになるよう仕上げるのだ。
「うちは和歌山県大会の何回戦とかは、目の中にないんです。県大会といったら、頭の中には決勝戦しかない。だから、大会に入ってもギリギリまで追い込むし、決勝をにらんで最初のほうはエースを放らせなない。
1、2回戦あたりは、ビース(2番手)、シース(3番手)あたりが投げる。それで負けたらその程度のチームってことですよ。どうせ甲子園に行っても勝てない。だったら、1回戦で負ければよろしいやん」
そんな髙嶋以上に「打撃至上主義」に思えるのが、日大三(東京)を率いる小倉全由(おぐら・まさよし)だ。小倉は理想の野球をこう語る。
「僕はいつも10-0で勝ちたいと思ってるんですよ」
日大三と対戦することになったある高校の監督に、この小倉哲学をぶつけると、
「考えられませんね。私は試合が終わったら1点勝ってる、そういう野球を目指している」と嘲笑した。
おそらく10人中9人までが、野球とはそういうものだと思っているはずだ。サッカーのように得失点差が順位に影響することのない野球というスポーツは、一勝はどこまでいっても一勝である。
だが、小倉はこう言う。
「ОBの集まりなんかがあると、年配の方は『三高野球とは1点差で競り勝つ野球だ』って言うんです。でも、攻撃が1回しかないなら1-0とか、2-1でもいいですけど、せっかく9回できるわけだから、もったいないじゃないですか。でも、そう言うと『だから守備が甘くなるんだ』って言い返される。いや、だから守りは0点に抑えるって言ってるんですけどね」
6点差、7点差くらいで買っても小倉監督は「もっと打たないとダメですね......」とぼやくのが常。小倉の頭の中にある野球は、ある意味、ファンタジーだ。
だが小倉はこれを空想では終わらせなかった。11年夏、決勝の大舞台で、理想を1点上回る11-0で10年ぶりの全国制覇を遂げたのだから。
■「大阪の野球は勝ちにこだわる野球」
髙嶋や小倉が攻撃的野球の代表格だとすれば、守りの野球のそれは明徳義塾(高知)の馬淵史郎だ。だが、地味に映る守りの野球はファンの支持を得にくい。その象徴が92年、星稜(石川)の松井秀喜を5敬遠し、3-2で勝利した試合だった。当時、社会現象にもなり、大バッシングを浴びた馬淵は後年、こう語っている。
「極端に言えばね、玄人さえわかればいいと思って野球をやっていた時期があるんです。玄人が見て、あいつはよう野球を教えているって思われたいと。これが俺の出発点。でも、それが間違いやった。
玄人受けしかしないのは二流なんですよ。大衆のほうが圧倒的に多いわけやから、大した芸でなくても大衆に受けがいい役者とか歌手のほうが一流になれる。玄人はだしで味がある......なんて言われるのは所詮、みんな二流ってことなんですよ。だからって、いまさら生き方を変えられるものでもないんやけどね」
あのとき36歳だった馬淵は今年62歳になった。男の哀愁漂うセリフである。
さて、いよいよ100回記念大会が幕を開ける。
長く甲子園を見ているが、大会中、まるで竹のように目に見えて大きくなっていくチームがある。07年夏に優勝した佐賀北(佐賀)もそうだった。優勝インタビューで監督の百﨑敏克(ももざき・としかつ)は、こう感慨深げに語った。
「選手たちはとっくに私の手元から離れてます」
選手が監督を超えるとき。チームにおいて、それに優る飛躍期はないように思える。とはいえ「親」は「子」を庇護(ひご)下に置いておきたいもの。子が巣立とうとしている瞬間を見極め、子離れできる監督であるか否かが、勝てる監督の条件のうちのひとつだ。
百﨑といえばもうひとつ、忘れられない言葉がある。選手たちの親離れを実感したというこの年の準々決勝、優勝候補の帝京戦の試合前のことだった。百﨑は静かに言った。
「うちが勝つと思っている人は誰もいない。確かに、練習試合だったら10回中10回負ける。でも、本番は違う」
約4時間後、佐賀北は4-3でジャイアントキリングを起こしていた。
* * *
思えば、10年前の08年夏、頂点に駆け上がったのは大阪桐蔭(大阪)だった。学校としては17年ぶり2度目、西谷浩一が監督に就任してからは初めての戴冠だった。
西谷は大会中、こう繰り返していた。
「大阪が弱くなったといわれて悔しい。大阪桐蔭はもちろん、大阪の野球を見せたい」
PL学園の勢いが衰え始めた90年代から2000年代、大阪府内の有力選手が県外に流出してしまったこともあり、大阪勢の低迷期だった。90回目の夏の甲子園という節目の大会で頂点に立った直後、西谷監督に「大阪の野球とは」と尋ねると、こう即答した。
「勝ちにこだわる野球です」
あれから10年――。08年も含めると大阪桐蔭は実に6度も全国を制した。完全なる「大阪復権」だ。締め切り時点ではまだ北大阪代表は決まっていないが、巷(ちまた)では、今年の春の王者である大阪桐蔭のメンバーは「最強世代」と呼ばれている。だが西谷は決まってこう否定する。
「そんなこと言ったら、過去の先輩に対して失礼。最強世代なんて、マスコミがつくり上げた虚像ですよ」
なかなか本音を見せない指揮官だが、西谷の言葉に耳を傾けていてひとつ気づいたことがある。それは、謙遜しているときほど自信があるということだ。
■『高校野球 名将の言葉』
中村 計・著
講談社 1500円+税
現役の名将に加え、甲子園史に名を刻む伝説の監督たちへのインタビューが一冊に