 「現代の魔法使い」落合陽一(左)と「ゲームプロデューサー」鈴木達也(右)
「現代の魔法使い」落合陽一(左)と「ゲームプロデューサー」鈴木達也(右)
鈴木達也(すずき・たつや)はゲーム開発に携わって25年になる、ベテランのゲームプロデューサーだ。ゲームボーイ、Nintendo64、プレイステーションシリーズなどなど、多くの機種でソフトを作り、近年はスマホゲームにも進出している。プログラミングを独学していた少年時代も含めると、ファミリーコンピュータ(ファミコン)以来のゲーム史とほぼほぼ重なる半生だ。
かつては"子供たちの遊び"に過ぎなかったゲームの地位はすっかり上がった。コミュニケーションツールとしての活用、そしていまだ実装途上のARやデジタルツイン(仮想空間に物理空間の環境を再現する技術概念)といった領域の先遣隊としても期待されている。これからのゲームはどこへ向かうのか?
* * *

鈴木 初めまして、鈴木達也と申します。ゲーム業界25年の"老兵"でございます。現在は「125(イチニゴ)」という自分の会社をやっていますが、その前はソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)でゲームを作っておりました。
簡単に来歴をお話します。僕は1973年に静岡県の片田舎に生まれました。ひとりっ子だったせいもあってか、小さい頃は寂しがり屋で、家に遊びに来ていた友達が帰った後にこっそり泣いちゃうような子でした。
そんな寂しいときにはテレビを見て慰められていまして、人が心安らげるものとか楽しめるものを作るってすごいことだな、と。やがて、自分でも何か作りたくなりました。
その"何か"は小説でもアニメでもなんでもよかったんだと思いますが、小4の頃、ファミコンという衝撃的なものと出会い、人を楽しませるメディアとして、ゲームというのは最高なんじゃないかと考えるようになりました。
そこからプログラミングを学ぼうと思ったのですが、当時は情報がとにかく少なかった。今だったら「Unity」とか「Unreal」といった誰でも使えるゲームエンジンがあり、それぞれの解説書も潤沢、さらにネットで調べたりチャットで質問したりすることもできますが、そういうものは一切ありませんでしたから。地元の書店にあるいくつかの専門書や月刊誌を買って、隅々まで読んで勉強しました。
高校を出た後は情報系の専門学校に進み、1年目で情報処理技術者試験の一種に合格しました。そうなると学校的には免許皆伝のような扱いで、卒業生の方々が就職した企業さんでバイトさせてくれるんですね。学校に籍を置きながら、いろんな現場でプログラムを書かせていただきました。

落合 その頃のゲーム開発は、なんの言語を使っていたんですか?
鈴木 当時は、ゲーム開発を志すのであれば「アセンブラ」でした。CPUに直接命令できるマシン語という数字の羅列を、ワンステップだけ人間寄りにしたような低級言語ですね。
ファミコン、スーパーファミコンはアセンブラです。それ以降のゲーム機(プレイステーションやNINTENDO64など)から「C」や「C++」が使われるようになっていきました。
それから僕は1996年に株式会社元気という会社に就職し、まずNintendo64用のソフト開発に携わりました。その後、仲間と起業して、ゲームボーイ用のソフトを作っていたのですが、次第に行き詰まり、いったん地元・静岡の富士通に入ります。ここでは携帯電話用のプログラムを書いていました。後に「ガラケー」と呼ばれるものです。
あとはカーナビ関連ですね。勤めていた事業所ではアセンブラが書ける人が少なかったので重宝されました。
落合 富士通のガラケーとかカーナビ、懐かしいですね。ジャパンが超強かった頃だ。
鈴木 強かったですね。自国の市場だけを見て「新しいものを作るぞ、出すぞ、みんな買ってくれるぞ」という気運がありました。
2003年に再び上京しましたが、これは彼女――のちの妻です――が「東京へ行く」と言うので「じゃあ俺も」という軟派な理由でした。SIEから「経歴が面白いからプロデューサーやってみなよ」と採用していただいて、そこからソニー時代が始まります。
この時期に作ったゲームをひとつ紹介させていただきますと、『無限回廊』があります。

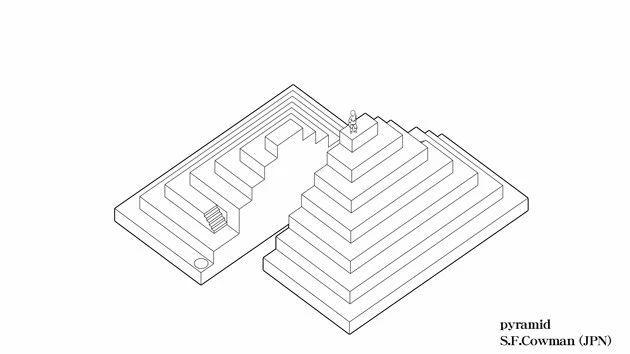 鈴木氏がSIE時代に手がけた名作パズルゲーム『無限回廊』シリーズ(PSP、PS3)。九州大学大学院芸術工学研究科に在籍していた藤木 淳氏による錯視をテーマにしたインタラクティブアート作品(文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞を受賞)を土台にして製作された。©2008 Sony Computer Entertainment Inc.
鈴木氏がSIE時代に手がけた名作パズルゲーム『無限回廊』シリーズ(PSP、PS3)。九州大学大学院芸術工学研究科に在籍していた藤木 淳氏による錯視をテーマにしたインタラクティブアート作品(文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞を受賞)を土台にして製作された。©2008 Sony Computer Entertainment Inc.
落合 『無限回廊』は超面白かった!
鈴木 ありがとうございます。これは"錯視"を用いたパズルゲームで、アイデア自体がすごいと高評価をいただきました。
当時、九州大学にいらした藤木 淳さんのPCで錯視を体験できる『OLE Coordinate System』という作品が文化庁メディア芸術祭で優秀賞を受賞されていて、その展示を見た僕がすぐにメールを送らせていただいて「ゲームにするともっと一般の人に広まると思うので、一緒にやりませんか?」とご提案申し上げた、という経緯があります。
自分たちだけでやっていると、どうしても"職業ゲーム屋さん"であるがゆえの狭い視野から抜け出せなくなることがあるので、畑が違う方々とのお付き合いは大事です。
今は自分の会社「125」で、ほかの会社さんのゲーム制作のお手伝いをしたり、ゲームに関するなんでも屋のような仕事をしています。もちろん自社のゲームも作っています。
例えば、iPhoneとAndroidで出させていただいている『シンゾウアプリ』というゲームがあります。それまで長いことプレイステーション用のゲームを作ってきたので、スマホゲームの開発は未経験でした。
未知の世界で初めてのことをやりたい、といろいろ考えて作ったこの『シンゾウアプリ』は、キャラクターのグラフィックが一切なく、声だけでストーリーが展開されるゲームです。呪いをかけられて、どこかのイケメンの心臓がスマホに乗り移っているという設定で、ゲームを始めるといろいろ話しかけてきます。
 株式会社125が2019年にリリースしたスマホ向けノベルゲームアプリ『シンゾウアプリ 6人の彼』。呪いをかけられた男の心臓がアプリに乗り移ったとの設定で、ゲーム中の選択肢によってシナリオが分岐していく。©2019 125 Inc.
株式会社125が2019年にリリースしたスマホ向けノベルゲームアプリ『シンゾウアプリ 6人の彼』。呪いをかけられた男の心臓がアプリに乗り移ったとの設定で、ゲーム中の選択肢によってシナリオが分岐していく。©2019 125 Inc.
落合 今、さっそくダウンロードしてプレイし始めているんですが、心電図表示に合わせてスマホが「ドクン」って震えるのが絶妙に気持ち悪くて最高ですね。
鈴木 それはホメ言葉ですね(笑)。人の心臓のリアルな大きさは握りこぶしくらいなので、スマホはサイズ感としてもちょうどいいんです。
これは美麗なグラフィックで攻める従来の恋愛シミュレーション系ゲームに対するアンチテーゼをやりたかったのと、私の小さな会社ではグラフィックにあまり予算がかけられないという現実問題から落とし込んでいった上でのゲームデザインです。
多くのゲームではグラフィックにかなりの予算を割いているわけですが、いっそそれを思いっきりカットしよう、その分声優さんを豪華にしよう、と。おかげさまでご好評いただいております。

落合 逆転の発想ですね。ハプティクス(触覚フィードバック)とシンプルなグラフィックのタイミングがいいし、メディアアートっぽさを感じます。
鈴木 僕は家庭用ゲーム機出身の人間なので、「振動できるなら震わせるのが当たり前でしょ」というアプローチで考えるんですね。ハードの持つ機能を活用してやりたい、と言いますか。僕らがもともとやってきたゲーム作りの知恵が、また別のハードと絡むと常識を変えられるのかな、とひとつ手応えを感じました。
エンタメの中でもゲームというジャンルの特殊なところは、「自分で触ってグッときたい」という欲求を刺激する点です。人を受け身にさせない。だからこそ、人間社会のさまざまな場面でこれからも求められ続けていくでしょう。
落合 ありがとうございました! 僕はメディアアーティストなんですが、どちらかというと"空間性"の人間で、彫刻とか映画とか、決めきったもののほうが得意なんです。ゲームはその真逆で、おっしゃったように実際にプレイしたくなる、インタラクション性の高いジャンルですよね。
それでお訊きしたいのですが、操作性とか触った感じの心地よさとか、ゲームを作る人はどのような基準で追究されているのでしょうか? 自分はインタラクション研究者なので、「気持ちのいいインタラクション」についてよく考えてみたりするのですが、ゲームのインタラクションを習うような教科ってありませんよね。
鈴木 "文法"はあります。自分で老兵だ、おっさんだ、と言ってきましたが、もっと上の世代、それこそ任天堂の『スーパーマリオブラザーズ』などを作られたレジェンド級の方々がいらっしゃって、すでに心地よいインタラクションの基礎の文法をその世代の方々が見いだされているわけです。
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、スーパーマリオはキャラクターが奈落に落ちかけていてもジャンプできるんですよ。"コヨーテ・タイム"と呼ばれていますが、「足場から外れて落ちていても少しならジャンプを受け付ける」という時間の幅が設けられているんですね。
これはほんの一例で、業界の古参の方々なら「必ず採用する」という文法がいくつもあります。それらを守るだけでも、グッと手触りがよくなります。明文化されていないし、一子相伝の技みたいな感じですが。
落合 そのゲーム文法を体系的にまとめている人はいないんですか? 映画やアニメーションだとちゃんと技術としてまとまっていますよね。
鈴木 それこそ任天堂さんが公開してくださらないかしら、と思っています。任天堂さんは近年、「CEDEC(セデック)」というゲーム開発者会議で講演されるようになったので、そのうち秘伝の文法ももっと公開されないかなと期待しています。
◆後編⇒落合陽一×鈴木達也(ゲームプロデューサー、株式会社125代表)「Zoomに足りない機能はミニゲームだった!?」
■「コンテンツ応用論2020」とは?
本連載は2020年秋に開講された筑波大学の1・2年生向け超人気講義、「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします(今年度はリモート開催)。落合陽一准教授がコンテンツ産業に携わる多様なクリエイターをゲストに招き、白熱トークを展開します
●落合陽一(おちあい・よういち)
1987年生まれ。筑波大学准教授。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。人間とコンピュータが自然に共存する未来観を提示し、筑波大学内に「デジタルネイチャー推進戦略研究基盤」を設立。近著に、2016年の著作『これからの世界をつくる仲間たちへ』をアップデートした新書版『働き方5.0』(小学館新書)
●鈴木達也(すずき・たつや)
1973年生まれ、静岡県出身。株式会社元気、富士通などを経て、ソニーインタラクティブエンタテインメント(SIE)でゲームプロデューサーとして『無限回廊』シリーズ(PSP、PS3)、『I.Q Mania』(PSP)など多くの作品に携わった後、独立し株式会社125を設立。独立後の作品に『シンゾウアプリ 6人の彼』(iOS、Android)、『ステオス 雇われ砲撃手の哀愁歌』(Steam/Switch)など