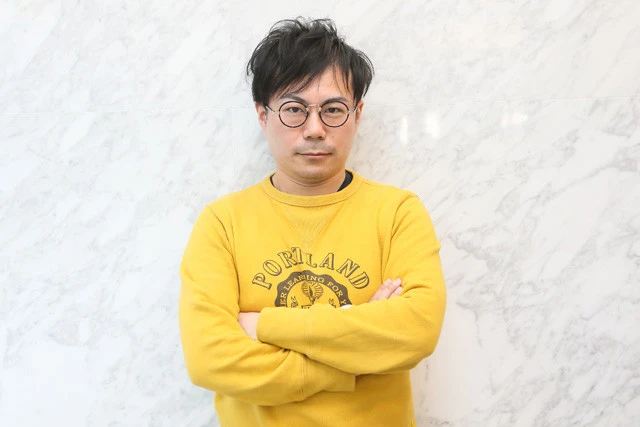 「『受け取っていたことに気づく』のも大事ですが、他者と向き合う際には『自分も今まで気づいてなかった』という視点があると、寛容になれるでしょう」と語る近内悠太氏
「『受け取っていたことに気づく』のも大事ですが、他者と向き合う際には『自分も今まで気づいてなかった』という視点があると、寛容になれるでしょう」と語る近内悠太氏
モノを手に入れたり、サービスを受けたりするためにはお金を払わなければならない。お金を得るためには働かなければならない。資本主義社会ではそれが当然とされているが、実は見返りを求めない"贈与"こそが大事なのでは?
そのように贈与を中心に据えて倫理を説いた『世界は贈与でできている――資本主義の「すきま」を埋める倫理学』が静かに人気を集めている。昨年3月に刊行された本書は、半年以上かけてベストセラーに。コロナ下に悩む人々の希望を受け止めるかのように、読者を増やし続けているのだ。
贈与から読み解くことで明らかになる人間の姿とは? 著者の近内悠太氏に聞いた。
* * *
――この本は近内さんの初めての著書とのことですが、どのようなきっかけで書き始めたのでしょうか。
近内 今は人と人がつながるのが難しくなっている時代だと思います。例えば恋愛でも親子関係でも、「こういうつながり方をすればいいんだよ」というデフォルトが賞味期限切れになっていて、「ひとりひとりが責任を持って考えなければいけない」とする傾向が強まっているのではないかと。その結果、人間関係の悩みが増える。
じゃあ人間関係の根底にあるものは何か、人と人とがちゃんとつながり直すには何が必要かと考えると、おそらく贈与という観点になるだろう。そう思ったのがひとつのきっかけです。
――交換が合理的であるのに対し、贈与は不合理的なものと書かれていますね。
近内 はい。本書では人類が進化の結果として、極めて無力な乳幼児期を長く過ごさざるをえなくなったことを出発点に考察を進めています。未熟な赤ん坊が生き残れるのは、保護者をはじめとする他者に守られてこそ。
赤ん坊を守るという行為は決して打算に突き動かされて取るものではなく、ある種不合理な贈与です。人類はそもそもこうして生き延びてきたのだし、個々の人生の始まりには贈与があるのです。私とあなた、というミクロなつながりの総体が社会である以上、やっぱりこの点を考えないわけにはいきません。
大人になるにつれて、合理的な等価交換という手段で他者とつながる比重が増えますが、それでも社会の根っこにはまったく不合理な贈与という行為が潜んでいる。人間関係で悩む人がそれに気づき、少しでも救われたらいいなと思います。
――贈与が原因となる人間関係の悩みにはどのようなケースがあるのでしょうか。
近内 本書でも例に出しましたが、親子関係の悩みがそうです。親に愛情を感じないのに「育ててもらったんだから感謝しなきゃだめだ、恨んじゃだめだ」と思い込もうとすると、人間はどんどん精神的にがんじがらめになってしまいます。そこで贈与の構造を知っていれば、「あっちが一方的に育てたんだから、こっちに責任はない」とふっきることもできるかもしれません。
――ちょうどコロナ下で交換を前提とする市場原理が部分的に機能不全を来す時代状況で、贈与を論じたこの本が支持されるのは興味深いところです。読者の反応はいかがでしょう?
近内 感想をくださる方のなかには「そうか、あのときのあれは贈与だったんだ!」と、ご自身の経験を過去形で語られる方が多いです。つまり、贈与という現象自体は決して未知のものではなかった、ただ言語化できてなかっただけなんです。
誰しも生きてゆくなかで、「なんであのとき幸せな気持ちになれたんだろう」とか、逆に「(贈与を)もらったのにどうしていやな気持ちになったんだろう」と思う経験をしているでしょう。それをまずは言語化し、贈与の構造の中で理解できるようになれば、と考えて書いた本なので、「読んで気づいた」と言っていただけるとうれしいです。
――狙いどおりにメッセージが届いたということですね。
近内 だけど贈与って語るのが難しいんです。一歩間違うと、「しなければならない」と束縛するようなメッセージと受け取られかねないから。そのとおり書いてなくとも、です。
語ることで、(贈与によるつながりから)排除される人々が出てしまう危険もあります。例えばこの本は前半だけ読むと実はかなり暴力的な本なんです。「親の愛を受け取ってきた者だけが贈与に気づき、他者にパスを出せる」と言っているようなもので、「じゃあそれ以外の人たちは?」と疑問が生じますよね。
「自分が受け取っていたことに気づく」のも大事ですが、他者と向き合う際には、むしろ「自分も今まで気づいてなかったんだから」という視点があると、寛容になれるでしょう。
受けた贈与を見落としていても構わない。だけどいつか気づけたらいいよね、気づくとしたらどういうプロセスがありうるのか、といったことを議論してるのが後半部分で、全体としては優しい目線で贈与を語ることができたのかなと思います。
――贈与は受け取ってから気づくまでに時間がかかるようです。"遅さ"を伴う贈与の論理は、逆にせっかちな世の中で生きる知恵になるのでは?
近内 はい。料金を払うと瞬時に意味が発生する等価交換に対して、贈与の場合は行為と気づきの間に時差が生じます。その性質を受け入れることは、性急に答えを求めようとしない、宙ぶらりんの状態に耐える"ネガティブケイパビリティ"に通じるでしょう。
――与える側の心がけも気になるところです。相手に負担を与えないでプレゼントを渡すコツがあればお聞かせください。
近内 僕は「かわいげ、ユーモア、爽やかさ」が条件だと考えています。例えば、「別にあなたのために買ったわけじゃないけど」みたいなツンデレには、かわいげがありますよね。逆に贈り物をする際にマジメにやりすぎちゃうと重く受け取られてしまうので注意が必要です。
――贈る側にも受け取る側にも単純なものではないのに、それでも贈与をしてしまうのが人間のさがなのでしょうか。
近内 そうですね。贈与を軸に人間を考察していて、「いじらしい」という表現が一番しっくりきました。人間は立派なものでも、強いものでもない。いじらしく、弱々しさを持った存在です。なのに大したものであろうとするから、現実との乖離(かいり)が生じ、苦しむわけです。
「そうじゃない、弱くていい、あなたは間違っていないんだ」というのがこの本のメッセージです。贈与とは要するに、人間の正しいあがき方なんです。
●近内悠太(ちかうち・ゆうた)
1985年生まれ、神奈川県出身。教育者。哲学研究者。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践。本書がデビュー著作となる
■『世界は贈与でできている――資本主義の「すきま」を埋める倫理学』
(NewsPicksパブリッシング 1800円+税)
現代社会を生きる多くの日本人が仕事のやりがい、生きる意味、大切な人とのつながりを狂おしいほどに追い求めてしまうのはなぜか――。見通しが立たないコロナ下の社会を生き抜くための愛と知的興奮に満ちた、新しい哲学書。糸井重里氏、茂木健一郎氏、山口周氏らが絶賛する本書は第29回山本七平賞奨励賞を受賞。また、「紀伊國屋じんぶん大賞2021――読者と選ぶ人文書ベスト30」で第5位入賞

