 歴史を学ぶというと一見、おカタい作業に感じるが、桜井氏の著書は多くの人物が生き生きと書かれており、ハードルの高さを感じない
歴史を学ぶというと一見、おカタい作業に感じるが、桜井氏の著書は多くの人物が生き生きと書かれており、ハードルの高さを感じない
イギリスは1066年にフランス人によって創立された‐‐。
現代のイギリス人でも、知らない人が多くいるという歴史の事実。世界史を勉強した人であれば、1066年の「ノルマンの征服」もしくは「ノルマンコンクエスト」という単語を丸暗記した覚えのある人がいるかもしれない。
ここで言うノルマンとは、イギリスからドーバー海峡を隔てた対岸にあるノルマンディ公国(現在のフランスの一部)のことであり、そこに住むノルマン人とはすなわちフランス人のことである。
それ以前のイギリスには、924年から1066年(日本でいえば平安時代後期)のわずか142年で歴史に幕を降ろすことになったイングランド王国(オールド・イングランド王国)があった。
王国の歴史としては短いが、アングロサクソン人が国を治めたその時代のことは『アングロサクソン年代記』という有名な史料に記されており、そこには勇敢な王と王に絶対の忠誠を誓い戦った命知らずの戦士など数多くの英雄が登場する。その英雄譚(たん)は、今なおイギリス人の憧憬(どうけい)の的であり続けているという。
このアングロサクソン人の王国の歴史を紐(ひも)解いたのが、『消えたイングランド王国』(集英社新書)である。著者の桜井俊彰氏に歴史の狭間(はざま)で一瞬の煌(きら)めきを見せたこの王国の魅力について聞いた。
‐桜井さんがイギリスの中世史に興味を持たれたのは、どういったキッカケがあったのでしょうか。
桜井 40歳を過ぎてイギリスのロンドン大学(UCL)に留学したのですが、その時、勉強するならイギリスの中世史だろうと。近代史や現代史は研究され尽くされていて、大家と呼ばれる人もたくさんいます。今さらそんなところをやってもしょうがないですから(笑)。
その点、中世史はラテン語もオールドイングリッシュという今の英語とは全く違う古い英語も読めなければいけない。そういう大変さがあるので、イギリス人でも中世史を勉強しようという人は少ないんですよ。
‐自ら“イバラの道”を歩もうとしたわけですね。
桜井 もちろん、中世史には興味がありました。ノルマンコンクエストでイングランドを征服し、国王も貴族もフランス人となり、イングランドの公用語もフランス語にした征服者のフランス人が、その後、どのようにして自らを被征服者の“イングランド人”と認識し、英語を喋るようになったのか知りたいと思い勉強しました。
歴史って知れば知るほど、その前後の時代へと興味がつながる楽しさがあります。ちょうど大学でもノルマン征服前の時代の言語であるオールドイングリッシュの講義があり、担当の先生がある詩を読んでくれて、それその響きがうっとりするほどいいんですよ。それですっかりハマってしまって、オールドイングランドの時代について勉強してみようと思ったわけです。
王が倒されても戦士たちは戦い続ける

‐本書の中には、自ら家臣を率いて侵略者ヴァイキングと戦う王様の姿が描かれています。
桜井 普通、王は国の一番大事なシンボルであり、自ら戦う存在ではないイメージがあると思います。でも、この時代はそうではありません。自ら剣を取り、王がヒーローになるから臣下がついてくるのです。王という言葉の語源をたどると面白いのですよ。
英語でkingと書きますが、これは古英語のcyningから来ていて、cyn (kin、一族)とingより成っています。つまり、一族をずっと維持していく、率いていくのが王なのです。だから、王は先頭に立たないといけない。そういう王様だからこそ、王が倒されても戦士たちは戦い続けるんです。
また、その戦士たちがかっこいいんですよ。イングランドに侵略してきたデーン人(ヴァイキング)との戦いを記した散文詩「モルドンの戦い」では、自らの主がデーン人に倒された後に残った戦士たちが、次々に名乗りを上げて戦います。その苦しい戦いの最中、ある老兵が楯(たて)を高く掲げて言うんです。
「わが軍の力衰えれば衰えるほどに勇気はいよいよ熱くあれ 意志はさらに堅固たれ 心はますます剛毅(ごうき)たれ (中略)われは齢(よわい)を重ねし者 もはやここからは帰らず わが慕いし主の傍らにいまは横たわらん」(桜井俊彰・訳、ルビカッコは編集部)
これを訳していて思ったのは、彼らは自らに酔っているところもあっただろうなと。彼らには詩人的なところがあって、あの当時は詩を詠(うた)いながら戦いに突っ込んでいく。
これは僕の推測なんですが、詩人がいるということはそれを聞く文化もある。戦士が名乗りを上げている時には、敵も味方も手を止めて聞いているんだと思うんですね。日本でもかつて、「我こそは!」と名乗りを上げて戦っていた時代があった。日本の歴史好きで、正々堂々とした戦いが好きな人には、この時代のイングランド戦士の戦いはウケると思います。
‐それでも142年でイングランド王国はその幕を降ろします。本書を読んで思うのは、現在のイギリス、もしくは大英帝国時代から比べると、当時のイングランド王国が弱いということです。
桜井 そう、弱いんですよ。その理由について考えていて、「そうか!」と思うことがあったんですが、弱い理由のひとつにキリスト教が関係しているのではないかと。キリスト教は汝(なんじ)の敵を愛せよという教えですからね。相手に対して、“情”のようなものが湧(わ)くのだと思います。一方、デーン人はまだ多くはキリスト教に改宗していませんから、「蛮族」で戦う気満々(笑)。
それからもうひとつ、なぜ当時のイギリスがデーン人に弱かったかというと、これは機動力の差ですね。彼らはヴァイキングだから船でいきなりわっと攻めてくる。海岸沿いはもちろん、内陸でも船で川を遡(さかのぼ)って不意を突いてくる。突然侵攻されても地元の部隊は体制を整える間もなく、やられてしまう。今のように連絡網もないですしね。これではいいようにやられますよ。
歴史と文学の境界が曖昧な時代が一番面白い
‐イングランド王国最後の戦いとなったヘイスティングズの戦いでも、ノルマンディ公ウイリアム1世に負けてしまいました。
桜井 当時はイングランド王国といっても、地方のボスがたくさんいた。国としてのイングランドはあっても、国防だとか全イングランドを挙げて戦うという意識、つまり国家という概念まであったかどうかは疑問です。
だからこそ、ウィリアム1世が来ても、当時のイングランド王ハロルドに変わる新たな勢力が来ただけであって、国家的な危機という認識がなかったのではないかと。
それにイングランドは大陸に比べて戦術も兵器も一時代遅れていたんですね。城といっても、柵(さく)をめぐらすような山城のようなものでしたからね。他方、ノルマンディー公国軍は、イングランド軍にはない騎兵戦術を駆使し、フランス国王軍を始め、大陸各地で様々な相手と戦ってきた豊富な軍事経験をもっているわけですからね。
‐それにしても本書では、1千年前のことが生き生きとした描写で描かれていて、歴史の物語の中にすっと入り込んでしまいます。
桜井 僕自身、大学の先生のようないわゆる“プロの歴史学者”ではなく、エッセイや文学もやっていますから、読者を意識して絶対に面白いものを書いてやろうという気が強いですからね。言葉ひとつ選ぶにもじっくり考えながら書いています。
それに歴史的な厳密性を担保するとなると、この時代をこんなにたくさん書けません。残っている資料が少なすぎてね。だから文学的なイメージでもアプローチをしたワケです。歴史と文学の境界が曖昧(あいまい)な時代というのは一番面白いし、多くの人に読んでもらえる。そもそも歴史と文学なんて切っても切れない関係でしょう。
高校生の頃に勉強する世界史は、受験勉強ですから暗記でもしょうがない。でも、覚えた年号と年号の間には結構な時間が流れているわけです。歴史というのは、早い話が昔の人の人生ですから、つまらないはずはありません。歴史に興味を持つキッカケは教科書でいいですから、その歴史にはどんなことがあったんだろうと調べて入ってもらいたいと思います。
僕自身、教科書に出てきた出来事をひとつひとつ繋(つな)いでいこうという気持ちで、教科書に書かれていない部分、こんな熱い人間ドラマがあったということを書きました。歴史文学を書いている人間にとってはそれを書くのが使命じゃないかと思っていますからね。
* * *
歴史学的にこの時代を考証した本は珍しい。文学的にも優れており、スラスラと読めてしまう本書。極上の世界史の授業として堪能してみては!?
(取材・文/頓所直人 撮影/関純一)
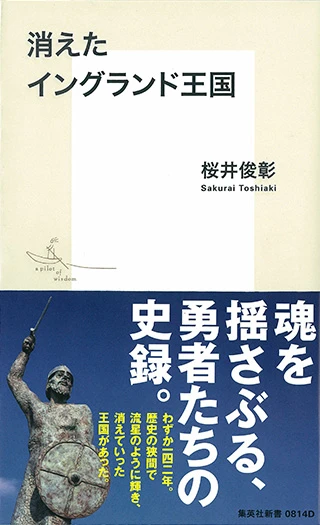 『消えたイングランド王国』(集英社新書・760円+税)
『消えたイングランド王国』(集英社新書・760円+税)
●桜井俊彰(さくらい としあき) 1952年生まれ、東京都出身。エッセイスト、歴史家。1975年、國學院大學文学部史学科卒業。1997年、ロンドン大学ユニバシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)史学科大学院中世学専攻修士課程(M.A. in Medieval Studies)修了。主な著書に『僕のロンドン』『英国中世ブンガク入門』『英語は40歳を過ぎてから』『イングランド王国前史』『イングランド王国と闘った男』など。写真は、モルドンの戦い跡地に立つ、英雄ビュルフトノース像のポーズをまねる桜井氏