 「製作本数が減っている中で、ストライキで現場も止まる。この影響が出る数年後、公開作品がなくて困っているアメリカの映画館を救うのは日本のアニメ映画かもしれない」と語る宇野維正氏
「製作本数が減っている中で、ストライキで現場も止まる。この影響が出る数年後、公開作品がなくて困っているアメリカの映画館を救うのは日本のアニメ映画かもしれない」と語る宇野維正氏
約100年にわたってアメリカ産業の大きな柱のひとつであり続けたハリウッド映画は、終焉へと向かいつつあるという。
世界的なパンデミックや配信プラットフォームの普及も手伝って、製作本数や観客動員数は減少。そんな窮状を、2020年以降に公開された16本の映画を通してつまびらかにしたのが宇野維正氏の新刊『ハリウッド映画の終焉』(集英社新書)だ。
大衆の娯楽だったハリウッド映画は今後どうなっていくのか?
* * *
――なぜ「終焉」というタイトルを冠したのでしょうか?
宇野 ここ10年、ハリウッドのメジャースタジオは観客動員の見込める人気シリーズものばかりに依存してきました。スーパーヒーロー映画など、エンターテインメント性に振り切った元ネタのある作品。
一方で、監督の作家性を押し出したオリジナル脚本の作品を手がけられるのは、名前でお金が集められるポール・トーマス・アンダーソンとか、クリストファー・ノーランのようなごく一部のスーパーエリートに限られてきています。
その中間に位置する映画が作られなくなってきている。そして、そうした作品をこの10年間、積極的に作ってきたのは配信プラットフォームなんです。
――ネットフリックスがオリジナル作品を手がけ始めたのがちょうど2013年頃ですね。
宇野 本書でも取り上げた作品のひとつ『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(配給:ネットフリックス)の監督、ジェーン・カンピオンは「ネットフリックスは現代のメディチ家のような存在」だと言っています。
ルネサンスの時代からアートには資金を出すパトロンが必要だったワケですが、ハリウッド映画というのは奇跡的にアートと商業のバランスが取れていた。
パトロンというパトロンがいなくても浮き沈みを繰り返しながら100年近く続いてきたんです。でも、今回ばかりはまた浮かび上がる未来図は想像しにくいですね。
――ここ数年の映画産業を支えたのは、実は配信プラットフォームだったと。
宇野 ただ、そんなパトロン期間も終わりかけています。この10年間、配信プラットフォームはかなりの資金をつぎ込んできましたが、それはいわば投機マネー。配信プラットフォームの中で優位に立つための投資だったんです。
インターネット回線でも電子マネーでもシェア獲得のために、最初の数年は赤字覚悟でキャンペーンをやったりしますよね。それとまったく同じことです。
つまり、投資の季節は終わった。しかもそんなタイミングで今年のストライキが起きているワケです。
――全米脚本家組合(WGA)は今年5月から、またハリウッドの俳優労組「映画俳優組合―アメリカ・テレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG−AFTRA)」は7月からストライキをしており、賃上げと労働環境の改善などを訴えています。
宇野 これは相当悩ましいですよね。そもそも製作されている作品数が減っている中で、ストライキで製作現場も止まる。
ストライキに参加している方々のほとんどは、さっき言ったような中間に位置する映画が成立しないと商売が成り立たない人たちなワケで。
映画会社も配信プラットフォームもクリエーターも、今回のストによってよけいに疲弊していくことになるのは明らかなんです。
――やはり映画を見る人口が減っていることが大きいのでしょうか?
宇野 この間なんて、本来はライバル関係にあるのに、『ミッション:インポッシブル』の新作と、『インディ・ジョーンズ』の新作と、『バービー』と、(クリストファー・)ノーランの新作『オッペンハイマー』を主演のキャストが見て回るみたいな自然発生的なプロモーションまで起こりました。
もう、そうでもしないと見に来てもらえないっていう危機感の表れですよね。
どんな形であれ盛り上げなきゃいけないっていうのが作品のプロデューサーを兼ねているトップスターたちの考えていることで、一方の末端の人たちは「もう金がない」ってストをやっている状況。もう落としどころがないんですよ。
――しかし、そんな状況でもヒット作は生まれています。
宇野 今ではそうした映画が救世主の役割を担っていますよね。2021年でいえば『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』、22年でいえば『トップガン マーヴェリック』と、年に数本のメガヒット作品が映画産業全体を支えている傾向が強まっています。
――今年は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』がその役割を担った印象です。こうした日本のIP(知的財産)が映画産業を救う可能性はあるのでしょうか?
宇野 あると思いますよ。ハリウッド映画の衰退の理由のひとつとして、中国で近年反米感情が強まっていて、人口の多い中国市場でハリウッド映画が当たらなくなってきているのは無視できません。
その一方で、反日感情はほとんどないため日本の映画は見られている。『マリオ』もそうですが、『THE FIRST SLAM DUNK』や『すずめの戸締まり』のヒットも記憶に新しいところです。
そういう意味ではハリウッド映画のほうがよっぽど絶望的なんですよね。しかも今はストライキで製作が止まっている。現場が止まっていないのはインディペンデント系のスタジオか、実写でないアニメくらいですよ。
アメリカでも『THE FIRST SLAM DUNK』が公開中ですし、ジブリの新作『君たちはどう生きるか』も大変なことになるんじゃないですかね。
そうしてヒットが連続する流れが生まれれば、このストの影響が出る数年後、公開する作品がなくて困っているアメリカの映画館を救うのは日本のアニメ映画かもしれません。
――ここまで聞くと、誇張なく「ハリウッド映画の終焉」が近づいているのだと感じます。
宇野 もちろんこれからもハリウッドからヒット作は生まれるでしょうし、新しい価値観をもたらすこともあるでしょうが、歴史的に大きな役割を終えてしまったことは自明で。産業として規模が小さくなっていくのは、切ないですが間違いありません。
ただ、見る側にとっては一度腰を据えて名作と向き合ういいタイミングでもあると思います。これまで作られた素晴らしい作品が山のようにありますから、まずはこの本で紹介している16作品から、ぜひ。
●宇野 維正(うの・これまさ)
1970年生まれ、東京都出身。映画・音楽ジャーナリスト。『キネマ旬報』『装苑』『リアルサウンド』『MOVIE WALKER PRESS』などで連載中。著書に『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書)、『くるりのこと』(くるりとの共著、新潮社)、『小沢健二の帰還』(岩波書店)、『日本代表とMr.Children』(レジーとの共著、ソル・メディア)、『2010s』(田中宗一郎との共著、新潮社)。ゴールデン・グローブ賞インターナショナル・ボーター(国際投票者)
■『ハリウッド映画の終焉』
集英社新書 1056円(税込)
ハリウッド映画が危機にひんしている。配信プラットフォームの普及、新型コロナウイルスの余波、北米文化の世界的な影響力の低下などが重なって、製作本数も観客動員数も減少が止まらない。ハリウッド映画は、このまま歴史的役割を終えることになるのか? 2020年に入ってから公開された16本の作品を通して、今、映画界で何が起こっているかをつまびらかにしていく
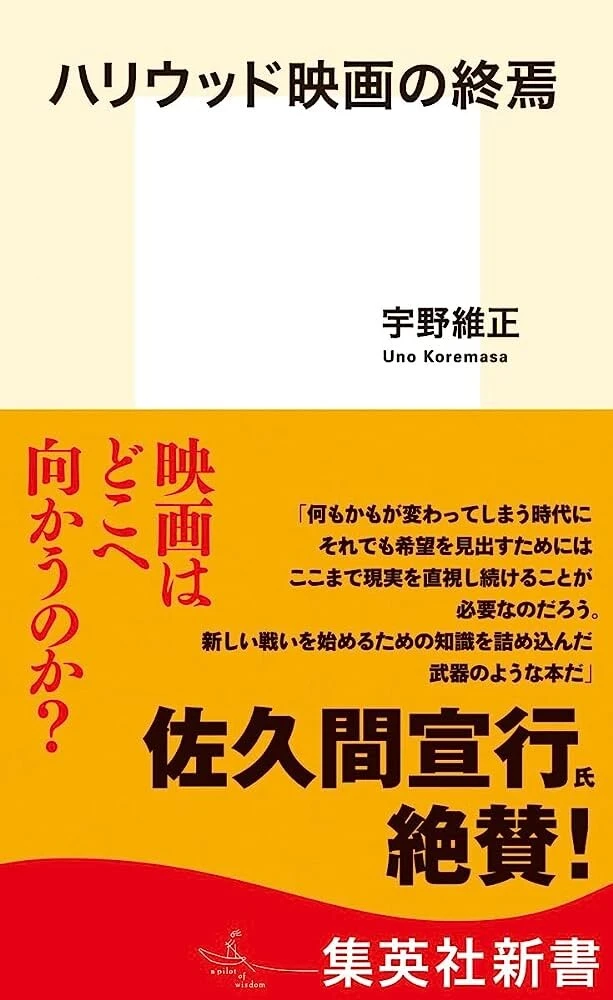 『ハリウッド映画の終焉』(集英社新書)
『ハリウッド映画の終焉』(集英社新書)
