
まぶしい! 痛い! しょぼしょぼする! 目に明らかな不調があるのに、眼科で「異常ナシ」と診断されるケースが少なくない。
そんな事例を示しながら、日本の眼科の問題点を指摘したのが、若倉雅登(わかくら・まさと)氏の著書『心療眼科医が教える その目の不調は脳が原因』(集英社新書)である。
神経眼科・心療眼科の第一人者として、街の眼科で診断不可とされた症状を数多く診てきた若倉氏に、脳を原因とする目の病とその向き合い方について話を聞いた。
* * *
――目に痛みや不調を感じた人は決まって街の眼科に行きますが、若倉先生の著書を読んで感じたのは、様々な目の不調に対し、町の眼科医は万能ではないという点でした。
若倉 街の眼科とはいわゆる一般眼科のことですが、そこでは視力という数値を重視しながら、角膜や水晶体に異常はないか、緑内障や白内障はないかと、眼球中心の診察がなされます。言ってしまえば、一般眼科とは"眼球科"なんです。ちなみに、日本に眼科医は約1万4000人いますが、そのうち9割方が一般眼科医に当たります。
ただ、一般眼科では目に不調を感じているのに「異常なし」と診断されたり、治療したのに自覚症状が軽減されない、といったことが起こりえます。それは、眼球だけを診る診療では気づけない不調の原因があるからです。
眼球はモノを見るための入口であって、それだけでは見る、という作業は完結できません。見るという作業には、脳の働きが大きく関与しています。そこに不具合があって、視覚に何らかの症状が出ているのだとしたら、"眼球医"では診断や治療が難しくなります。
――ヒトは脳でモノを見ている、ということですか?
若倉 そうともいえます。詳しく説明すると、見るというのは「そこに意識が働き、意味のあるものとして認識する」ことです。そして、ヒトは何か注目したいと感じる関心の対象があると、脳がそれを見るための準備を即座にはじめます。
たとえば近い対象物を見るときには、眼球の外側にある外直筋(がいちょくきん)の働きを抑え、内側にある内直筋(ないちょくきん)を作動させることで、両眼を寄せる輻湊(ふくそう)という動作を行います。これが視線を合わせるということで、それぞれの筋肉を動かすための適切な分量を、脳が厳密に計算しているんですね。
対象物に視線を合わせたあとは、内眼筋を動かし、水晶体の厚みを変えることで、ピントを合わせます。近くの物体を見るときには水晶体は膨らみ、凸レンズの度が増します。その際に働かせる筋肉の収縮量もまた、脳が精密に計算しているんです。
実際には、対象物を見る作業は現実には自分も動くし、対象物も動くし、背景もめまぐるしく変化するという複雑な空間の中で繰り広げられます。脳はそうした変数が多くあるなか、緻密な計算を瞬時に行い、対象物を明視させてくれるのです。
――では、その脳を原因とする眼の不調や疾患にはどんなものがあるのでしょう?
若倉 一例をあげると、私が以前に診た患者で、視力は正常、瞼の筋力も落ちてないのに、両眼ともほとんど上に向かない「上方注視麻痺」という症状を持つ女性(30代)がいました。この方は動くものを見ていると激しい頭痛を感じ、子供を保育園に車で送迎する際には上方にある信号や標識が見づらく、車間距離もつかみにくいために、スピードをかなり落として運転しなければならないという悩みを抱えていました。
こうした症状は4年前に見つかった脳の「松果体嚢胞(しょうかたいのうほう)」が原因で、良性腫瘍ではありましたが、これが中脳を圧迫し、上方注視麻痺を起こしていたのです。
このケースを含め、眼球は健常なのにその機能をうまく利用できない症状を総称して、私は「眼球使用困難症候群」と呼んでいますが、その原因の多くは脳にあります。
「小雪症候群」もその一種。私が最初に診たのは中学生の女子で、彼女は視野全体にいつも小雪が降っているように見えて邪魔だと訴えました。この現象は眼球の中で起こっているわけではありません。視覚に関係する脳のどこかに発生している過敏状態、あるいはノイズであろうと推定されます。
視野の中に存在するはずのない模様や生物がしつこく現れる「シャルル・ボネ症候群」は、網膜などの病気によって、脳に到達する視覚信号の量が減少した際に出現する症状と言われています。ある60代の女性は、診察室にはその方と私しかいないのに、「この邪魔者を何とか消してほしい!」と外来を受診されました。

――脳に"誤作動"が起きると、ほかにはどんな症状が?
若倉 数として多いのは、眼瞼(がんけん)けいれんです。
これは自分の意志とは関係なく、瞼(まぶた)がピクピクと不随意にけいれんして、眼を開け続けることが難しくなる病気。まぶしさで目を開けていられなくなる「光過敏」や「羞明(しゅうめい)」も、この病気の中核をなす症状として挙げられます。
厚労省の調査によれば、眼瞼けいれん患者は年2000人~1万2000人とばらついた数字が報告されていますが、私の神経・心療眼科外来の約40%が眼瞼けいれんの患者で、99年からこれまで、のべ1万2000人以上が受診している。一施設でこの数字ですから、実際には全国に数十万~100万人ほどが潜在しているんじゃないかと私は見ています。その発症の頻度から見ても眼瞼けいれんは誰にでも起こりうる、身近な病気です。
しかし、眼瞼けいれんも大脳の神経回路の不調=脳の誤作動によって引き起こされる病気。視力検査では正常な数値が出るケースも多く、一般眼科では見過ごされてしまいがちです。
――「原因不明」もしくは「異常なし」と診断されてしまう?
若倉 眼瞼けいれんの場合は、似たような症状を持つ「ドライアイ」や「加齢性眼瞼下垂(がんけんかすい)」、「原因不明の眼精疲労」などと診断されるケースが多いですね。
実際、私たちの調査では、眼瞼けいれん患者の3分の2で「ドライアイ」と診断され治療を受けたことがありました。自覚症状が似ているからですが、ドライアイではありえないほどの頑固さ、治りにくさがあります。さらに、私どもの施設で初診を受けた1116名の眼瞼けいれん患者を観察した結果によると、約77%は診断にたどりつくまでに「1年以上」かかり、「5年以上」という人も3分の1以上に及びました。
眼瞼けいれんを発症すると、「目を開けているのがつらい」状態に襲われるわけですから、患者のなかには日常生活が快適に送れず、仕事に支障が出ている人も少なくありません。しかし、一般眼科では納得のいく診断が得られず、治療を受けても症状が改善しない。こうして眼科を転々とすることになってしまうのです。
そのため、眼瞼けいれんの患者の中には不眠や抑うつ、不安、焦燥といった精神症状を併発し、自宅にひきこもらざるをえなくなる人もいます。
――やはり、眼科は万能じゃないということでしょうか?
若倉 日本の眼科学は外科医の一部として発展してきた歴史的背景があります。外科医は端的にメスで切って治す専門職。ですから、切って治らなければそれでおしまいといった、よく言えば割り切りが良く、悪く言えば冷淡な性質を持つ人が少なくなく、患者の心に寄り添って相談に乗る姿勢になかなかならない事例が診られます。
――では、眼科に行って「異常ナシ」と診断されたり、治療を受けても症状が改善しない場合にはどうすればいいのでしょうか?
若倉 眼科のなかには眼球と脳を一緒に考える科があります。神経眼科ですね。まずはそこに掛かることが選択肢の一つとなります。ただ、眼科医全体のなかで一般眼科医が9割を占めるのに対し、神経眼科医は1割もいません。
日本の眼科は、領域が偏りすぎている点に問題があります。大半を占める一般眼科医も"眼球屋"にとどまっているんじゃなくて、脳の問題が視覚異常の原因になることや、眼の様々な疾患が心の問題につながることがあるという点にもっと目を向け、患者に寄り添う姿勢を持たなければいけません。
とはいえ、一般眼科のなかにもそうしたマインドを持った医師は少なからずいるものです。しかし医師側も多忙な中では、問診に「はい」や「いいえ」で回答するだけだったり、何かを訴えたりしない患者に対しては、なかなか積極的な姿勢になれないものです。医師は患者が頼みもしないことには手出ししないのです。積極的な治療には何らかの副作用(リスク)が起こりうるし、治療効果にもばらつきが予想されるためですね。
イチ眼科医の立場から、「この患者さんなら積極的な治療を提案できる」と思うのは、"見えない"ことへの不満や生活上の悩みを要領よく伝えてくれる人。また、自分の受ける治療に対して積極的に理解しようとする姿勢を見せてくる人でしょうか。医師を本気にさせるには、自分も治療に参加するのだという自己責任を持った姿勢を見せることが大切です。
不調の原因がよくわからない眼の"不定愁訴"に苦しむ人を減らすためには、眼科医も変わらなければなりませんが、患者自身も賢くならなければいけません。

●若倉雅登(わかくら・まさと)
1949年、東京都生まれ。北里大学医学部を卒業後、土居大学助教授などを経て、2002年より日本で最も歴史ある眼科専門病院「井上眼科病院」院長、12年より名誉院長。日本神経眼科学会理事長などを歴任し、現在は目と脳の関係異常による病気を扱う「神経眼科」「心療眼科」の第一人者として活躍。著書多数。
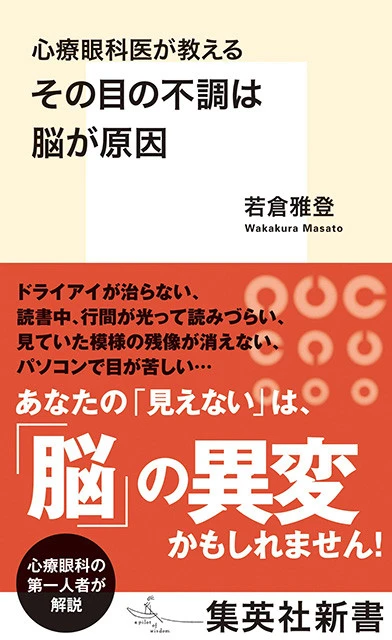 『心療眼科医が教える その目の不調は脳が原因』(集英社新書 860円+税)
『心療眼科医が教える その目の不調は脳が原因』(集英社新書 860円+税)