 作家デビュー20周年を迎えた堂場瞬一氏
作家デビュー20周年を迎えた堂場瞬一氏
作家デビュー20周年を迎え、なんとすでに150冊超!の著作を誇る堂場瞬一氏の新作『幻の旗の下に』(集英社)が10月26日(火)に刊行。人気、実力ともに脂の乗り切った手練れが今回、題材としたのは1940年、"幻のオリンピック"となった初の東京大会の代替で開催された「東亜競技大会」――この夏、コロナ禍で強行された五輪を経験した今こそ、知られざる歴史が問いかけるスポーツの在り様とは?
――今回の2020東京オリンピック・パラリンピックの延期が決まった際、即座に1940年の東京大会開催返上を思い出されたとか。そこですぐ直後の「東亜競技大会」というものが行なわれた事実に、何かがあるのでは......と?
堂場 いや、返上したって話は有名だと思うんですけど、その後どうなったかは私も全然知らなくて。調べてみたら、代わりになのか、意外に大きな大会をやっていたと気づいて、これはいけそうだなとピンときましたね。
――日本が主導し、東アジア圏を中心に競技ごと他の国も参加するという中、当時、大隆盛だった学生野球の背景もあって、野球競技にはハワイの日系人チーム「ハワイ朝日」を招聘。その実現に向け、繰り広げられる男たちの物語です。
堂場 資料自体、戦前のものなので非常に少なかった。どんな競技をやって、どの国が参加してみたいな大枠はわかっても、大会の開催までをどう進めていったのかが全くわからない。逆に、そこは自分で作っていい話だなと勝手に判断しまして(笑)。
――主人公の若者ふたり、大日本体育協会の理事長秘書である石崎保と「ハワイ朝日」のマネジャー・澤山隆......懸け橋となり奔走する彼らを通して、舞台裏の想像をドラマチックに巡らせたわけですね。
堂場 そもそも、実は一番わかっていないのが、なんでハワイのチームが参加したのか、誰が呼んだの?という部分です。そこは特に想像の余地が働くところですよね。非常に日米関係が悪化している時期ですから、そこであえて呼ばれて、なおかつ受け入れるというのはすごく大変だったはず。それを大きな山として設定するのは使えるなと。
――警察小説など幅広いジャンルを描かれていますが、スポーツものも特に野球はデビュー作から得意テーマでもあり。ピンポイントで興味をそそられた?
堂場 これはなんとしても小説的に生かしたいという気持ちが先に走りましたし、最初は「ハワイ朝日」側を完全に主役に据えてというのも考えたんですよ。野球を中心にという考えもあったけど、いかんせん大会や試合の細かいところが全くわからない。ここは全体をまとめて取り上げたほうが説得力を持つのかなと、テクニック的な問題もありましたね。
――大東亜戦争に至る不穏な情勢下で、国威発揚という政治的な側面もありつつ、失われたオリンピックに代わる意義を問いながら、実現までの苦難、葛藤が描かれていきます。
堂場 最終報告書みたいなものが少し残っているだけで、予算とか数字の部分は結構リアルなものを使っているんですけど、実際どう交渉していったか、誰を説得してとかはほぼ創作です。大会そのものを描くと、どうしてもリアルなところが必要になってきますから。結局そこに至るまでの道が、今回の本筋になりましたよね。
――まずは日系二世である澤山が日本への留学時、大学野球で交流した石崎との縁で参加を打診されることから話が始まります。ハワイのセミプロたる地域リーグの存在も興味深く描かれますが、"朝日"といえば映画化もされた「バンクーバー朝日」も有名ですよね。
堂場 カリフォルニアにもありましたし、やっぱり日系人にとって野球ってものすごく重要な意味を持っていたんだなと。特に、戦前はアメリカに溶け込むためのツールであり、故郷をつなぐものでもあり......なので今回、ひとつの象徴として使わせてもらいました。以前に日系人の野球の話も書いていましたからね。
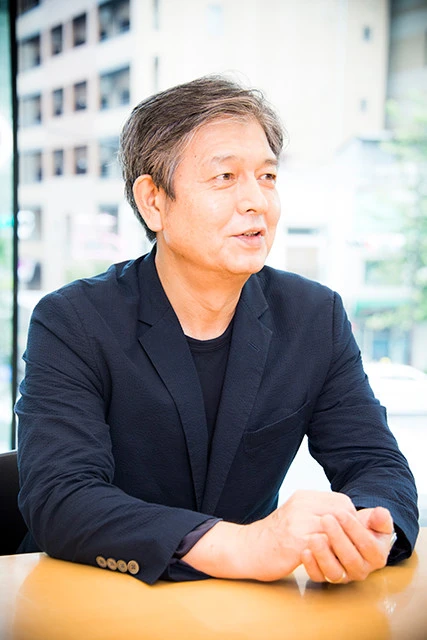
――今までの積み重ねが自分の引き出しにあるからこそ、また反映できたと。では執筆のタイミング的にも、やはり当時のエピソードが描かれたNHK大河ドラマ『いだてん』も想起され、嘉納治五郎や金栗四三ほか、共通する人物の名前も登場しますが、その影響は?
堂場 他人のものは参考にしないんで。そもそも僕自身、金栗を書いていますし(『奔る男 小説金栗四三』)、そこからの流れはありますよね。戦前のスポーツは登場人物、プレーヤーが非常に少ない。スポーツというもの自体、日本に入ってきたのは明治維新後じゃないですか。だから、出てくる人が大体同じになってしまうところはある。
――そこでかぶっちゃったらイヤだなとか、意識せざるをえない部分も......。
堂場 いや、ですから『いだてん』も観てましたよ。金栗さんの連載を新聞でやっていた時、もろにかぶっていたんで。逆に、真似したと言われないように半年早めたとか、裏話では一応ありますけど(笑)。まぁ、オリンピックが決まって開催が近づいてくれば、同じようなことを考える人は絶対何人もいるんでね。
――では、影響という意味では、昨夏の開催延期からこの1年余り、現在進行形で先の読めないオリンピックの動向に左右されたりは?
堂場 今回と1940年の状況は当然、比較するわけですよ。片や返上、片や延期だけど、考えていくと全然違うなというのがわかってくる。1940年は戦争で、これは人間の営みじゃないですか。今回のコロナは人間にはどうしようもない部分があって、一概に並べられないと思うんですけど。
戦争のせいで返上しても、代わりの大会を開いちゃえばなんとかなる、やったもん勝ちだからやっちゃおうぜみたいな。すごい勢いが当時はまだあったみたいで、やれる余裕もあった。今回は1年延期でよかったのか?というのを非常に書きながら疑問に感じていました。
――結局、なし崩しにオリンピック開催を強行、終わった直後のこのタイミングで本作を読むことに、あらためて訴えかけるものが多々あるなと。
堂場 ただ、僕自身がなかなか結論を出せない。今回のオリンピックがどうだったのか総括できないというか......やってよかったというのは特にないし、日本でやったから感動したわけでもない。毎日すごい押しつぶされそうな思いをしながら、ただテレビで観ている感じで、考えるだけわからなくなってくる。
1940年の場合はもっと真っすぐ、正面突破でいっても許されたような。当然、スポーツに対する関心も今と全然違うでしょうし、ほとんど誰も注目していない、観に行こうという人も少なかったはずで、だからこそやっちゃったもん勝ちみたいな。そこが物語のひとつの結論ではあるけど。
――状況は違えど、大会が象徴するスポーツの意義を登場人物たちもそれぞれに悩みながら、開催の大義や本分を問うています。
堂場 ただし、彼らの場合、結論は一個しかない。やっちゃえば勝ちという、非常に空しい価値観で、そこにスポーツマンの意地みたいなところも出ていたとは思うけど。今年の場合はそういうわけではない。準備して一生懸命やっていた選手やスタッフを叩く人もいるし、多くの人が非常にもやもやした感じで終わっちゃったのかなと僕は思っています。

――そのもやもやはコロナ以前、招致が決まった当初から今のこの東京で開催する意味があるのかと、必然性が疑問視されていました。
堂場 そもそも論なわけですよね。それで言うと、1964年だって戦争から日本が立ち直って、歴史的には大きなターニングポイントとされますけど、実際には全然興味がない人も結構いたわけで。日本人はお祭り好きだし、始まっちゃえば盛り上がるだろうみたいな話もあったけど、今回はそういう感じにもならなかったかなと。
――そういった是非含め、登場人物たちに語らせている言葉にも確信がないままに、ご自身の迷いが反映されている感じですか。
堂場 今のオリンピックに対してはっきり言えないことが多いですよね。もうやめちまえなんて言うのもちょっと筋が違うし、万歳する感じでもないし......結局、部外者なので、どうせ何言っても関係ないでしょみたいな。
IOCがやるわけであって、我々にはなんの権限もないわけですから、何も言わずに勝手にやっててくださいという横目で見ているのが正しいのか。今までスポーツに対して持っていた熱量みたいなものが、かなり変わっちゃいましたね、今回をきっかけに。
――そこで、この東亜競技大会の時代と照らし合わせて、また浮き彫りにされるのが政治とスポーツの関係性など、大義名分との間で揺れ動く彼らの苦悩は普遍的テーマなのかと。
堂場 例えば、万博もそうなんですけど、いかに金をかけて派手にできるかみたいなところがポイントになっちゃって。開会式とか閉会式だって、なんであんなに演出しなきゃいけないのみたいな疑問を持っている人は結構いると思うんです。選手だって大変だろうし。
お金をかければすごい派手なことできるけど、それが日本の国力かと言われたら違う感じがするし、国別でメダル数を競うみたいなのも違うだろうって。選手が個人で参加して、国の対抗戦じゃないんだというのもひとつの考え方だろうし。じゃあ、今のオリンピックってなんなの?と考えても、明確に答えられない。
世界最大のイベントと言い切って間違いないけど、あまりにも大きくなり過ぎて、単純に定義できなくなっちゃってる。だから、個別のところを見れば、ここはよかったね、みたいな感動はあるけど、東京オリンピック全体がどうだったのかという気持ちの総括ができないんですよね。
――では、面白い素材になるぞと着手して、執筆の過程では何を伝えるべきかという結論に向け、予想した以上に自らも揺らぎながら?
堂場 書き終わっても、まだ揺らいでいます。1940年の環境からすれば、彼らは一応真っ直ぐにやって、政治に左右されず、やったもん勝ちなんだというのが当時としてはわかる。逆にちょっと羨ましいなという感じすらありますけど、今、そんな単純なことではないので。何かやっぱりわかんねえやって話になっちゃう。
――とはいえ、そこでいちいち刺さる会話や言葉が、今に通じるというか。「政治とスポーツは、何だか相性が悪い気がするけどな」など、伝えたい主張が散りばめられています。
堂場 そこは今の状況を少し代弁してもらったところですよね。昔から政治がスポーツを利用してきたことはあるわけで、今でもそうだろうし、逆にスポーツが政治を利用してきたという側面もある。経済界だって絡んできますしね。
単純に結果が出て、わかりやすい世界のはずなのに、そこに至るまでいろいろ面倒くさいことがあってというのは1940年の時もそうでしょうけど。今はスポンサーとかも絡んで、もっと複雑怪奇なワケのわからない状況ですから。ますます大変だろうなって感じながら、まとめるには困ったな、というところでしたね(苦笑)。
●堂場瞬一(どうばしゅんいち)
1963年、茨城県生まれ。2000年に『8年』で第13回小説すばる新人賞受賞しデビュー。スポーツ青春小説から警察小説まで幅広いジャンルで人気作家に。

■『幻の旗の下に』〈集英社〉
幻に終わった1940年東京オリンピックの代わりに計画された、新たな国際競技大会。その実現と参加に向け、海を越えた友情を信じて奔走するふたりの若者がいた――知られざる歴史を浮かび上がらせる圧巻の交渉小説!