 新作『幻の旗の下に』を刊行した堂場瞬一氏
新作『幻の旗の下に』を刊行した堂場瞬一氏
作家デビュー20周年を迎え、なんとすでに150冊超!の著作を誇る堂場瞬一氏の新作『幻の旗の下に』(集英社)が10月26日(火)に刊行。人気、実力ともに脂の乗り切った手練れが今回、題材としたのは1940年、"幻のオリンピック"となった初の東京大会の代替で開催された「東亜競技大会」――この夏、コロナ禍で強行された五輪を経験した今こそ、知られざる歴史が問いかけるスポーツの在り様とは?
東アジア圏を中心に、競技ごと他の国も参加するという大会の野球競技には、ハワイから日系人チームを招聘。大日本体育協会の石崎と「ハワイ朝日」のマネージャー・澤山がその実現に向け、奔走する舞台裏が描かれる中、現代にも通じる切実なメッセージが......!(前編記事「終わっても結論が出ない東京五輪――単純に"やったもん勝ち"ではない」参照)
――スポーツを題材にした青春小説でありつつ、裏を返すと政治小説風にも読めます。
堂場 実際この作品では、スポーツをあんまりやっていませんもんね、試合とか。ほとんど裏交渉みたいな話ばかりで、自分では"交渉小説"という変な言い方をしています。
――本当にネゴシエーションの連続、その痺れるやりとりを経て、若者が成長していく物語でもあります。
堂場 本来、スポーツの場がそうあるべきじゃないかと思ってますし。今回はそこに至るまでが肝(きも)になるワケで、そういう時におっさんたちが交渉の場にいても、何か嫌らしくなるだけじゃないかと。あの時代に無理して若者が頑張ったというところで、あえて「スポーツってあなたたちのものなんですよ」というメッセージでもある。それが届いているか、自信はないですけど......若い人がおっさんを説得して落とすって、やっぱりそこが醍醐味(だいごみ)だと思いますね。
――戦争と今のコロナの時代というのも、もちろん一緒にはできませんが、あえてスポーツをやる意義や正当性において説得力をどう持たせるのか。陸軍次官・白井との交渉でも「我々は武器を手に命がけで戦っている。呑気に金メダルなどと言っている人の気持ちは理解できない」と突き付けられます。
堂場 そこがやっぱり今回との違いで、僕の中ではうまく今と重ね合わせた形になっていない、最後まで微妙にずれている部分ですね。要するに、当時はお偉いさんがやめろと言ってオリンピックも返上したわけです。今回はお偉いさんがやると言ったわけで、実は状況は似ているようで逆ですよ。
人間が始めて人間が終わらせる戦争と、コロナのような病気は全然違うじゃないですか。戦争のほうがまだコントロールできるというか、コロナは本当にアンコントローラブルなので。そういった環境も全然違いますし、今に生かせることは正直あまりないのかなと。結局、自分でも合点がいかなかった。
――ただ、その言葉に対して、石崎は「スポーツに助けられる人もいるんです」と個人的なエピソードを用いて、ある意味、強引に情動で訴えます。
堂場 個別から一般へという、よくある説得のやり方ですけどね。白井さんもあれくらいで心揺さぶられて落ちちゃいかんよね(笑)。それこそ本当に軍部が戦意高揚のためにやったとか考えられなくもないけど、逆にまた、そこまで政治に翻弄されるのか?と。ますます話が複雑になって着地点を見い出せなくなるので、あくまで今回は若い連中がいかに理想を貫いたかという話にするしかないなと思いました。
――体育協会の理事長である末広に言わせている通り、「自分たちの時代は爺さんたちの圧力が本当に嫌だった。あんな年寄りたちにはならないようにと決めたんだ」と。やはり代弁者として、若者たちに希望を託すという。
堂場 当時っていうより、むしろ今の話ですよね。老害という言葉も言われるし。
――まさに、今回も森喜朗さんなんか批判の矢面となって......。
堂場 いや、名前は出さなくていいけど(苦笑)。そこで若い人が声を上げない。もっとやればいいのになという、今の若い世代に対するメッセージだと思っていただければ。
――自分たちが動かしていかねばという熱情、活力を突きつけられるところです。
堂場 僕もそろそろ老害のほうに入ってきてるんだけど、やっぱり若い力ってすごいなと思います。同じ状態が続いたら、社会は必ず滅びますから、何かを少しずつでも変えていくには若い人の発想とか力がないとできない......って、自分がこんなこと言うようになってるのもショック。ああ、イヤだイヤだ(笑)。
――(笑)そういう若者向けというか、読んでもらって、あの時代にも矛盾を感じながら、軋轢(あつれき)にぶつかりながらも純粋に自らを賭した人生があるんだぞと伝えたいですよね。
堂場 大事なのは、それが特に金にもならんけどねってことなんです。利益のためとかじゃなく、理念とか夢のために動くようなことがあってもいい、あってほしいなと。
――もちろん、その一方で現実はこうだぞと金の工面に走らされたりもしますが。
堂場 そこが甘いこっちゃないっていう感じですよ。理想だけじゃ飯は食えない、金を持ってこいというのが当然の話で、単純に理想を追う小説ではない。
――その金策でパトロン的な役割を果たす大物喜劇役者・井川がまた魅力的です。今の暗い時代こそ喜劇が必要だと、スポーツからも勇気、元気をもらおうやと、気前よく出資してくれる。
堂場 ひとりぐらい豪快な人がいないと、話が暗くなるでしょう。そこで野球がブリッジになっているというのも今回の肝ですかね。だから、若い人はそういうおっさんをうまく捕まえれば、自分の思う通りにできるという。今、そうそういないだろうけど。まぁ、そうあってほしいという願望ですよね。

――そこでもうひとり、往年の名投手である大阪タイガースの若林忠志も重要な役割を果たしますが、実在の人物で「ハワイ朝日」の出身だったという...。
堂場 彼のことは昔から知っているというか、野球好きで歴史好きの人なら、まず七色の変化球の、伝説の大投手と理解しています。非常に劇的な人生を送っていますし、どこかでいつか描けないものかと。今回、ハワイのチームを出したので、ここぞとばかりにハマりましたね。
――まさに、ここまでハマるとはという感じで「スポーツは戦争より、ずっと上の存在だ」と、最高の決め台詞まで言わせてます。
堂場 日系アメリカ人という非常に微妙な立場で、あくまで理想だと思うし、彼の言動は想像で作ったところですけど。重要なポイントでご登場を願ったわけです。ほんと、若林でもう1本書きたいくらいですね。
――澤山ら「ハワイ朝日」の描き方でも、日系人でありながらアメリカで生きている、ただ日本人目線だけではない心理や葛藤がうまく活かされているかと。
堂場 そういう"境界人種"が好きですね。ボーダーライン上にいる人にすごい興味があるんです。同じ社会の同じような立場の人じゃなくて、ちょっとずれたところから入ってくる......そうすると、見えていないものが斜めから少し見えてくるかな。
だから、ほぼ裏方さんオンリーで押し通していくという形も今回初めてなので、微妙に冷静になったりするところとか、逆に書いていて面白かったですけどね。
――その裏方的なサイドストーリーとしては、前畑秀子の後継者とされた女性スイマーに参加要請するエピソードも印象深く。
堂場 あれは前畑にしなくてよかったんだろうな......。いくらなんでもここで出すのはどうかと思って、架空のスイマーを出したんです。実は、女性が全く出ていない大会になったんですね。男子だけというのが謎なんです。
ただ、この時期は前畑ですごい盛り上がって、女性の運動選手の勃興期でした。なかなか社会的に認めてもらえた時代ではないけど、やっぱり女性アスリートの存在はものすごい重要なわけで。無視できなかったし、どうしてもああいうエピソードを作りたかった。
――末弘理事長にも「職業婦人はもっと活躍すべきだし、スポーツの世界でも同じだ」と語らせているほどですし。
堂場 今の時代だとそれが当たり前というか、僕の考え方というより、それがいわゆる常識だと思っていただければ。
――結果、その女性スイマーは出場を断念するわけですが、大会の返上や延期によって、夢が叶わなかった者たちをも掬(すく)い取っている気がしました。
堂場 それはいつの時代のどんな大会でもあるんですけど、特に今回のオリンピックともかぶってはきますよね。1年延期になったことで、もう駄目だと引退した選手もいるわけですから......。スポーツの歴史なんて、真面目に勉強する必要ないという考えもあるでしょうけど、過去にはこんなこともあって、こういう状況だったと知っておく――今と繋がるものを見直すことは大事だなと、常々思ってます。
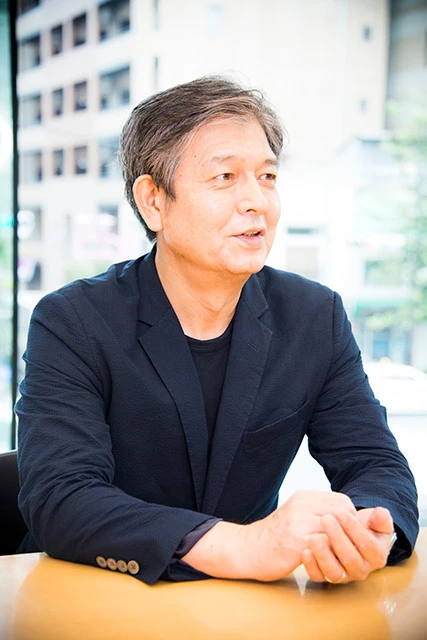
――そして、軍隊から負傷で戻った石崎の盟友・立花も先輩・若林のいる職業野球復帰を期し、野球には夢があると。「俺はまだ諦めなくてもいいんじゃないか」という言葉に、今ならパラリンピックをも想起させます。
堂場 それは、本当に解釈次第でいい。自分の中ではそこまでの意識はないし、少しカッコいいことを言わせたかっただけじゃないかな(笑)。あんまり計算ずくでやっちゃうと途端に嫌らしさが出ちゃうんで、あんまり何も考えずにさらっと書いていますよ。
――では、書き終わった今でも結論は出ずと仰っていましたが。多様な気づきを織り込んだ作品ということで満足感は......。
堂場 いや、満足はしていませんね、やっぱり。オリンピックとはなんぞや?みたいな、迷いが滲(にじ)み出ちゃっているかなという心配がありますし。小説は小説の中でぴたっと完結して、ちゃんと落ちてみたいなのを期待している人が多いと思うんで。
読んでくれた人と一緒に考えたいなという気持ちはあるけど、別に誰もそんなの求めていないじゃないですか。だから、僕のもやもやした気持ちをぶん投げちゃった感じがあって、そこは申し訳ないなと。まぁ僕自身、そういう作者に挑戦されるような小説は結構好きなので、今回はみんなで考えましょうということですかね。
――リアルな問題は尽きないですし、賛否含めてこの先も結論はなかなか出ないのかと。「スポーツで心がひとつになった。やってみれば悪いことは絶対ない」が理想ですけど。
堂場 この夏のオリンピックは、やってみればよかったとはなっていないんでね。なんとも言えないなとしか......だから、一緒に考えていきましょうと。
――最後に、石崎と同じく「オリンピックは政治に影響を受けすぎます。そういうところから離れて、本当に選手のための大会を開けないでしょうか」と問い続けるしかない?
堂場 それも理想的過ぎますけどね。ただ、今みたいなオリンピックが政治と経済を抜きに実現できるわけがない。常にスポンサーを見つけ続けて、さらに拡大するのか、あるいはコンパクトな形にして全く別の大会を作るのか。じゃあ、どうするんだという話って、まだ全然ないですよね。
そのどうあるべきかみたいな議論のきっかけにと言ったら大袈裟(おおげさ)かもしれませんが、池に一石を投げ入れられたらぐらいの感じはあります。
――そういう意味でも、このオリンピックがひとつの分岐点というか、後世においてターニングポイントになる歴史の端緒でもあるのかと。
堂場 そうですね。問題は誰がそこで石を投げるかということで、これから僕が個人的に興味を持って見ていくところです。特に若い現役の選手が、何かいい改革案を出してくれるとすごくいいなと思いますけど......過去にはこんなこともあったんだよというのをこの本で知ってもらって、何か今に生かせる材料として頭の片隅に考えてもらえたらいいですね。
――今後の作品でまた旺盛な創作意欲が発揮されるのも楽しみです。
堂場 全国民を巻き込んで熱狂させるものなんてないと思うので、オリンピックみたいな大イベントの在り方を議論していくべきという気はしますし。いずれまたそういう話も書きますよ。20年書いてきて、まだ面白いと思うもんね、小説って。
●堂場瞬一(どうばしゅんいち)
1963年、茨城県生まれ。2000年に『8年』で第13回小説すばる新人賞受賞しデビュー。スポーツ青春小説から警察小説まで幅広いジャンルで人気作家に

■『幻の旗の下に』〈集英社〉
幻に終わった1940年東京オリンピックの代わりに計画された、新たな国際競技大会。その実現と参加に向け、海を越えた友情を信じて奔走するふたりの若者がいた――知られざる歴史を浮かび上がらせる圧巻の交渉小説!