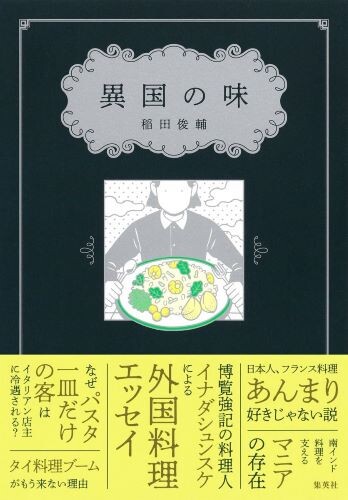「食の原理主義者」を自認する稲田俊輔氏は、南インド料理とミールスブームの火付け役となった南インド料理店「エリックサウス」総料理長でもある
「食の原理主義者」を自認する稲田俊輔氏は、南インド料理とミールスブームの火付け役となった南インド料理店「エリックサウス」総料理長でもある
キャベツが主役の回鍋肉(ホイコーロー)、鮮魚のカルパッチョ、ベーコンのカルボナーラ(生クリームベース)、甘くてフカフカのナンと辛さを選べるバターチキンカレー。どれも日本人の口に合うようにローカライズされた"日式外国料理"だ。
「へえー初めて知った」という方、あなたは「普通の人」です。逆に「そんなの知ってるわい!」という人は、もしかしたら「食の原理主義者」(あるいはその素質がある人)かもしれません。
世界各国・各地の料理そのものを再現すること、あるいはそれを食べることを至福の喜びとする原理主義者たち。逆に、日本人の舌に合うように外国料理を"魔改造"して広めてきた挑戦者たちと、それを受け入れてきた大多数の普通の人々。
この両輪によって形づくられた日本独特の外国料理文化を描いたのが、南インド料理店「エリックサウス」総料理長を務める稲田俊輔(イナダシュンスケ)氏のエッセイ『異国の味』だ。
* * *
――この本では「まえがき」で、「僕自身は完全なる原理主義者です」と、ご自身の立場をはっきり示しています。どちらにも与(くみ)さない第三者の立場から書く選択肢もあったと思うのですが、なぜこの形を選んだのでしょうか?
稲田 原理主義者って、数の上ではいわば"珍獣"なんです(笑)。僕の周りにはインド料理マニアといわれる人たちを中心に、珍獣がかなりの数生息していますが、その中では当たり前のことが、たぶん外から見ると不思議な生態なんだろうなと。
この本では客観的な資料ではなく物語を作りたかったので、珍獣の行動や考え方をある種の見世物にしたほうが、エンターテインメントとして面白くなるだろうと思いました。
多くの原理主義者たちには「自分たちは特殊である」という意識が間違いなくあると思いますし、それがいい意味でのプライドにもなっています。彼らはよく「普通の人々」という言葉を使うんですよ。しかもためらいなく(笑)。
その上で自分を「珍獣です」みたいにちょっと卑下するか、山岡史郎(@『美味しんぼ』)のように「われこそはエリートである」という自意識になるのかは人それぞれですが、いずれにせよ数の上では少数であっても、新しい異国の味の文化が広まっていくときには、間違いなく重要な役割を果たしてきたと思います。そのドキュメント的なものを描きたかったというのもありますね。
――この本を読むと、原理主義者の考え方や生態を知ることで、逆にそうではない自分の立ち位置もはっきりしてくるような感覚がありました。例えばスペイン料理の章では、原理主義者側から見た違和感の一例として、「なんちゃってバル」の「いぶりがっこクリームチーズ」や「アボカドサーモンタルタル」を挙げていますが、ああ、自分は何も気にせず注文していたなとか(笑)。
稲田 普通はそういうものを当たり前においしいもの、最近流行しているものとして食べますよね。ところが原理主義者やその周縁の民から見ると、ものすごい違和感というか、独特のストーリーを背負った食べ物という位置づけになる。いい悪いではなく、哲学がまったく違うという話だと思います。
――でも、それでいながら"普通の人々"も、イタリア料理と言われるよりシチリア料理、シチリア料理と言われるより南シチリア料理と言われたほうがイイ感じに受け取るみたいなところがありますよね。
稲田 自分は正しいものを食べているという安心感なんでしょうね。決して悪い意味ではなく、"本場の味"という言葉自体がブランド的になっているというか。
ルイ・ヴィトンだから間違いないでしょうという感覚と、本場の南シチリア料理らしいから間違いないでしょうという感覚は、わりと似ているのかなと思います。
――だけど、その南シチリア料理は、実際はもしかすると日本人向けに"魔改造"されたものかもしれない。
稲田 そこには確かに矛盾というか人間の複雑さがあって、本場を求めるけど本当に本場の舌に合わないものを出されたら困るな、という人のほうが多いんです。でも、そのあたりをあいまいにしたまま楽しめるからこそ、日本ではさまざまな外国料理が受け入れられてきたのかもしれません。
ちなみに原理主義者としては、ホンモノの本場の味が出てきてちょっと食べづらかったりすると、むしろうれしくなります。俺の側がまだ合わせられていないだけなんだ、みたいな(笑)。
――この本には、普通の人も原理主義者も、どちら側からも楽しめるであろう"あるある"も多いです。「ついたての向こうに一卓だけ回転テーブルがある中華料理店」とか、「確かにおいしいけど、すっごくおいしいというわけでもない結婚式場のフランス料理」とか(笑)。
稲田 それは自分でも意識して書きました。両方の視点から違う風景が見えるんだけど、そのどちらかは自分にとっての"あるある"であり、もう一方は"珍獣見物"である、みたいなものになっていると思います。
――それと、驚かされるのが稲田さんの持つ「食の記憶」です。子供の頃に一度だけ食べた料理の味も見た目も、ものすごく鮮明に覚えていますよね。文章でもその再現度合いがすさまじくて、引き込まれます。
 子供の頃に一度だけ食べた「ポークステーキ・グリーンペッパーソース」の食感をはっきりと覚えているという稲田氏。特殊能力......!
子供の頃に一度だけ食べた「ポークステーキ・グリーンペッパーソース」の食感をはっきりと覚えているという稲田氏。特殊能力......!
稲田 それに関しては、われながらよくこんなにディテールまで覚えているなと思うことが多いですね。僕はなんとなく料理や食べることを自分の職にして、ここまで続けていますが、そういう記憶は確かにものすごく役立っています。あの感じに豚を焼くにはどうやったらいいんだろうってめちゃくちゃ試行錯誤したりとか。
――この本では中華、ドイツ、フランス、タイ、ロシア、イタリア、スペイン、アメリカ、インドという順で外国料理を取り上げています。これは『よみタイ』での連載順そのままですが、その意図は?
稲田 自分にとって特別なものであるインド料理を最後することは決めていました。あとは、イタリア料理は重要なところで出そうと。日本で一番成功した外国料理であるイタリア料理が今までやってきたことを基準に、それと比較していろいろ語るのがわかりやすいだろうと思ったんですね。
ただ......イタリア料理は、いろいろと情熱を持っている方がおそらく一番多い料理でもあります。ものすごく平たくいうと、最も炎上する確率が高い(笑)。ですから、それを書く前にある程度練習を積もうということで、最初はアルバムのオープニングチューンのように、キャッチーでみんなが好きな中華から始めました。
――イタリアンがここまで成功しているのは日本だけなんですか?
稲田 ここまでの一極集中というのは、かなり特殊なんじゃないかと思います。例えばヨーロッパでは、どの国でも一番正式な食事はフレンチで、そこに地元のローカル料理が加わったものでもてなしをしますというのが基本です。ところが日本では、完全にイタリアンがフレンチを人気の上でも数の上でもしのいでいますよね。
――確かに、誕生日のディナーでもイタリアンが選ばれがちな気がします。ここまで圧倒的王者になったのは"魔改造"のおかげなんでしょうか?
稲田 そこにはものすごく複合的な理由があって、いろんな要素ですべて高得点をたたき出し続けたという言い方が正しいかもしれません。
歴史的に見ても、たらこスパゲティの発明とか、カルボナーラがクリームソースっぽくなった工夫とか、そういった巧みな改造が成功してきた一方、まったく違う軸の話として、そもそも日本人に好まれやすいタイプの料理だったということもあります。2010年頃から大流行したナポリピッツァなんてまったく改造されず、そのまま受け入れられて定着しましたし。
――そのイタリアンひとり勝ちの中で、1980年代中頃以降に流行したタイ料理は「パラダイムシフトだった」とも書かれています。
稲田 僕がタイ料理に出会ったのは1990年頃でした。当時ももちろん外食の主役はイタリアンだったんですが、なんというか、人生の主役の人たちが行く場所という感じだったんですよ(笑)。
――なんとなくわかります(笑)。
稲田 バブルの時代にブイブイ言わせてた若者のヒエラルキーの頂点にいるお兄さん、お姉さんたちのものだったというか。僕は自分なんかダンゴムシみたいなものだと思ってましたから、今さらそこに乗り込むのは気が引けたんですが、タイ料理が出てきたときに、これはピラミッドがひっくり返るかもしれないと。
バブル期のイケイケのヒエラルキーみたいなものとは全然違うところで楽しめる世界が出てきたという感覚でしたね。
――コロナ禍が明けて外国人観光客が増え、今後は移民が増えていくとの予測もあります。日本における外国料理は、この先どうなっていくと思われますか?
稲田 ここ最近の日本人の傾向は、残念ながら食に関して保守化の傾向があって、新しいものがなんでも好まれるという感じではなくなっています。その流れはまだもう少し続くかもしれませんが、だからといってずっと変わらないものではないという感覚もあるので、また人々がある種軽薄に、新しいものに飛びつく時代がきっと来るだろうと思っています。
一方で、移民の方が同胞のための飲食店を開き、そこに日本人がお邪魔させてもらうというような形は、今後間違いなく増えていくでしょう。考えてみれば、世界的にはそれが外国料理のスタンダードなんですよね。
外国料理好きとしては、そういう方向で新たなものと出会える時代になっていくのも楽しみです。
●稲田俊輔(イナダシュンスケ)
料理人/飲食店プロデューサー/「エリックサウス」総料理長。京都大学卒業後、飲食メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加。2011年、東京駅八重洲地下街に南インド料理店「エリックサウス」を開店。南インド料理とミールスブームの火付け役となる。『ミニマル料理 最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる現代のレシピ85』(柴田書店)、『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』(扶桑社新書)、『お客さん物語 飲食店の舞台裏と料理人の本音』(新潮新書)など著書多数。
■『異国の味』
集英社 1650円(税込)
日本ほど、外国料理をありがたがる国はない。なぜ「現地風の店」が開店すると、これほど日本人は喜ぶのか? 中華、フレンチ、イタリアン、タイ、インド料理ほか、各国料理が日本の日常食に浸透していった過程を、博覧強記の料理人が数多くのエピソードとともに綴る。読めば必ず食べたくなる「異国の味」エッセイ。