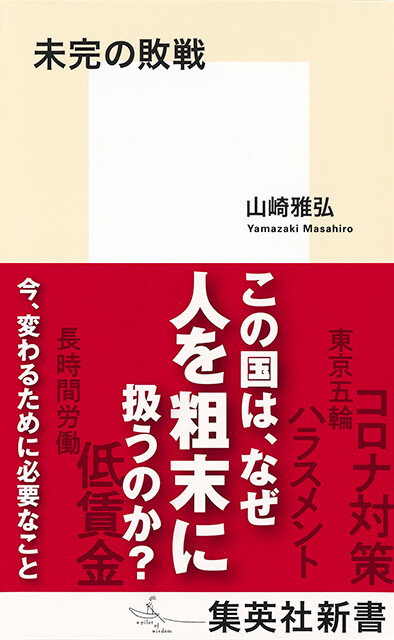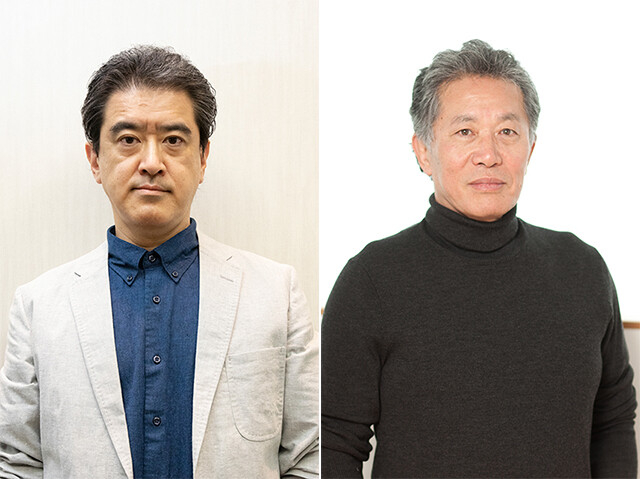 対談した戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏(左)と思想家の内田樹氏(右)
対談した戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏(左)と思想家の内田樹氏(右)
コロナ・パンデミックで日本政府の後手後手の対応に怒りを覚えた人は多いだろう。失政により多数の死亡者を出しても、為政者が責任を取ることもなく、政策の見直しを迫られることもない。コロナに限らず、長時間労働に長引く低賃金、外国人技能実習生への冷酷な仕打ちなど、この国では、人の命があまりにも軽んじられていないか──? そうした思いから、戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏が『未完の敗戦』(集英社新書)を上梓。思想家の内田樹氏と対談を行った。
(本対談は、2022年7月9日に大阪・隆祥館書店にて行われた『未完の敗戦』刊行イベントの内容を一部抜粋して構成しています)
■ここまでおかしな国は他にない!?
山崎 日本の組織は、支配層や上層部の利益が全体の利益になると思わせて、都合のいいように人々を従わせていると思います。例えばSNSでも、職場環境や雇用の問題に関心が集まった時、自分は会社に雇われている側の一人なのに、なぜか経営者の目線で思考し語る人が少なくない。支配層の利益に沿うことが自分の利益にもなるんだと思い込まされている感じがするんですね。
原発にしても、エネルギー資源の乏しい日本で脱原発は無理などと言われますが、福島第一原発よりさらにひどい最悪の事故が起きれば、国民の生活そのものが成立しなくなる。また、外国からミサイルが飛んできた時、原子炉そのものは衝撃に耐えたとしても、外部電源が破壊されれば原発は爆発するという事実を、我々は福島の事故で学んだはずです。なのに、この国の支配層は原発が攻撃される可能性から目を背け、外国との戦争に備えて敵基地攻撃能力が必要だなどと言う。彼らの言うことを聞いていたら、我々はまた何回でも犠牲になっていくでしょう。
内田 自分にとって利益よりも損害の多い政策を支持するという、どう考えても不合理なふるまいをしている人が日本人の過半になっています。大阪はコロナで多数の死者を出しました。行政の不適切な感染症対策のせいで、死ななくてもいい人が死んだ。雇用環境も劣化している。教育に至っては日本最低レベルまで下がった。現に深刻な実害を被っているはずの大阪の市民たちが、にもかかわらず自分たちにリアルな損害を与え続けている当の政治勢力に圧倒的な支持を与えている。このタイプの倒錯が全国的な規模でも起きていると思います。
なぜ、このような不条理なことが起きるのか? それは、「自分にとって本当にたいせつなことは何なのか? 自分の心と体が本当に求めているものは何なのか?」を問うてはならないと日本人が子どもの頃からずっと教え込まれているからだと思います。「自分は何をしたいのか?」よりも「自分が何をすればほめてもらえるのか」の方を優先的に考えるように仕込まれている。自分の中から湧き上がる内発的な感情や思念を抑圧して、外部評価で高いスコアをつけられるように感じ、行動することが「正しい生き方だ」と教え込まれている。
学校では先生がまず問題を出して、子どもたちが答えを書いて、それに対して先生が採点をして、その評点に基づいて資源の傾斜配分が行われます。それがすべての教育活動で行われている。ですから、子どもたちは「問いに答えてよい点をもらうことが唯一の自己実現の方法だ」と信じている。
武道ではそういう構えのことを「後手に回る」と言います。「後手に回る」と必ず敗ける。それは禁忌なんです。ですから、武道ではいかにして「後手に回らないか」を教える。僕が道場で教えているのは、学校で骨身にしみこむまで教わった「査定されて高いスコアを取る」ことをめざすマインドを解除することなんです。
相手が問題を出して、自分がそれに答えて、採点されるのを待つというのは、典型的に権力的な関係です。ですから、相手に対していきなり優位に立とうと思う人間は、必ず相手に質問します。どんな質問でも構わない。相手が正解を知らないような問いであれば、何でもいい。「あなた、...を知ってますか?」と切り出して、いきなり「試験官と受験生」の関係に持ち込む。これにうっかり応じた瞬間に、そこには権力的に非対称な関係が出来上がる。だって、何を答えようと、相手が採点者で、自分はその採点を待つだけという非対称的な関係がもう出来上がっているから。どうして「私が出題し、お前が答える。その答を私が採点する」というような圧倒的に不平等な関係を無抵抗に受け入れてしまうのか。そういう関係を子どもの頃から刷り込まれているからですね。「後手に回る」ことに習熟しているから、あっさり「先手を取られて」しまう。
出題されて、答えて、採点されて、評点が高ければほめられ、低ければ罰される。それが社会的なフェアネスだと信じ切っている。「後手に回る」というのは「支配される」ということです。日本の学校教育は「支配される」マインドを子どもたちに刷り込んでいる。でも、生きる上で、最も大事なことは、他人に査定されて、点数をつけられることではなく、自分自身の生きる知恵と力を高めてゆくことなんです。言葉にしてみると簡単なことなんですけれども、これが現代日本では常識になっていない。
■なぜ日本の組織は「非効率」で「非倫理的」なのか?
山崎 本当にその通りだと思います。学校教育がその要因になっているという面もありますが、それはやはり社会の価値観の反映だと思います。外国に行くと、みんな本当にしたたかで、図太く自由に生きているなと感じます。自分の自由や権利が政府や雇用主に侵害されたと感じたら「自分の権利をちゃんと保障しろ」という主張を、誰もがやっている。それは、「わがまま」ではない。人間として、正当な主張なんです。それによって議論が生じることもありますが、それは相手と自分は対等であるという考えに基づくものです。
お店に行っても、客と店員、みんな対等です。でも日本では、なぜか上下の序列が作られる。客は自分が店員より偉いと思い込み、店員に横柄な態度を取る。上下関係があると、お互い尊重し合うという関係が生まれない。上の者は下の者をないがしろにしても許されると思ってしまう。こうした身近なところから少しずつ変えていかないと、人を大事にするという意識改革はできないのかなという気がします。
内田 この前、感染症内科が専門の岩田健太郎先生とお話ししたときに、似たような話を伺いました。日本社会においては、どこでも「どっちが上か」ということがまず配慮される、と。岩田先生はエボラ出血熱のとき、シエラレオネで医療チームのメンバーとして参加されたのですが、そこには「国境なき医師団」とかWHOとか、世界中からさまざまな組織が来ていて、その混成チームが指定された場所に集まって、さあ今から治療を始めるというとき、まず問われるのが「おまえは何できるんだ?」ということだそうです。自分は隔離病室を作れる、自分は発電機を操作できる、自分は自動車を直せる、自分は感染症の手順を知っている...、そういう自己申告に従ってジョブ型の集団を作って、治療が始まる。
ところが、日本で被災地や感染症の発生現場に行くと、最初に聞かれるのが「おまえは何者だ」ということなんだそうです。まず医師か看護師か薬剤師かという職能を聞かれ、次に出身大学を訊かれ、医局を訊かれ、卒後年数を訊かれる。何のためにそんなことを訊くのかというと、誰に対しては敬語を使い、誰に対してはため口をきき、誰に対しては偉そうにしてよいのか、その上下関係をまず確認するために(笑)。
岩田先生が、コロナウイルスによるクラスター感染が発生した「ダイヤモンド・プリンセス号」に入ったときも、誰も「あなたは何ができるのか」を問わなかった。何よりも優先されたのは「ここでは誰が一番偉いのか」ということで、それは橋本岳という当時の厚生労働副大臣だった。でも、この人は政治家ですから、感染症のことは何も知らない。でも、その人が感染爆発の現場で決定権を握っている。
感染症の専門家として岩田先生は「これじゃ駄目。やり方が間違っているから、やり直しなさい」と当然アドバイスするわけです。でも、日本ではこのふるまいは「専門家が非専門家に指示を出す」ふるまいではなく、「下の人間が上の人間に指示を出す」ふるまいと解釈される。これは日本では絶対の禁忌ですから、ただちに「出て行け」と言われる。
感染症の現場なんですから、感染症の専門家の指示が最優先的に聞かれるべきであることは明らかですけれども、日本の場合は「上位者の指示に従えないやつは出て行け」ということになる。これが日本の組織を徹底的に非効率で非倫理的なものにしていると思います。
■結果よりも「頑張っている」という印象が大事
山崎 そうですね。日本の組織では序列の上下のほかに、精神論も重視されます。先の戦時中の日本軍がまさにそうで、戦争初期のうちは、軍事的な合理性もある程度考慮して戦っていましたが、1942年6月にミッドウェー海戦が起き、日本海軍は主力空母4隻を失って、アメリカに勝てる望みを事実上失った。そして、同年の後半以降、どんどん戦況が悪化していきました。
そうした中で日本軍は、どうやってアメリカに勝つかということよりも、「いかに頑張っている姿勢を示すか」という精神論に判断基準がシフトしてった。その考え方が行き着いた究極の姿が「特攻」です。もう戦争でアメリカに勝てないとわかった時から、勝つために頑張って命まで捧げる姿勢をアピールすることが目的化した。
なぜそのような思考法が出てきたかというと、人の命を大事だと思わない精神文化に思考を支配されていたからだと思います。日本の場合、天皇という特別な存在があるので、国民の命の価値も、天皇と比べてどうかという話になってしまう。そのバランスが極端におかしくなったのが昭和の大日本帝国時代です。当時、国民は「臣民」と呼ばれていました。つまり「天皇のために尽くして奉仕するための存在」だと。天皇のために何をするかという基準でしか存在価値が評価されない。そういうエキセントリックな思考になってしまった。
明治時代や大正時代は、まだそこまで極端ではなかったんです。特に大正時代は、軍人であっても自分の権利は認められるはずだという認識はあった。それが昭和に入って全くなくなり、本当に人の命が使い捨てのように扱われた。
恐ろしいのは、悪意があってそんな精神文化になったというよりも、当時の価値観の中で、みんなお国のために役立つ、いいことをしているつもりだった。おかしいと思っていた人もいたはずですが、それを口に出しては言えない。言うと、「おまえは国や社会よりも自分のほうが大事なのか!」と罵られてしまうので、それが怖いから言えなかった。その同調圧力が極端に高かったのが昭和の大日本帝国時代で、敗戦を経て、それが無くなったと思っていました。でも、気がつくとこの10年ぐらいでそれが社会に戻ってきた感じがします。
内田 どうして日本人がこんなふうなゆがんだ人権意識を持つようになったのか、それについてはやはり歴史的経緯を見てゆく必要があると思います。幕末から明治初年にかけて、それまで存在した幕藩体制が解体されて、300の藩がなくなり、建前上は「一人の天皇が全国民を統治する」というかたちになりましたね。この「一君万民」という思想はそれまで300人の殿様がいて、武士や役人たちに人間扱いされてこなかった民衆にとっては衝撃的なものだった。
少し前まで「殿様」として雲の上にいた藩主も、威張り散らしていた武士も、百姓と同格の「万民」の一人だとされたわけですから。
「一君万民」の思想というのは、幕末から明治初年にかけての時期においては、それなりにデモクラティックな思想だったわけです。天皇をはるか高みに祭り上げることによって、それ以外のすべての日本人が同格のものになる。そういうやり方で幕末まで無権利状態に置かれた人々が、幻想的なしかたではあれ、人権を回復する道筋が示された。
世界史を見ればわかるように、民衆の政治的なエネルギーが爆発的に高揚するのは、国家意思と民衆の個別意思が中間的で媒介機構抜きで直接に繋がるという「幻想」が活性化したときです。日本の場合は、天皇が国家意思を人格的に表象しています。ですから、「中間的な媒介物である統治機構を抜かして民衆の個別意思と天皇の国家意思が無媒介に繋がる」という「幻想」がリアリティをもつと日本人は政治的にはげしく高揚する。
明治以降、大衆の政治的エネルギーを功利的に利用しようとした人たちが例外なく「天皇と国民個人が統治機構の媒介抜きで直接繋がる政体」という政治的幻想をレバレッジに用いたのはそのせいです。統帥権というのは、帝国の軍隊を統御しているのは政府ではなく、天皇であるという特異なものです。「上御一人」が単身で全軍を支配している。そういう話にまずはしておいて、その上で、帷幄上奏権(いあくじょうそうけん:君主制国家において軍部が軍事に関する事を君主に対して上奏する権利)を持つ陸海軍大臣、参謀総長、軍令部総長、教育総監らが「天皇の国家意思」なるものを代弁して、彼らの集団的な欲望を実現する。「軍部の暴走」なる事態が可能になったのは、天皇が軍のすべてを統帥しているという日本国民の可憐な夢想がそれを支えたからです。
「日本軍国主義」と言われますけれど、あれは語の本来の意味での「ミリタリズム」ではありません。「ミリタリズム」というのは「軍事優先」ということですから本来は徹底的に計量的で非情緒的な思考を要求するはずです。でも、日本の「軍国主義」はそういうものではなかった。それは「軍隊にあるものはすべて天皇の所有物であり、兵士たちは全員天皇から直接雇用されている」という妄想のことだった。
■人の命が軽んじられるきっかけとなった昭和の事件
山崎 以前、『「天皇機関説」事件』という本を書いたのですが、これは昭和の大日本帝国時代、日中戦争が始まる2年前の1935年に起きた事件です。「天皇機関説」というのは、天皇は一応、神の子孫ということにはなっているけれども、少なくとも近代国家としての大日本帝国の中では、憲法を超越する存在ではないよ、と。当時の憲法学者は、あくまで天皇は一つの国家の最高の機関、一機関として、憲法の枠内でのみいろいろな権能を行使できるという憲法解釈をしていたんですね。それが主流でした。
ところが、軍人や右翼団体が、「天皇は絶対的に崇高な存在なんだから、国の一つの機関などと言うのは不敬だ」と言って弾圧した。帝国議会まで巻き込む形の大騒動になって、最終的には当時の岡田啓介首相が、「天皇機関説」は認めないという声明(国体明徴声明)を出してしまった。それ以降、本当にたがが外れたかのように、天皇を神格化する政治運動や主張がどんどん高まっていきましたが、それで何が起きたかというと、一般国民の命の価値が下がっていったんです。天皇という存在が天に昇れば昇るほど、一般市民の命の値打ちは下がり、虫とか砂粒とか、そんなものでしかないという形になってしまった。そんな冷酷な認識に至る出発点が、僕はあの事件だったと思うんです。
今の日本で、天皇の名前を居丈高に持ち出す人間とはどんな人間かと見れば、例えば「あいちトリエンナーレ」のとき、展示物に乱暴な言いがかりをつけた名古屋市長の河村たかし氏や整形外科医の高須克弥氏などがいます。彼らは、慰安婦問題や南京虐殺などの大日本帝国時代の負の歴史を否認し、当時の日本軍の行いを肯定的に捉えている。つまり大日本帝国時代の精神を今も継承しているわけです。一方で、戦後の民主主義にはほとんど関心を示さない。
今の社会にある人権軽視の状況を一つ一つ見ていくと、結局、根っこはあの時代の精神に行き着くのではないかと思います。厳密には、もっと昔の封建時代にも遡りますが、少なくとも今の日本社会における人を粗末にする考え方の直接の出発点は、昭和の大日本帝国時代に形成された世界観だと思います。
■天皇制と立憲デモクラシーをいかに両立させるか
内田 そういうことが可能になるだけ天皇制には力があるということだと思います。天皇制という太古的な制度と立憲デモクラシーという近代的な制度が並立しているというような奇妙な国は世界で日本しかありません。だから、他国の民主制の成功事例を日本に適用しようとしてもどうしても無理がある。スウェーデンではこうやっている、デンマークではこうやっている、アメリカではこうだ、だから、日本でも...という議論は無理なんです。それらの国々には天皇制がないんですから。天皇制というアクターが政治的幻想のすみずみにまで入り込んでいて、その機能を熟知していないと政治過程を適切にコントロールできないなんていう国は日本にしかない。そうである以上、日本の政治をどうやって統御するかという仕事は僕たち日本人が自分の頭で考えて、自分の手で実行するしかない。誰も僕たちに代わって考えてくれないんですから。
僕は上皇陛下や天皇陛下に対しては個人的には非常に親しみを持っています。日本の国家としての道徳的なインテグリティー(誠実さ)を守っているのはこの方たちではないかとも思っています。僕のこの「尊皇」感情はかなり自然発生的なものです。僕のように久しく欧米の哲学思想に親しんできた人間になぜこのような不合理な感情が生まれてくるのか。そこからもう一回掘り下げて考える必要がある。
天皇制と立憲デモクラシーを両立させることはもちろん原理的には不可能です。でも、原理的には折り合いのつかないものを、実践的には折り合いをつかせるということはできる。なにしろ僕たちの手持ちの政治資源としてはこれしかないんですから。これをなんとか折り合わせて、権力が適切に制約され、市民の人権が十分に守られる仕組みをどうやって作り上げたらいいのか。誰もあらかじめ正解を知っているわけじゃない。自力で考えるしかない。
山崎 そこで重要なのは、自分たちには一人一人に独立した価値があるという事実をみんなが認識することだと思います。学校教育はもちろん、社会全体でそういう認識を持つ必要があります。国や省庁、企業、チームなどの集団に属して、そこに何かで貢献したから自分には価値があるのだ、ということでなく、自分たちはありのままで政府や集団から大事にされるべき存在なんだ、と。それが本物の「民主主義」です。
大日本帝国時代の精神を肯定する人間がよく主張するのが、「子どもが自己肯定感を持てる歴史教育の必要性」です。こういう大義名分で、南京虐殺や慰安婦問題を学校で教えることを禁じようとする。でも、これは完全に欺瞞です。何が欺瞞かというと、「おまえはこんな立派な日本という国の一人なんだ」という形で自尊心や自己肯定感を持たせようとしているところ。
一見もっともらしいですが、個人としてではなく、日本という国につながる者として自尊心を持たせようとしている。そして、国に奉仕や貢献をしない人間は存在を軽んじて、自尊心や自己肯定感を持てないようにする。この詐術にうっかりだまされてしまうと、行き着く先は昭和の大日本帝国時代のような、国や集団への献身奉仕という美談的な大義名分で人を極限まで粗末にした精神文化です。
こうした「情緒的な美談」にだまされないようにしないといけない。なんとなく「仕方ない」と思って我慢している自分の境遇が、実は「人権侵害の不当な扱い」ではないか、自分は「私たちを粗末に扱うな」と、国の支配層にもっと怒ってもいいのではないか、と気付くことが大事だと思います。
●山崎雅弘(やまざき・まさひろ)
1967年、大阪府生まれ。戦史・紛争史研究家。主な著書に、『日本会議 戦前回帰への情念』『「天皇機関説」事件』『歴史戦と思想戦 歴史問題の読み解き方』(以上、集英社新書)、『中国共産党と人民解放軍』『第二次世界大戦秘史 独ソ英仏の知られざる暗闘』(以上、朝日新書)、『[増補版]戦前回帰』(朝日文庫)ほか多数。
●内田樹(うちだ・たつる)
1950年、東京生れ。神戸女学院大学名誉教授、芸術文化観光専門職大学客員教授、凱風館館長。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)で小林秀雄賞、『日本辺境論』(新潮新書)で新書大賞、著作活動全般に対して伊丹十三賞受賞。近著に『レヴィナスの時間論』、『撤退論』、『武道論』など。共著に『新世界秩序と日本の未来 米中の狭間でどう生きるか』(集英社新書)など。