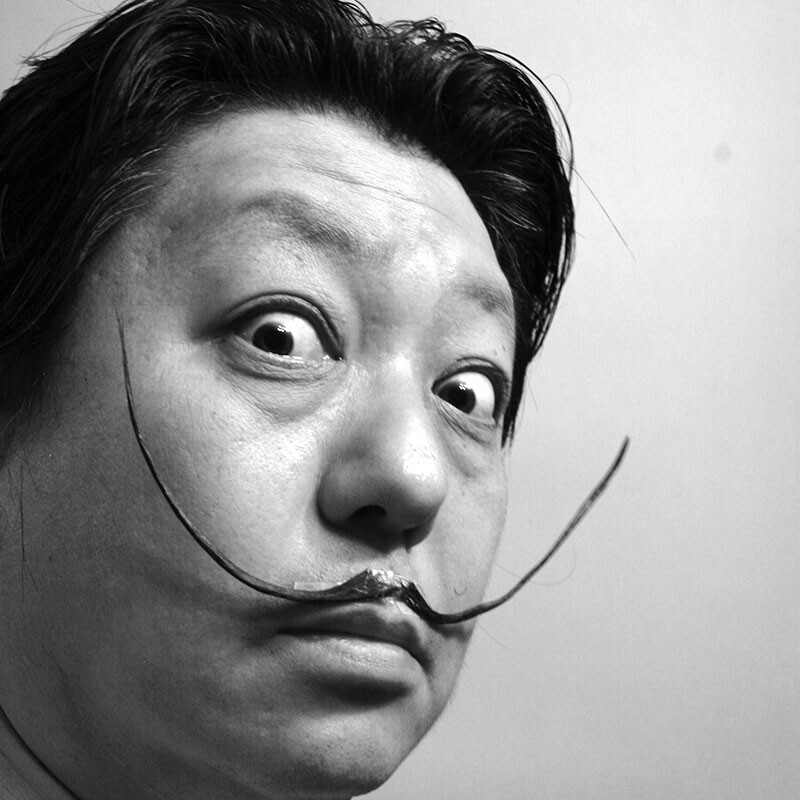
川喜田 研かわきた・けん
ジャーナリスト/ライター。1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。自動車レース専門誌の編集者を経て、モータースポーツ・ジャーナリストとして活動の後、2012年からフリーの雑誌記者に転身。雑誌『週刊プレイボーイ』などを中心に国際政治、社会、経済、サイエンスから医療まで、幅広いテーマで取材・執筆活動を続け、新書の企画・構成なども手掛ける。著書に『さらば、ホンダF1 最強軍団はなぜ自壊したのか?』(2009年、集英社)がある。
 2025年1月のゼレンスキー(47歳)。開戦後から落ちているとはいえ支持率は52%ほど
2025年1月のゼレンスキー(47歳)。開戦後から落ちているとはいえ支持率は52%ほど
ロシア軍が全面侵攻を始めて3年。当初、プーチン大統領はウクライナの首都を数日で攻め落とす算段だった。「元コメディ俳優は逃げ出すはずだ」と。しかし、ゼレンスキーは自撮り配信で「俺は逃げない」と抗戦を呼びかけた。あの日から今日まで、そんな彼の視点で、この戦争を振り返る――。
* * *
2022年2月24日にロシア軍によるウクライナへの全面侵攻が始まってから3年。
今年、そのウクライナにとって最大の支援国だったアメリカがトランプ政権に代わり、「6ヵ月以内に停戦を実現する」と豪語するトランプ大統領がこの戦争の行方をどのように変えるのかに大きな注目が集まっている。
しかし、かつては世界を二分する軍事大国として知られ、今も最大の核保有国であるロシアとの全面戦争に、ウクライナが3年も耐え続けていること自体、驚くべきことなのかもしれない。
そして、3年前の開戦以来、ウクライナのリーダーとして"抵抗のシンボル"であり続けているのが、元コメディアンで俳優という異色の経歴を持つボロディミル・ゼレンスキー大統領(47歳)だ。
下ネタもこなす人気のお笑い芸人として知られ、19年に第6代ウクライナ大統領に就任する直前まで『国民の僕』というテレビドラマや映画で、間違って大統領になってしまった元高校教師を演じていたコメディアンが、プーチンのロシアを相手にこれほどの抵抗を続けるなど、いったい誰が想像していただろうか?
 2019年5月、大統領に就任したゼレンスキー(当時41歳)。得票率は73.03%だった
2019年5月、大統領に就任したゼレンスキー(当時41歳)。得票率は73.03%だった
「それは、多くのウクライナ国民や国際社会、何より本人も同じで、ロシアの侵攻が始まった当初は、おそらくゼレンスキー自身も、本当に自分がこの事態に対処できるのか、半信半疑だったと思います。
しかし、そんなゼレンスキーがこの3年間、英雄的にロシアと戦い続けてみせた。戦争が長引くにつれて支持率は下がっていますが、このような状況でも、ゼレンスキー以外のリーダーを求める声は出ていないし、いまだに5割超のウクライナ国民が彼を支持しています」
そう語るのは、ウクライナ事情に詳しい国際関係学者で筑波大学教授の東野篤子(ひがしの・あつこ)氏だ。
「19年の大統領選までの彼はテレビドラマの中で政治風刺をしていただけで、もともと政治家を目指していたわけでもなければ、実際の政治経験があるわけでもない。
おそらく彼自身にとっても"降ってきた大統領職"という感じだったはずで、私の友人のウクライナ人たちも『ポロシェンコのほうがいい』と言い、誰ひとりゼレンスキーには投票しませんでした」
しかし、ゼレンスキーはコメディアンとしての人気をテコに現職(当時)のポロシェンコを破って大統領に当選。当時の彼は、すでに緊張が高まっていたウクライナ東部のドンバス地方の問題に関して平和的解決を訴えていたという。
 「武力ではなく外交によって平和的に解決する」とうたって大統領に当選した当時のゼレンスキーを、ロシアのプーチン大統領はまったく対等に扱わず、交渉の席に着かなかった
「武力ではなく外交によって平和的に解決する」とうたって大統領に当選した当時のゼレンスキーを、ロシアのプーチン大統領はまったく対等に扱わず、交渉の席に着かなかった
「対ロシア強硬派でタカ派色の強かったポロシェンコ前大統領の政策との差異化もあり、『武力ではなく外交によって、平和的に解決する』というのがゼレンスキーの主張でした。
そのため、フランスやドイツを仲介役にロシアとの対話を試みましたが、肝心のプーチンはゼレンスキーのことを対等な交渉相手とは認めず、まったく相手にされなかった。
また、ロシアによる軍事侵攻の直接的な引き金になったともいわれるウクライナのNATO加盟問題についても、侵攻の直前、ロシア軍がウクライナ国境に集結して圧力を増す中、ゼレンスキーがロシアに『NATO加盟を諦めるから侵攻しないでほしい』と伝えたものの、プーチン大統領が聞く耳を持たなかったといわれていますから、当時はNATO加盟も諦めるつもりだったのだと思います」
 ペトロ・ポロシェンコ前大統領も異色の経歴の持ち主で、国内最大手の製菓メーカー社長から政治家に転身した
ペトロ・ポロシェンコ前大統領も異色の経歴の持ち主で、国内最大手の製菓メーカー社長から政治家に転身した
そんなゼレンスキーの運命を大きく変えたのが、ロシア軍が首都キーウへの侵攻を開始した直後に彼が国民に向けて徹底抗戦を呼びかけた、伝説の「スマホ自撮り動画」だ。
「全面侵攻が始まった当初、ロシアは数日で首都キーウを陥落させ、ウクライナ政府を支配下に置けると考えており、ゼレンスキーも、いわゆる"斬首作戦"で、ロシア軍特殊部隊による暗殺ターゲットになっていました。
そのため、イギリスのジョンソン首相(当時)が『われわれが逃げ道を準備する』と伝えるなど、英米共にゼレンスキーに対して国外脱出を促したのですが、ゼレンスキーはこれを拒否。
側近たちと共にキーウに残り、あの動画で『自分は逃げずに戦い続ける!』と国民に語りかけたことで、ウクライナ国民が一体となって侵略に抵抗する最初の原動力にもなったのです。
あのとき、ゼレンスキーは誰かに指示されたわけではなく、自らの意思で逃げずに戦うことを決めた。それまでゼレンスキーを相手にしてこなかったプーチンにとっても、また、彼に脱出を呼びかけた英米にとっても予想外の出来事で、その後、すでにキーウに迫っていたロシア軍をいったん国境まで押し返すことにもつながりました。
仮にあの『スマホ自撮り動画』がなければ、その後のウクライナとゼレンスキーの運命は完全に別のものになっていたと思います」
こうして、一躍"抵抗のシンボル"となったゼレンスキー大統領だが、このときはまだ戦争の序盤戦。当初はウクライナ軍や市民による予想以上の抵抗と、驚くほどお粗末だったロシア軍の内情も相まって首都キーウの防衛に成功したが、ロシア軍は態勢を立て直すと、ウクライナ東部に戦力を集中して再び猛攻を開始。
その後は、ウクライナ側の反転攻勢によるハルキウ奪還などもあったものの、次第に戦況は膠着(こうちゃく)し、一進一退の泥沼状態が続いている。
「核保有国であるロシアとの戦争が世界大戦に拡大することだけは避けたい欧米の支援が、直接的な軍事支援ではなく『兵器・武器と資金の供与』にとどまる中、ゼレンスキー大統領は、ロシアという"正面の敵"との戦いだけでなく、欧米などの"支援国との交渉"という闘いにも直面し続けてきました。
また、この戦争の難しさは何をもって『ウクライナの勝利』と考えるのかが必ずしも明確ではない点です。
ゼレンスキー大統領も、当初は『22年の侵攻開始以前の状態回復』を目標に掲げていましたが、その後、14年にロシアが一方的に併合したクリミア半島の奪還も訴えるようになった。
もちろん、東部・南部共にロシアが攻勢を強めている現状を考えると、いずれの目標も実現は難しいと言わざるをえませんが、私は、ゼレンスキーが本当に考えているゴールは『失われた領土の回復』ではなく『ウクライナの安全保障』、具体的に言えば『停戦後、いかにしてロシアの再侵攻を防ぐのか』なのではないかと考えています」
どういうことか?
「ゼレンスキーがクリミア半島の奪還にこだわるのも、黒海艦隊の基地がありロシアにとって貴重な中継拠点となっているクリミアが敵のコントロール下にある限り、ウクライナの安全は保障されないと考えているからで、ロシア本土と半島をつなぐクリミア大橋を破壊して孤立させたいと考えているからでしょう。
また、東部の前線で苦戦が伝えられる中、『ロシアを過剰に刺激してしまう』という欧米の懸念を横目に、昨年夏からロシア領内、クルスク州への越境攻撃を開始しました。
これも、長く続く戦争で疲弊したウクライナ国民の士気を高めるだけでなく『支援国がより射程の長いミサイルなどの兵器をウクライナに供給してくれなければ、自分たちはロシアへの越境攻撃を続けるしかない......』という欧米支援国へのメッセージでもあるのだと思います」
元コメディアンの大統領がロシアのプーチンと真っ向から戦うだけでなく、アメリカやEUの大国を相手にさまざまな駆け引きを演じてみせるなど、この3年間、まるで映画のような奮闘を続けてきたゼレンスキー。しかし、この1年は地力で勝るロシアが攻勢を強め、長引く戦争で犠牲者も増え続けている。
 侵攻当初、総司令官として活躍したバレリー・ザルジニー氏は2024年に総司令官を解任され、駐英ウクライナ大使に任命された
侵攻当初、総司令官として活躍したバレリー・ザルジニー氏は2024年に総司令官を解任され、駐英ウクライナ大使に任命された
そうした中、ドナルド・トランプという予測不能な"大物怪優"が重要なキャストに加わったことで、ロシア・ウクライナ戦争は大きな転換点を迎えることになりそうだ。
プーチンとの直接会談もにおわせつつ「ウクライナは将来ロシアになるかもしれないし、そうではないかもしれない」という意味不明の発言をしたかと思えば「アメリカはこれまでのウクライナへの支援に対する見返りが必要だ」と、ディールを迫るトランプを相手に、ゼレンスキーはどんな演技を見せるのだろうか?
「トランプ政権に代わったことで、ウクライナが今後、ロシアとの停戦に向けてなんらかの領土的な妥協を強いられる可能性は高い。その着地点に関する具体的な議論がおそらく25年中に始まるのだと思います。
その上で、ゼレンスキーはいかにしてトランプから有利な条件を引き出すことができるかをシビアに考えています。最近、話題になり始めた『レアアース問題』もゼレンスキーの交渉のためのカードのひとつ。トランプはウクライナ東部のレアアース資源の権益を、米国がこれまでウクライナに対して行なってきた巨額の支援の見返りとすべきだと言い出しました。
急にどこからそんな話が出てきたのかと思うかもしれませんが、実はこのレアアースの利用も、ゼレンスキーが昨年明らかにした『勝利計画』の中に含まれている。トランプ政権との交渉における取引材料として、ウクライナ側が事前に用意していたアイデアのひとつなのです。
ちなみに、ゼレンスキーが国内で人気がある理由のひとつはこうした巧みな交渉術。
もともとウクライナ人は、困難な交渉事でも驚異的な粘り腰を見せる人が多い。ゼレンスキーもそうしたウクライナ人の気質を受け継いでいるからこそ、あの手この手でトランプにアピールしながら『この若造は俺の助けを必要としている』と思わせることが大事だとよくわかっているのでしょう」
コメディアンから大統領に、そして、大国ロシアと戦う英雄となったゼレンスキーの"一世一代の大芝居"、その最終幕はこれからが正念場だ!
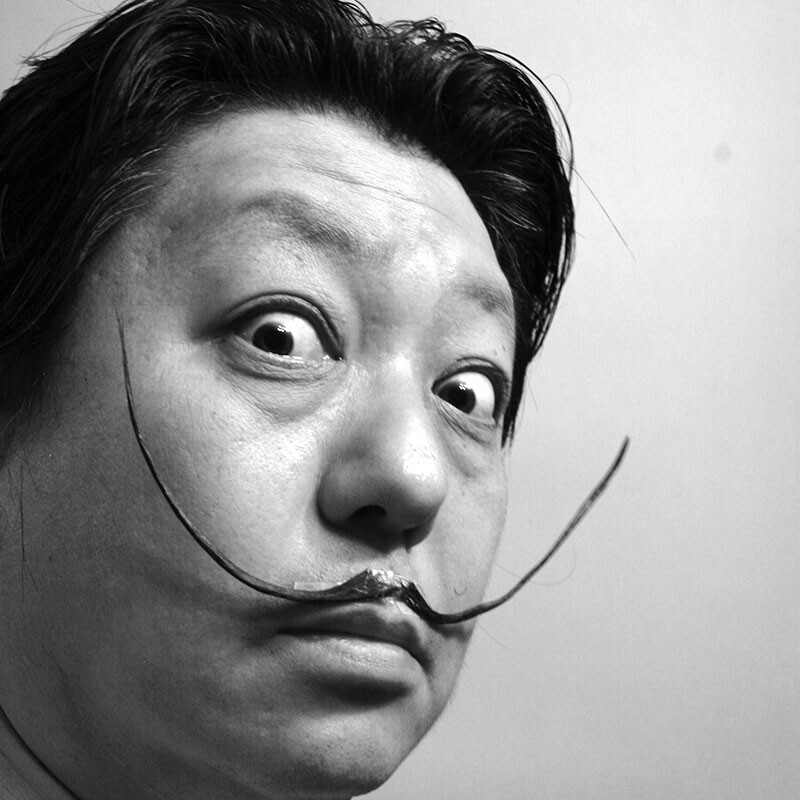
ジャーナリスト/ライター。1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。自動車レース専門誌の編集者を経て、モータースポーツ・ジャーナリストとして活動の後、2012年からフリーの雑誌記者に転身。雑誌『週刊プレイボーイ』などを中心に国際政治、社会、経済、サイエンスから医療まで、幅広いテーマで取材・執筆活動を続け、新書の企画・構成なども手掛ける。著書に『さらば、ホンダF1 最強軍団はなぜ自壊したのか?』(2009年、集英社)がある。