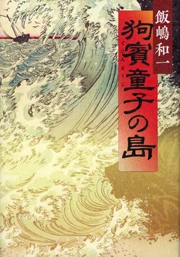自分を突き詰めて考えると孤独になる。その孤独をちゃんと感じ、安易に人とつながらずに自分の直感を信じて形にすることが大事と飯嶋氏は説く
自分を突き詰めて考えると孤独になる。その孤独をちゃんと感じ、安易に人とつながらずに自分の直感を信じて形にすることが大事と飯嶋氏は説く
寡作で知られる作家・飯嶋和一(かずいち)氏。前作『出星(しゅっせい)前夜』(2008年8月刊)から6年余りを経て、新作『狗賓童子(ぐひんどうじ)の島』(小学館)が今年発表された。
時代は幕末。天保の飢饉(ききん)が起きるなど人々は慢性的な米不足にあえいでいた。しかし、幕府は何もしようとしない。大坂では庶民が命の危機にさらされている現状を見かねた大塩平八郎が蜂起(ほうき)するも失敗。それでも大塩平八郎の精神は日本各地に影響を及ぼしていた。そのひとつが松江藩・隠岐(おき)だ。
乱に連座した罪に問われた男の息子が流刑になって送られてくるところから物語は幕を開ける。だが、そこでも人々はひどい政治と重税にあえいでいた。そしてそれに耐えきれず、やがて、島民は蜂起へと向かう。
その光景は、どこか今の日本とそこに生きるわれわれに重なるところがある……。
***
―主人公の西村常太郎は、父親が「大塩平八郎の乱」に参加したことで、当時6歳だった自分まで罪に問われ、15歳で隠岐に流されてしまいます。しかし、島の人々は彼を温かく迎え入れ、やがて医師になり、島のために働くようになる。読みながら、大塩平八郎が行なったことは果たして「乱」だったのか?という思いをまず抱きました。その行動は単に守るべき大事なものを守ろうとしただけではないかと。
飯嶋 「乱」かどうかは江戸幕府が決めたことですからね。お上に逆らえば、「乱」。なんでもそうです。貿易でも幕府が公認すれば正式な貿易になり、それ以外は密貿易にされてしまう。
大塩平八郎はこれまでにも小説に書かれていて、森鴎外なんかも書いているんだけど、どうもよく書かれてはいない。批判的に書かれているんです。その点については「そうじゃないだろう」という思いがありました。
―しかし「乱」にされてしまったことで、常太郎は隠岐に流されてしまう。
飯嶋 隠岐では大塩平八郎が人々にどのように受け止められていたのかを常太郎の視線を通して描いてみたいという思いがありました。いや、大塩だけではなく、松江藩の苛政(かせい)と重税に耐えかねた隠岐の人々の間で「隠岐騒動」(1868年、明治元年)が起こりますが、それも常太郎にはどう見えていたのだろうというのもあります。
どの視点からものを見るかで姿は変わってきます。江戸幕府以外の見方はどうだったのか? 違う角度で見てみようというわけです。小説を書くという行為は、これまでと違った見方を提示することに意味がある、と言ってもいいと思ってますから。
どの視点からものを見るかで、姿は変わってくる
―隠岐の人々の視線も物語を動かす重要な要素だと思いました。常太郎は絶海に位置する隠岐のなかでも最大の島の「島後(どうご)」に流されますが、物語の冒頭、島の人々が常太郎を迎え入れるシーンは感動的です。読者としては流人が手厚く扱われることを意外に思いつつ、常太郎の理不尽な境遇には同情しているのでホッともします。その裏には大塩平八郎の影響があることを知ります。
飯嶋 天保の飢饉、米不足、人々の窮状、その状況に何もしようとしない幕府に業(ごう)を煮やしたひとりが大塩平八郎です。なんとかして人々の生存権を守らなければいけない。大塩は蜂起を促す「檄文(げきぶん)」を書いていろいろな人に読ませていました。蜂起(ほうき)を促す内容です。その「檄文」が日本各地に伝わって読まれていたようなんです。隠岐の人たちも読んでいたことでしょう。
―それが、流されてきた常太郎を温かく迎え入れる素地になり、15歳の常太郎は島に育てられることになります。
飯嶋 人間誰しも自分の置かれている現実と、こうありたいという理想の両方があって、そのギャップに苦しみますよね。常太郎も苦しみます。父親は死罪、母親や弟とも離れ離れになってしまった。弟も流刑になっています。家族に会うなどという、ごく普通のことさえできないわけです。
ただ、どうしたってひとりの人間ができることは限られていて、人生だってそう長いものでもなくて、その場その場でどうするかが重要になってきます。常太郎は島で医師になり、人々の役に立つ道を選びます。流人としての境遇を受け入れながら、島の激動を見届けることになる。
―島でコレラが流行した時、常太郎は寝ずの治療を続け、船頭や漁師や庄屋も採算度外視、命がけで薬の調達に走り回ったり。その姿はこれまでの飯嶋作品にもずっと描かれてきた登場人物たち、常に他人のことを思い、驕(おご)らず、偉ぶらず…そういう人たちの生き方と同じです。
『狗賓童子の島』でも、歴史に名を残すような大きなことを成し遂げようとか、自分の正しさ、すごさを証明し見せつけようとかするのではなく、自分の身の回りの人を思いやり、大切にし、助け合う生き方こそが人として一番大事であり、そしてそれで十分なのだとあらためて確認させられ、心に染みました。
「狗賓」とは何か?
■自分の直感や違和感を今こそ「行動」という形に
―タイトルになっている「狗賓童子」は、聖性であるとか浄化作用のようなものであるとか、島の何かを象徴する存在だと思います。「狗賓」(深山に棲[す]む天狗[てんぐ]のこと)が宿るという山の千年杉があって、そこに初穂をささげる役を常太郎は島の人々から命じられます。その場所には狗賓に許された者しか入ることができない。狗賓というモチーフは以前から温めていたのでしょうか?
飯嶋 小説ですから、事実そういう存在がいたかどうかはまた別です。ただ、隠岐にしても八丈島にしても佐渡にしても、人が流された先ではいろいろなことが「起きた」はずです。トップの権力者だって政治犯として流されるし、凶悪犯だって流される、いろんな連中が流された先でのことです。例えば、島の若衆たちがどうしようもない流人を島のために葬ってしまったなんてことがあったかもしれない。それを小説で描く際に「狗賓」の仕業という姿にしてみました。
―常太郎を預かるのは庄屋の黒坂弥左衛門です。「大塩の乱」に加わった常太郎の父親も庄屋でした。今の日本でいえば支配層、あるいは富裕層に当たる人たちが、民衆の苦しみにシンパシーを持って描かれていることもグッとくるところでした。現在の日本と全然違うという意味でも。
飯嶋 常太郎の父親の西村履三郎にしても弥左衛門にしても、名主や庄屋といえば支配構造の末端の層ですね。かつ一番楽な立場でもあるわけです。責任を負わず、何もせず日和見(ひよりみ)でいることもできます。何かをしようとしなければ楽でいられたのに蜂起した。何がそうさせたのか? 民衆の生存権を守ろうという思いは当然あったはずですが、もうひとつ、その場に際して自分がどうあるかでしょうね。見過ごすのか、自分ができることをやるのか。
例えば、今の日本を見てもこのままではいいわけがない、ということだらけです。権力側は「おまえたちのためにやっているんだ」という物言いですが、それが果たして本当なのかは大いに疑問です。
―作品の中でも隠岐を治める松江藩は搾(しぼ)るだけ搾っておいて、幕末、藩政が揺らぐと自分たちがどう生き残るかしか考えられなくなる。権力者はいつの時代でも庶民ではなく自分たちを守るのみ。「国が自分たちを守ってくれる」というのは幻想ですよね。
飯嶋 その通りだと思います。自分たちを守るのはひとりひとりの行動しかありません。我々に伝わってくる情報は限られたものでしょうが、その範囲内で考え、動くしかない。その時、頼りになるのは直感です。直感は何かおかしいぞと告げてくれます。なんとなく不快だとかイヤだとか違和感があるとか、そういう「直感で物事を判断する」のは有効だと思います。知識ではなくて、直感でつかんでいることはたくさんあるはずなんです。
「直感で物事を判断する」のは有効
―『狗賓童子の島』の登場人物、例えば漁師の喜六にもそれを感じました。この生活の苦しさは道理に合わない、やっぱりおかしい、と思い始める。そのひとりひとりの直感が「全島蜂起」につながっていきます。
飯嶋 感じたことを言わないといけないんでしょうね。言わずに、感じていたイヤなことが形にされてしまってからではもう遅いですから。今の日本でも、原発の再稼働も憲法も自衛隊派遣の問題も形にされてしまいそうですよね。
―しかも、税金は上がる、年金は下がるで「貧乏人は死ね」と言われているような状況…そこも小説の舞台設定と重なるところでした。
飯嶋 人間の価値が経済だけで測られてしまっているところはありますよね。金をいくら稼いでいるとか、いくら持っているとか、そういうことよりも、その人は何をしたか、何を考えたかが大事なはずなんですけど。
でも、突き詰めてものを考えようとすると、自分が他人と違うことを自覚するかもしれません。それは孤独につながるんだけど、その孤独をちゃんと感じることも大事だと思います。安易に人とつながろうとするのではなく、孤独になって本でも映画でも昔のものだって構いません、その中に自分の直感が反応するものを見つければいいと思います。そして、直感を行動という形にしていくのです。
―『狗賓童子の島』に限らず、飯嶋作品の登場人物はいつも直感を形にする生き方をしていますよね。
飯嶋 感受性のない人なんていませんから、みんな何かを感じています。その人その人で違うことを感じていて、それが本当の自分なのに、それを形にしないでいるとみんなが同じように流される。それを平等だとか安心なんだと勘違いしてしまう。大間違いですよ。
―隠岐島後に人々はいろいろなものを押しつけられながら、蜂起という形で直感を形にした。今の日本で直感によって反旗を翻しているのは今や沖縄の人たちだけかもしれません。
飯嶋 現実でそういう大きな話が進行しているからこそ、『狗賓童子の島』では隠岐という限定された辺境を舞台に選びました。そこで常太郎や弥左衛門や喜六は直感による行動を選びます。すごくローカルな所で起きたことが日本全体にとって大切なことであったと。
―自分の直感に従って、自分と周囲を少しでもよくするために自分ができることを行なった人たちの物語が『狗賓童子の島』。今の政治について「変だぞ」と感じたことのある人は絶対に読んでほしいですね。
(取材・文/近藤邦雄 撮影/五十嵐和博)
●飯嶋和一(いいじま・かずいち) 1952年生まれ、山形県出身。1983年『プロミスト・ランド』で小説現代新人賞、88年『汝ふたたび故郷に帰れず』(小学館文庫)で文藝賞、前作『出星前夜』(小学館文庫)で大佛次郎賞を受賞した。ほかに『雷電本紀』『始祖鳥記』『黄金旅風』(すべて小学館文庫)などがある
■『狗賓童子の島』(小学館)
幕末、「絶海の孤島」隠岐「島後」に15歳の少年・西村常太郎が流されてくる。罪状は父・履三郎が「大塩平八郎の乱」に加わったこと。未来を絶たれた常太郎を隠岐の人々は温かく迎え、育てる。背景には政治に虐げられ続ける島民の思いがあった。常太郎は医師になりコレラの流行から人々を守るべく奔走。同時に、病気と圧政による窮状で、島民の怒りは蜂起へと向かう。どんなに苛烈な状況にあっても運命を受け入れ、なすべきことを誠実に成し遂げる、飯嶋作品ならではの登場人物たちの生きざまを、この時代にこそ、読め!