 『十五歳の戦争 陸軍幼年学校「最後の生徒」』の著者・西村京太郎氏
『十五歳の戦争 陸軍幼年学校「最後の生徒」』の著者・西村京太郎氏
この9月に87歳の誕生日を迎える作家・西村京太郎氏の新刊『十五歳の戦争 陸軍幼年学校「最後の生徒」』(集英社新書)は、ご自身の戦中から戦後にかけての体験と、そうした体験を通して得た「日本人は戦争に向いていない」という考えについて書かれている。
「生れてから七年間は平和だった。昭和十二年に盧溝橋事件があって日中戦争になり、昭和二十年まで、八年間延々と戦争が続く。十五歳までである」とあるように、幼少期を丸ごと戦争とともに過ごし、敗戦の年4月には東京陸軍幼年学校に入学、同校の最後の生徒として、短いながらも士官候補生の教育を受けている。
戦争の悲惨さを身をもって知り、戦後70年の一昨年、「安保法案」が国会で可決され、「戦後」が「戦前」の様相を呈してきたことに危機感を覚え、その年末から翌年に刊行された十津川警部シリーズ作品にはどれも戦争、戦後のことを組み入れるなど、戦争体験の風化を押し止めようとしてきた思いの集大成ともいえる本書を書き終えた西村氏にお話を伺った。
■なぜ戦争がいけないのかをきちんと書いておこう
─戦後70年の一昨年、このあたりで戦争のことをきちんと書いておかなければいけないということで、『無人駅と殺人と戦争』『一九四四年の大震災』『北陸新幹線殺人事件』などにはすべて戦争のことが書かれています。
西村 ええ。何か大それたことを言おうと思ったわけではなく、このままでは時代の流れがなんとなく戦争のほうへ行っちゃうんじゃないかという感じがして、実際に戦争の時代を生きた人間がどう考えていたのかを書いておこうと思ったんですね。戦争を知っている世代がだんだんと少なくなっていますから。
例えば、ぼくは今、模型飛行機を集めているんですけど、若い人にB29の模型を見せてもB29がどういう飛行機か知らないんです。ぼくは陸軍幼年学校時代にB29の空襲を受けましたけど、今の人に空襲の話をしてもピンとこない。まあ、しようがないことではありますけれど、そうした記憶そのものがなくなってしまうのは、やはり困りますね。
少なくとも、ぼくの実感では、戦争が終わってすぐの頃は、もう二度と戦争はイヤだという雰囲気が非常に強くあって、それがかなり長いあいだ続いていた。それがいつの間にか、戦争はイヤだけど、万が一の時には戦争も仕方ない…といったような雰囲気になってきて、おまけに戦争をした日本は正しかったなんていう意見も出始めてきた。
とにかく、そっちの方向へ行ってはまずいので、ただ戦争はいけないといっているだけではなく、なぜ戦争がいけないのかをきちんと書いておこうと思ったわけです。
「この世の中は火と水しかない」70年以上経ってもなぜかその言葉を覚えている
─第二章の「私の戦後」では、昭和20年の8月15日以降に起こった様々な出来事が当時の新聞などを引用されつつ、詳しく書かれています。あらためて振り返ってみて、いかがでしたか。
西村 とにかく、あの8月から翌年の春までは忙しかったですね。何しろ日本中が飢えていて、配給だけではとても足りないから、食糧の買い出しに行かなくてはいけない。ぼくもリュックサックを背負って、親父と一緒に農家へ買い出しに行くわけですよ。それでも、お米みたいな高いものは売ってくれないから、大抵はサツマイモを買ってくる。
だけどそれは闇取引、つまり非合法なわけだから、途中で検問しているお巡りさんに捕まったら取り上げられてしまう。といって、持って帰らないと家族が飢え死にしてしまいますからね。だから、検問があるという情報が入ると、捕まらないように、サツマイモの入った重い袋を担いで必死に逃げ回る。あれは忘れられないですね。
それから、早く学校に行きたかったのだけれど、旧制中学の3年生に戻れたのは翌年の4月になってからです。ようやく授業が始まったのはいいのですが、敗戦で自信を失った教師たちは何をどう教えたらいいかわからなかったのでしょう、やたらと自習が多かった。もっともこちらも相変わらず頭を占めていたのは食べ物のことでしたけどね。
あと、よく覚えているのはアルバイトですね。友人と一緒に学校の近くの町工場で電球を作っていました。面白いのは、若い人はみんな兵隊にとられてしまって、まだ戦地から戻っていない人も多かったので、働いているのはおじいさんばかりなんです。で、そのおじいさんのひとりが、「この世の中は火と水しかない」といったんです。どういう意味なのかいまだにわからないんだけれど、70年以上経ってもなぜかその言葉を覚えている。不思議ですね。
で、ぼくらの仕事というのは、その電球にゴム印を押すことなんですけど、それが当時の有名なメーカーの名前で、今から考えると、そのメーカーのニセモノの電球を作っていたんですね。なんだか全てがうさん臭い時代でした。
─将来に対する不安のようなものはなかったのですか。
西村 なかったですね。まだ子どもでしたからね。大人たちは、戦争に負けてどうなるかという心配はあったと思いますけど。とにかく嬉しいんですよ。
─嬉しい?
西村 要するに、もう空襲がないから夜中に逃げ回らなくてもいいし、夜、電灯をつけても怒られない。戦争中は敵機に見つからないように電灯に覆いをかぶせて、うっかり光が漏れていたりすると、「おまえのところ、漏れてるぞ」とか言われましたからね。お腹は空(す)いているんだけれど、夜、ちゃんと眠れたのは嬉しかった。
日本の将校は「桶狭間の戦い」が好きなんです
─第三章は、「日本人は戦争に向いていない」と題して、戦争中の日本軍の「玉砕」を良しとする前近代的な精神主義や根性主義を詳細に分析して、日本人が全面的な総力戦となる近代の戦争にいかに向いていないか、そしてその精神構造がどこからきているのかを書かれています。
西村 日本人は戦争に向いていないし、そもそも戦争が好きじゃないんだと思うんです。ところが、上のほうから何か言われると、いやいやながらも黙ってついていってしまうところがある。そこが怖いところですね。
よく日本はタテ社会だといわれますが、日本の社会には、ある集団ができると、どこか親分─子分のような関係を作ってしまうところが抜きがたくあるんですね。例えば、戦争に負けて、フィリピンにいた兵隊たちが捕虜になる。すると、戦争が終わって、本来軍隊時代の階級なんかなくなったはずなのに、いまだ軍隊時代の上下関係が生きていて、自然と親分─子分という形ができてしまう。
だから、たとえ親分が食糧をひとり占めにしたとしても、子分は何もいえないし、親分から理不尽なことを押しつけられても、黙って従ってしまう。
─参謀本部内にも、永田鉄山のような優れた国際感覚を持っている人がいたけれども、その永田が暗殺されたことで、そういう路線が閉ざされてしまった、とあります。
西村 日本では、冷静で理論的な人はなかなか上に立てないんです。むしろ、豪快な親分肌で、子分が間違っても笑って許す、陸大(陸軍大学)出でも、そういう人が上に行けたんです。
それから本にも書きましたが、日本の将校は「桶狭間の戦い」が好きなんです。織田信長が、わずか3千の兵で4万の兵を擁する今川義元に勝ったという。要するに、日本はずっと貧しい国だったので、ああいう、奇襲によって小さい者が大きい者に勝つという戦いを理想としたわけです。しかし、戦国時代ならいざ知らず、戦車や飛行機が活躍する近代戦にそんなものが通用するわけがない。
そこにあるのはなんとも非合理な精神主義です。有名な話ですが、東條英機が参謀総長だった時に、学生に向かって「敵の飛行機が現れたら、どうやって落とすか?」と質問をして、「戦闘機で向かって行き、機関銃で落とします」と学生が答えたら、東條が怒って、「それでは駄目だ。精神で落とすんだ」と叱ったという。信じられないですよね。あの人だって陸大を出ているし、関東軍にもいたんですから。そういう人がトップにいて戦争をしたわけですから、勝てるはずがない。
◆この続き、後編は明日配信予定!
●『十五歳の戦争 陸軍幼年学校「最後の生徒」』(集英社新書 本体760円+税)
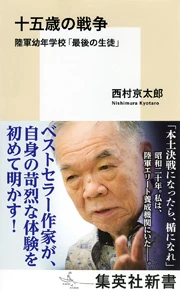
(取材・構成/「青春と読書」編集部 撮影/chihiro.)