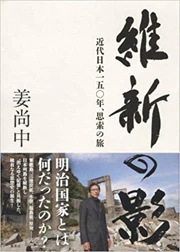『維新の影──近代日本一五〇年、思索の旅』の著者・姜尚中氏
『維新の影──近代日本一五〇年、思索の旅』の著者・姜尚中氏
2月1日、ジュンク堂書店池袋本店において、姜尚中(カン・サンジュン)氏の新刊『維新の影──近代日本一五〇年、思索の旅』刊行の講演会が開催された。
同書は、近代日本を支えてきたエネルギー産業の基幹であった端島炭鉱(通称・軍艦島)をはじめ、過疎と高齢化に見舞われる熊本県球磨村、大震災直後の熊本、3.11から時間が経った福島第一原子力発電所など各地を巡り、この国の繁栄の歴史とその負の側面とを振り返った「思索の旅」の記録である。
この本に込められた姜氏の願いとはどのようなものなのか。「思索の旅」を通じてどのような思いを抱くようになったのか。満員の中、行なわれた講演会での内容をダイジェストでお送りする。
* * *
本日はイベントにお集まりいただき、ありがとうございます。この『維新の影』という本は、共同通信社配信の連載を元に書籍化したものです。当初の新聞掲載時には「姜尚中 思索の旅『1968~』」という題を付けていただいたのですが、それを明治維新からちょうど150年にあたる2018年という節目に書籍という形でまとめて、日本の近代の歩みを振り返ろうとしたものです。
明治維新から150年という名目で、様々な形で一種の翼賛的な動きが出てくるだろうと予想されます。しかし、物事には光があれば必ず影もある。歴史の光の側面にばかり目を向けていてはいけない、という問題意識が私の中には強く横たわっています。
ちょうど刊行と前後して、本書と類似した問題関心から書かれた本があります。1月に岩波新書から科学史家の山本義隆さんが出した『近代日本一五〇年 科学技術総力戦体制の破綻』というタイトルの本です。山本さんといえば1969年の全国全学共闘連合で議長を務め、その後、大学を去り下野してしまったことで有名ですが、彼は科学史の立場で、そして私は政治や社会の視点からと違いはあるものの、奇しくも同じようなことを同じタイミングで書いているわけですね。
共通しているのは、この150年来、無限の前進運動としてやってきた「エネルギーをがぶ飲みする」ような文明が、日本の人口減少と福島第一原発の事故で限界に突き当たっているのではないかという見立てです。そんな文明のあり方はもう終わりを迎えているのだけれども、代わりのものが打ち出せていない。そういう日本の行き詰まりを見つめて、150年前に遡(さかのぼ)る形でそれぞれが歴史を読み解いているということになります。
私自身、残念ながら解決策を示せるような学識はありません。ただ、やはり明治維新から150年の歴史をどのような形で受け止めるかによって、また同じ悲劇が繰り返されてしまうのか、あるいはここでしっかりとピリオドを打って、いわば「ポスト明治」の方向に日本の社会が動いていけるのかが決まってくるのではないかという思いが根底にあります。
■日本という国家は「民」を恐れてこなかった
私が取材を続け、日本の近代を振り返る中で痛切に感じたふたつのことがあります。そのひとつは、どうして日本という国は「民」を恐れないのだろうかということ。『維新の影』でも言及したのですが、国家を操舵する人々が官僚であれ、政治家であれ、民を恐れていないように思える。これは今もそうなんじゃないかな。
例えば、『維新の影』では奇しくも優生保護法の問題を扱っています。つい最近、宮城県内の女性が「不良な子孫の出生防止」を目的として不妊・避妊手術を強制した「旧・優生保護法」に対して裁判を起こしたことがニュースになりましたね。この法律はなんと1996年まで続いており、そのために様々な不妊手術や断種が行なわれたとされています。日本全体では手術を強制された人数は約1万6千人とも言われます。
「旧・優生保護法」はひとつの事例ですが、取材を通して感じたことは、この150年の中でいろいろ起きている問題が、なぜかくも長く、ずっと引き延ばされてきたんだろうかと。公害の問題ひとつをとっても、例えば足尾銅山の問題は今も影を落とし続けている。2018年の現在でも、洪水などがあると有害物質が垂れ流しになるという状況はそのままです。
他にも、水俣病の問題もあればハンセン病の問題もあります。優生保護法と密接に関わってくる問題ですね。こうした問題が50年、100年という単位でずっと解決されず先送りされているということは、国は民のことを軽く考えている、つまり国家は民を恐れていないのではと考えざるを得ない。民主主義は民が統治者のはずであり、民の代表者は民を恐れなければならないのにそうはなっていない。今も、そして過去もそうだったとしか思えません。
日本の近代を振り返る中で痛切に感じたふたつのこと

同じことは東日本大震災と福島第一原発についても言えるのではないでしょうか。あれだけの黙示録的な出来事が起きていながら、今はどうなっているのかということはなかなか知りがたいですね。
これらの事実を見るにつけ、山本義隆さんの言葉を借りれば、「なにゆえにこれほどまでにも科学技術へのオプティミズム(楽観主義)が無くならないのか」ということになるでしょうか。山本さんの場合は、仁科芳雄という人物に注目しています。仁科は戦時中に原爆の開発に取り組んでいたとされる人物ですが、結局は広島・長崎に原爆が投下されてしまった。ところが、それを逆手に取って「だからこそ日本は原子力に励む資格がある」という論理を生み出してしまった。
このような論理が継承されたからこそ、この国には科学技術というものに対する根本的な懐疑が生まれなかった。だから、その後も日本では、科学技術は無から有をつくるぐらいの生産力に通じているという、ヨーロッパで歴史的に生まれていた科学技術に対する様々な懐疑や、あるいは原理的な考察とは別の能天気なほどのオプティミズムがずっと残るという結果になったわけです。
科学は、近代日本において常にフロントランナーの位置にありました。しかし今、こんなことを語っている私自身も、振り返れば科学というものに対して楽観論を抜け出し得ていなかったのではないか。そのことを痛感したのが、震災の直後に割と早い段階で相馬市に足を運んだ時のことです。そこで、南相馬から逃れてきた主婦から「なんで東京のために私たち、こんな犠牲を払わなきゃいかんのですか!」って、食ってかかられたんですね。その時に、もう言葉がなくて…。
考えてみると、私は九州の田舎で生まれて、やっぱり東京の明るさを目指して。蛾が街灯に引き寄せられるように、熊本の駅裏の暗いところよりは東京に行きたいという思いで出てきて、どちらかっていうと「光」の部分に甘んじていた。それが福島第一原発の事故で完全に吹き飛ばされたところに連載のお話があって、取材をやってもいいかなという思いが芽生えたのだと思います。
『維新の影』の第一章はエネルギーに関する話題で始まります。軍艦島をはじめ、三池炭鉱や福島第一原発など日本の近代を支えた化石燃料や原子力に関わる場所を順番に訪れたのですが、「まずは、エネルギーに関わる場所から行こう」という直感が働いた背景には、振り返ればこうした動機があったのかも知れません。
◆後編⇒姜尚中が思索の旅で振り返った近代日本の“冷たさ”と“恐れ知らず”…「残念なことに、知識人の活動が弱まっている」