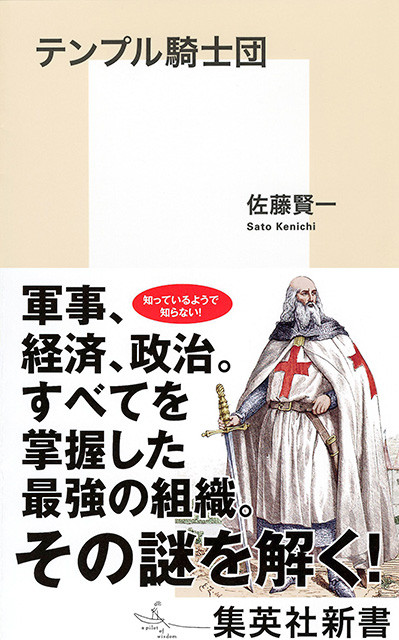『テンプル騎士団』の著者である佐藤賢一氏
『テンプル騎士団』の著者である佐藤賢一氏
12世紀初頭からおよそ200年にわたり、十字軍として活動したテンプル騎士団。ローマ教皇の認可を受け、キリスト教の聖地エルサレムを守るために修道士となった騎士たちの伝説は、『ダヴィンチ・コード』などの小説や映画作品にしばしば登場するが、そのわりに実態は多くの謎に包まれていた。
このたび、ていねいに資料を当たり、テンプル騎士団の史実を明確に記してくれたのが佐藤賢一氏だ。『テンプル騎士団』(集英社新書刊)に描かれたその姿は、ヨーロッパ初の常備軍であると同時に、時代を先取りしたビジネスを次々と成功させたスーパー集団でもあった。
―イントロでテンプル騎士団の巨大なスケールに度肝を抜かれ、次いでその突然の終焉がつづられて呆然とし、「テンプル騎士団とは何か」の説明に入ると『スター・ウォーズ』が引き合いにだされてまたびっくり。ぐいぐい引き込まれましたが、「ジェダイの騎士」のモデルは「テンプル騎士団」だと、いつから思っていらしたんですか?
「最初に『スター・ウォーズ』を見たときに、すごく違和感があったんです。悪の皇帝ダーク・シディアスが修道士のような服を着ていて、なぜ皇帝なのにこんな服装をしているのかと。片や主人公のルーク・スカイウォーカーはジェダイ騎士団に属していますが、これもなぜ銀河の物語なのに中世ヨーロッパを思わせる求道的な"騎士"なのかが不思議で。
そのことがずっと心に引っかかっていたんですが、テンプル騎士団を敵対視したフランスのフィリップ四世が、王でありながら普段は修道服を着ていたことを知って、シディアスとジェダイの騎士はフィリップ四世とテンプル騎士団ではないかと思いついた。そう思って比較すると、ジェダイ評議会の長もテンプル騎士団の総長も英語では同じグランドマスターだったり、ジェダイの評議会はジェダイ・テンプルに置かれていたり、よく似ているんです」
―テンプル騎士団には、隠された財宝とか実存する結社とのかかわりとか、伝説や陰謀説がかなりあるそうですね。
「結成直後、エルサレムのソロモン宮殿で寝泊まりしていたときに発見した財宝がどこかに隠されている、と信じて実際に探している人が今もいます。その財宝がアメリカ大陸に運ばれ、アメリカ合衆国建国の資金になったという説もあれば、フリーメイソンの原初のメンバーがテンプル騎士団だったという説も、ヨーロッパではまだ根強い。
海賊になったという説もあって、これは海賊旗のマークが根拠とされています。髑髏の下に大腿骨が交差している図柄は、エルサレムの地下墳墓で見られた埋葬方法を表したもので、エルサレムにいたテンプル騎士団が海賊になってあの旗をつくったと。ほかにもテンプル騎士団には数多くの伝説や陰謀説があって、ヨーロッパやアメリカではトンデモ系のメインストリームにもなっているんです(笑)」
―欧米人にとって、テンプル騎士団はそれだけ関心が高いということでしょうか?
「そうですね。ヨーロッパ人、アメリカ人で歴史の素養がある人は、テンプル騎士団を『精神性も加味した正義の集団』というイメージでとらえていると思います。暴君とか専制君主と呼ばれる支配者が登場すると、それを倒すヒーローとしてテンプル騎士団を思い出したりするようです」
―今回、小説ではなくノンフィクションとしてテンプル騎士団を描かれましたが、歴史を小説で語るかノンフィクションにするか、どこで線引きされるのですか?
「こんなこと、この時代、この場所でしかあり得ない、という特異性を見つけたら、ノンフィクションで書こうと判断します。テンプル騎士団はその典型でした。歴史というのは基本的に『驚き』がないと意味がない。驚きがない歴史の本は、歴史を書いているのではなく、過去の事実を書いているだけだと思います。
僕も含めて現代に生きている人がなにかに悩んだとき、ほとんどは「今の時代の枠組み」「今の常識」のなかで悩んでいるわけですよね。でも、今とは違う世界、違う枠組みがあると知れば、考える座標軸が広がり、自分がいかに小さなことで悩んでいたかに気づいて、心も広がっていくと思う。これが歴史に驚き、歴史に学ぶことです」

―テンプル騎士団の特異性には、ご自身も驚かれましたか?
「はい。まず騎士でありながら修道士で、十字架をつけて戦いに行くこと自体が不思議だし、その組織がヨーロッパ初の常備軍になっただけでなく、ヨーロッパ一の主要な土地を購入して大地主となった。各地の修道院を城塞化し、農場でつくった作物で自給自足したり、作物を売って現金を戦場へ送る。
さらには船を調達して巡礼旅を組織化し、巡礼をエルサレムまで送ったあとは、現地で物を買って船に積んでくる。旅行業も貿易も営んで、さらには庶民から王侯貴族までを相手に金融業も始め、ヨーロッパ初の銀行をつくってしまった。テンプル騎士団は驚きに満ちあふれています」
―歴史小説やノンフィクションを書きながら、佐藤さんはいつも現代と比較する視点をお持ちです。今回のテンプル騎士団と比較する対象は?
「強いていえば、IS(イスラム国)が若干近いですね。ただ、一部の過激派だけが参加したISは、宗教的な価値観を共有するパイが小さかったので巨大化はしませんでした。テンプル騎士団は、ローマ教皇が「十字軍に加われば罪が帳消しになる」と戦争参加を後押ししたのですから、パイが巨大ですよね」
―テンプル騎士団の時代は、宗教的な熱狂が頂点に達した時代でもあったのですね。
「そうですね、中世ヨーロッパは自分が予想していたよりもはるかに宗教的な熱狂に包まれていました。とくにフランス人はカァ~と熱くなりやすいのですが、感情だけで動くわけでなく、そこに合理性もミックスされている。だからひじょうに人間らしいドラマがたくさんあって、ヨーロッパのなかでもフランスは魅力的なんです」
―それにしても、テンプル騎士団はなぜあんなに強大な存在になり得たんでしょう?
「そこも不思議ですが、一つは優秀な人材を上の地位にどんどんあげていったこともあるでしょうね。これも当時のヨーロッパでは常識外のことでした。騎士にも格があって、才覚があっても父の地位より上には行けないし、家督を継ぐのは長男と決まっていた。それを破って実力主義を敷いたテンプル騎士団に、優秀な次男、三男が集まったのだと思います。
―フィリップ四世によって壊滅させられた時点で、テンプル騎士団はISのように独自の国づくりを目論んでいたと思われますか?
「いや、僕は意外になにも考えていなかったという気がしています。上に立って全体を見ている人が、それほど先見の明をもっていたわけではなかったと。むしろ先を考えていたのはフィリップ四世のほうで、王家を凌ぐほど巨大化したテンプル騎士団を警戒し、危機感を抱き、ついには「異端」の罪を着せてつぶしにかかった。信じられないほど一斉に、徹底的につぶしました。逆に言えば、テンプル騎士団側は、それほど油断していたのでしょう。
―文中、佐藤さんが「国際金融機関がアメリカ軍をもっていたようなもの」と表現した組織の、あまりにもあっけない幕切れ。伝説、陰謀説が多数生まれるわけですね。ところで、歴史を調べていく過程で人物が語りかけてくる、と以前どこかで発言されていましたが、今回も誰かが語りかけてきましたか?
「まあ200年という歴史で大勢が登場しますから、何回かはそんなこともあったような(笑)。いろいろな局面で、これは小説になるかな、と思うこともありました。僕が興味を抱くのは、等身大の人ですね。テンプル騎士団でいえば、偉い人ではなく無名の騎士を主人公にした小説もいいかなと思ったり・・・」
―今のご発言で、大勢の読者がテンプル騎士団の小説化も期待したと思います。
「あっ、いや、まだ構想もなにもないですけどね(笑)」