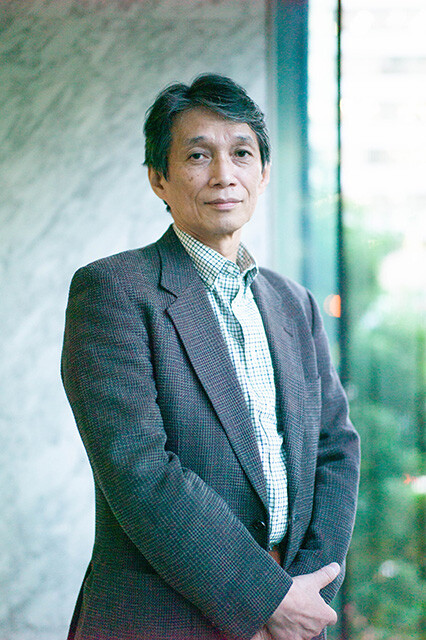
累計118万部の人気シリーズ最新作が刊行、『救命センター カンファレンス・ノート』の作者・浜辺祐一氏は、都立墨東病院救命センターの現役部長。臨場感溢れる描写は秀逸で、2作目ではエッセイスト・クラブ賞も受賞している。医療エンタメとして楽しめる一方で、登場人物のやりとりからは社会の在り方も問われ、ある種、禅問答の様相すらはらむ。36年間、死と隣り合わせの最前線に身を置き、来年3月に定年を迎える浜辺氏に、救命救急医療の現状からコロナ禍がもたらしたものまでお話しいただいた。
■救命センターは役割を終えた!?
――24時間365日、流血、心肺停止、昏睡......といった患者を救うミッションを背負った過酷な現場に36年とは、よく正気を保っていらっしゃるなと!
浜辺 ホントだよ(笑)。
――高度経済成長期には外傷患者が中心だったのが、バブル後は働き盛りの成人病に替わり、今は患者の平均年齢が70代半ばと高齢化が進み、救命センターはまさに時代の写し鏡です。まずは改めて、その役割とは?
浜辺 うーん、難しいんだよね......。30数年前だったらスッと答えられたんですよ。でも救命センターにも50年近い歴史があって、運営形態も今はずいぶん変わってきているのでね。
世代的なことでいえば、第1世代は何もないところから救命センターを作った草分け的な世代。それは我々よりも遥かに上で、僕は第3世代あたりなのかな。今は第5世代、第6世代みたいな時代ですよ。総本山の「日本救急医学会」でもオピニオンリーダーはすでに下の世代になっているわけで。
つまり、救命センターそのものに対する捉え方も大きく変わってきてるし、極端な言い方をすると、ひょっとしたらもう時代的には役割が終わりつつあるのかなという......。
――役割を終えたというのは、どういう面で?
浜辺 救命センターを立ち上げた頃は、大学の中に「外科」や「内科」、「脳外科」や「整形外科」などに並んで「救急科」というものを確立したいというのがあってね。当時、救急は医学の中で1ランク2ランク下の扱いを受けていたわけです。まあ今でも多分にそういうところはあって、遺伝子とか癌とかといった最先端医療、要は「専門家」が注目されていた時代で、救急というのはそんなものとは全く違った世界でしたよ。
――ただ、高度な専門医療を総合的に実施できるのは、救急しかないですよね。
浜辺 そうなんです、それをいかに実際的に組み合わせて現実的なことをするかっていうのが、救急医療の本質で、それを救命センターという場でずっとやってきたつもりなんだけど、社会が少しずつ変わり、今やっていることを続けるのが果たしていいのか、あるいは「続けられるのか」っていう思いがあって......。
今は例の「働き方改革」ってのがあるじゃない? 実は、管理者の立場から言うと、無茶な当直業務もやらせなきゃ現場が回らないんですよ。でもそれだと今はお叱りを受ける。「じゃあどうすんだよ」っていう感じなんです。
僕が今いる都立病院は、このまま行けば来年の半ばから「独立行政法人」化するわけですが、そうすると、行政医療をやらなければならないことは変わらないんだけど、当然「経営効率」という本音が出てくるわけなんですよ。

――でも、命が助かるかの瀬戸際で、採算なんて考えてられないですよね。
浜辺 そうなんですよ、少ない経費で多くの成果を上げるという考え方ではなく、むしろ効率なんかとは無縁のところで、もっと人手をかけて、無駄を承知でセーフティネットを敷くみたいなのが、救急医療の原理原則なんだと思うんだよね、。
――法人化に進むと、真逆の方向にいく危惧があると......。
浜辺 幸か不幸か、私は来年の3月で都立病院を"卒業"なんで、関与しなくて済むのは「ラッキー」っていうか(笑)、まぁそれは冗談だけど。ただ、まさか自分が30数年も同じ職場でやることになろうとは露(つゆ)ほども思わなかったわけで、もし何か理由があったとすると、そこが都立病院だったということがあると思うんですよ。
救急の現場って、私立大学や民間の医療機関が担わなきゃいけなくなると、経営的なことからどうしてもないがしろにされやすくて......。でも都立というのは、ケンカができるんです。「行政は救急医療をなんだと思ってんだ!」っていうようなことを正面切って言えたんでね。
――発言して問題提起できる土壌があったと。
浜辺 うん。これが民間病院だったら「イヤだったら辞めてもらっていいんだよ」って、それで終わっちゃうわけですよ(苦笑)。
■悪名は無名に勝る
――作中では、そういった現場の熱意や思いをくじくような制度も描かれますが、そんなジレンマとはどう付き合ってきたのですか?
浜辺 それはさっき言ったように、行政のところだから"ワガママ"が言えるわけです(笑)。まぁその発端みたいなものは、30数年前に救命センターを一緒に始めた先輩の教えで、それは「常に戦う」ということだったんですよ。どんな時も、ファイティングポーズを取り続けるんだということを叩き込まれたというかな。
その先輩の口癖は「悪名は無名に勝る」。そこに問題を作るというか、問題を見つけることで波風を立てていくっていうのかな。一般的には「問題児」って言われるような行動だけれども、そうではなくて、隠れている問題点を表に出していくということですよ。当時はそういうことが必要でね。
――救命センターが整備される過程には、その先輩や若き浜辺医師らの戦いがあったと。確かにそういう問題提起がないと変わらないですよね。
浜辺 だと思いますよ。現状維持でうまくいっても、さらにいいものにするためには何か問題点を見つけていかなきゃいけないわけで。
あとね、今から思うと、自分のレゾンデートルっていうか、存在意義とかの部分で、プラス100点じゃなくて、たとえマイナス100点を取ってでも「どうだ、俺はここにいるんだ」って知らしめたいというのもあったんだろうなと。上司や周囲からすると、鬱陶(うっとう)しくてしょうがないっていう存在だったとは思うんだけど(笑)。

――悪名高いというか、反抗心的な(笑)。そういう意味では、最近でも今夏のパラリンピック開催時、競技会場で重傷者や病人が発生した際に救急搬送を受け入れてほしいという組織委員会の要請を、墨東病院が断ったというニュースもありました。
浜辺 あれは、むしろパラリンピック委員会のほうが困ってると思ったんですよ。開催直前にそんな要請を出すってことは、とてもじゃないけど安全に開催できないから本当は延期・中止したいというのが本音であって、それを自分たちではもう言えなくなってるんだろうなって。だから、困ってるなら問題にしましょうよって。むしろ良かれと思ってね。
――代弁した感覚だったんですね。
浜辺 そうそう、だから意外だったんですよ、みんなが「よくぞ言った」と言ってくれてね。
■コロナが炙り出したもの
――実際、感染症指定医療機関でもあり、コロナ対応を優先するだけで手いっぱいの状況であったわけですよね?
浜辺 一時期はコロナの入院患者さんが150人とかですか。それこそ都知事から「とにかくコロナ用のベッド数を増やせ」というようなことを言われてやってましたよ。
――まさに逼迫した現場で、滅菌ガウン、手袋、帽子にゴーグルという防護具を装着し、重装備で医療にあたっている日常が続き......。
浜辺 変な話、「コロナ」って旗を立てて来てくれたら別に怖くないんですよ、コロナとして対応すればいいだけなので。でも救命センターってところは、一見、健康なドライバーとか歩行者が事故で運び込まれて、まさかと思って検査したら、ええっ!?っていうことがあるので。だから最悪のことを考えると重装備になっちゃって......。
――「患者を見たら、コロナを疑え」とも本の中にありましたが。
浜辺 最悪を想定して準備をしておけばいいのだけれど、そこで手を抜くと、スタッフに感染しちゃって、スタッフが倒れるならまだしも、そこから入院患者さんにうつるのが一番困るんで。当然、濃厚接触者に認定されたりPCR検査に引っかかると、本人はなんともなくても「職場に来るな」ということになる。
――貴重な人員がさらに......。
浜辺 そうそう。だからいろんな医療機関が、おそらくマンパワーが確保できなくなって、受け入れを制限したりしたはずなんです。でもコロナの時期ってね、実は、救急の患者さん自体は3分の1ぐらい減ったんですよ。だから、今までの救急患者さんって、一体なんだったの?っていう(笑)。
――必然性の低い患者まで運ばれて(笑)。あと外出もしないので外傷も減ったのでは?
浜辺 それはありますよ。緊急事態宣言が解除された途端に酔っ払って頭をぶつけたというのがたくさん来ましたからね(笑)。
去年はインフルエンザなんかほとんど出なかったわけだし、小児科なんて、それまで救急外来にいっぱい来ていたのがピタッと止まりましたから。病院側から言わせると、売上が減っちゃったとかがあるとは思うけれども(笑)。だから、実際問題として病気っていうのは医療側が作り出している部分もあったのではないかという意を強くしましたね。
今言ったような意味で、コロナがいろんなことを炙(あぶ)り出してくれたというか、隠れたものを明らかにしてくれたところは間違いなくあるよね。

――公立の病院が受け入れざるを得ないとか、対比して日本医師会が代表する民間病院系の方針、運営に関して今まで突っ込まれなかった部分も問題視されたり......。
浜辺 僕も医者仲間だから、医師会のことをあまりとやかく言える立場じゃないんだけれど(笑)。例えば、コロナ補助金をもらっても直接的な医療に使わなかったとか、もちろんだまし取ったわけではないんだけど、そういう補助金行政の弊害みたいなものも話題になったよね。
こんな時期にオリンピックを強行することの是非とか、結果はともかくとして、対応力と言えばいいのかな、日本の本当の力みたいなものが白日の下に晒(さら)されちゃったみたいな。まさしくコロナが、普段行なわれていることの功罪を炙り出し、突きつけた部分はあると思う。
ただ、「早く元に戻りたい」と皆さん仰るんだけど、元に戻れるのかなぁという感じがありますね。おそらく再検討をして元に戻るというのもひとつの選択肢だけれど、そうではなくて、まさに「災い転じて福となす」みたいな、新たなステージに移るようにしなきゃいけないのかなという気がします。
――そこで浮き彫りになった現場の疲弊や、ずっと問題視されていた地方医療もそうですし、偏った受け皿として悲鳴を上げ続けてきたギリギリのターニングポイントなのかと。
浜辺 医療そのものをもう一度考え直す、いいきっかけでしょうね。それこそ、少子高齢化に向かっていく日本で、価値観の再構築みたいなものなのかな、と。
■浜辺祐一(はまべ・ゆういち)
1957年、兵庫県生まれ。東京大学医学部卒業。東大病院救急部、国立水戸病院外科を経て、85年から救命救急センター開設と同時に都立墨東病院へ。現在、救命救急センター部長。99年『救命センターからの手紙 ドクター・ファイルから』で第四七回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。
 ■『救命センター カンファレンス・ノート』
■『救命センター カンファレンス・ノート』
患者の高齢化、急増する収容要請、緊迫の新型コロナ対応……現役医師が描く救命救急のリアル――累計118万部突破のシリーズ最新刊!