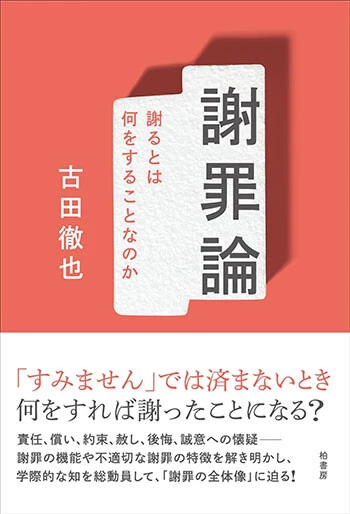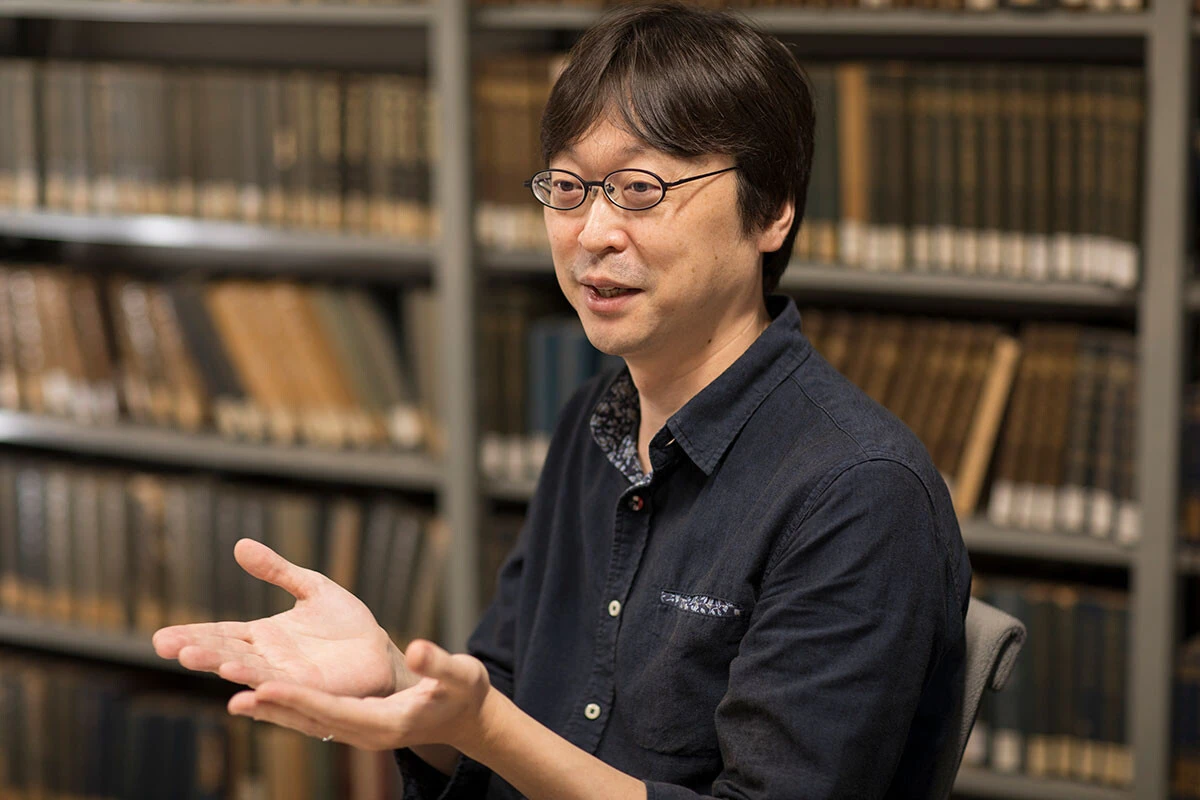 「謝罪をマニュアル化する取り組みもありますが、それではあまり意味がないと思います。技術的に『うまい』と感じさせる謝罪であればあるほど、そこには誠意を認めにくくなりますから」と語る古田徹也氏
「謝罪をマニュアル化する取り組みもありますが、それではあまり意味がないと思います。技術的に『うまい』と感じさせる謝罪であればあるほど、そこには誠意を認めにくくなりますから」と語る古田徹也氏
個人間での小さな過失や大きな事故、芸能人の不倫、企業ぐるみの不祥事、チームの成績不振など、毎日どこかで大小さまざまな「謝罪」が行なわれている。
企業や著名人の謝罪会見があれば、誰もがその良しあしを語りたくなってしまうほど、私たちは謝罪という行為をよく目の当たりにする。しかし、いざ自分が謝罪する側になると、そのタイミングや言葉の選び方に頭を悩ませ、失敗してしまうことも。
知っているはずなのによくわからない、そんな「謝罪」を哲学や倫理学の知見を基に解きほぐして『謝罪論 謝るとは何をすることなのか』にまとめたのが、東京大学大学院の古田徹也准教授だ。
* * *
――なぜ「謝罪」に関心を?
古田 誰にとってもすごく身近な行為なのに、私も含めて誰もが失敗するという点に強く興味を持ちました。自転車の乗り方であれば、ひとたび身につけてしまえば、まったく乗れなくなることはないですよね。でも謝罪は、慣れているはずなのに失敗します。
多くの人は「すいません」という言葉を日に何度も口にしているでしょうし、コロナで会社を休んだり、電車の遅延で約束に遅れたりといった、不必要にも思えるような謝罪を行なうこともしばしばあります。
謝罪はこんなに身近なのに、しかるべきタイミングで謝れなかったり、準備したはずの重大な謝罪で失敗したりする。このとらえ難さはどこから来るのかと、ずっと考えていたんです。
――大学の講義では、不祥事を起こした企業の謝罪会見を見比べて、どこが問題か学生と話し合ったことがあるそうですね。
古田 集めてみると、題材には事欠かないことがよくわかりました(笑)。企業倫理に関わる講義をしていた16年ほど前のことですが、「ささやき女将」で有名になった船場(せんば)吉兆の謝罪会見など、正直言って失敗例はいくらでも見つかるんです。しかし、成功例はめったにない。
――希少な成功例の代表格は?
古田 印象に残っているのは、ジャパネットたかたの髙田明社長(当時)の会見です。
――2004年に起きた大規模な顧客情報流出についての謝罪ですね。発覚後すぐに会見し、原因究明まで49日間にわたって営業停止、実に150億円もの減収が発生したとされています。
古田 髙田社長はまず自らの責任を認め、現時点でわかっていることとわかっていないことを整理して伝えました。そして、その時点で言えないことがあれば言えない理由についても、丁寧に説明責任を果たし続けました。
自分たちを正当化することもなく、どう責任を取り、今後どういう対策をするのかも明確に約束しています。結果として、ジャパネットたかたへの信頼はむしろ高まって、業績も事件以前よりも伸びています。
問題の矮小(わいしょう)化や騒動の幕引きを図ったのではなく、責任を果たそうという意思をメディアも視聴者も感じ取ったのだと思います。
より最近の見事な例は、むしろ「謝罪しなかった」事例です。スープストックトーキョーが、今年4月から店舗での離乳食の無料提供を始めたところ、SNSには「狭い店内がベビーカーでさらに狭くなる」「泣き声や奇声でくつろげなくなる」といった投稿が相次ぎ、いわゆる「炎上」状態になりました。
それに対して同社は、この施策が「世の中の体温をあげる」という企業理念の下で行なわれた「食のバリアフリー化」の一環であることを示し、取り組みの全体像を説明する声明文をホームページに掲げました。
この声明では「お騒がせして申し訳ありません」や「配慮が足らず一部のお客さまに不快な思いをさせてしまい」といった定型的な謝罪すらも、一切行なっていません。
――とりあえず騒ぎを収束させる目的であれば、「お騒がせして申し訳ありません」と謝って、いったん取り組みを中止してしまいそうです。
古田 ええ、それが今の風潮ですよね。「とりあえず謝る」ことへの誘惑や圧力は強かったと思いますが、理念に沿った取り組みであることを説明し、企業として目指す姿を明確に示しました。「謝るべきではないことは謝らない」という対応が、企業理念を伝える非常に強いメッセージとなった、稀有(けう)な例だと思います。
――この本を読むと、「謝罪」の意味や機能にはいくつもの要素が複雑に重なり合っていて、ひと言で定義することの難しさがひしひしと伝わってきます。それでも誰もが「あの謝り方には誠意が感じられない」などと直感的に理解できるのは、驚異的なことなのではないかとも思います。
特に印象的だったのが、謝罪は「する側とされる側のコミュニケーションの起点となりうる」という指摘です。ふたつの成功例はいずれも、「これから顧客とのコミュニケーションを強めていく」意志を示しています。
一方で、多くの失敗例は騒動の幕引きを図る謝罪に、つまりはコミュニケーションの終了を宣言するメッセージになってしまっていますね。
古田 そのとおりです。最近では謝罪動画の投稿もよく見られますが、多くは一方通行の発信に終始し、被害者とのコミュニケーションを図る意思が弱く映ります。
また、重大な謝罪を行なう際には、加害者が被害者になんらかの形で「謝罪する許可」をもらう必要があります。それもなしに動画だけ投稿するというのは、被害者に「赦(ゆる)し」を強要するような、暴力的な行為にもなりえます。
――謝罪の「実践的なヒント」を巻末に挙げたのは、最初に「正解」に飛びついてほしくないという思いからでしょうか。
古田 そうなんです。最近では危機管理マネジメントの一環として、謝罪をマニュアル化する取り組みもありますが、それではあまり意味がないと思います。技術的に「うまい」と感じさせる謝罪であればあるほど、そこには誠意を認めにくくなりますから。
ヒントのひとつとして「定型的な表現に頼り切らない」を挙げました。これはマニュアルというよりも、むしろ脱マニュアルの提案です。「誤解を与えたとしたら~」「ご迷惑をおかけして~」といった紋切り型に頼らず、起きてしまった問題の認識や今後の取るべき行動を、自らの言葉で語る努力をすることで、なんらかの「誠意」が伝わると思うんです。
――礼儀や型は必要だが、それらは謝罪の本質ではない、と。
古田 はい。私自身も謝罪がへたな人間のひとりです。だからこそ謝罪の難しさ、とらえ難さと真摯(しんし)に向き合うことが、大事なのだと思っています。
■古田徹也(ふるた・てつや)
1979年生まれ、熊本県出身。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(倫理学)。新潟大学人文社会・教育科学系准教授、専修大学文学部准教授を経て、現職。専門は、現代哲学・倫理学。『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ)で、2019年に第41回サントリー学芸賞受賞。そのほかに『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』(角川選書)、『このゲームにはゴールがない』(筑摩書房)など著書多数
■『謝罪論 謝るとは何をすることなのか』
柏書房 1980円(税込)
「すみません」では済まないとき、何をすれば謝ったことになるのか? 他人の謝罪を見て、「それでは謝ったことにならない」「誠意が感じられない」と言うとき、私たちはどうやってそれを判断しているのか? 責任、償い、約束、赦し、後悔、誠意への懐疑、そしてコミュニケーションの起点――謝罪の果たすさまざまな機能や不適切な謝罪の特徴を解き明かし、学際的な知を総動員して、「謝罪の全体像」に迫る!