 台湾北東部に位置する野球の名門校・三星国小野球部の面々
台湾北東部に位置する野球の名門校・三星国小野球部の面々
昨秋の「WBSCプレミア12」で日本を破って優勝し、野球の強豪としての地位を確立した台湾。その躍進の原動力になったのは原住民たちの力だという。ルポライターの安田峰俊氏がその実態を調査すべく、台湾を縦断! 知られざる原住民の"野球村"に突撃した!
* * *
■アジア有数の"野球民族"
台湾は意外と野球が強い。昨年11月に東京ドームで開かれた国際野球大会・WBSCプレミア12決勝では、台湾(チャイニーズ・タイペイ)代表が日本代表を撃破してまさかの優勝。日本の野球ファンにも衝撃が広がった。
だが、この優勝メンバー28人のうち、決勝戦勝利投手の張奕(元オリックス、西武)を含む13人が台湾原住民(タイワンユエンジュ―ミン)出身の選手であることはあまり知られていない。
原住民とは、漢民族が移住する前から台湾島で暮らしてきたオーストロネシア系の先住民族だ。アミ族やタイヤル族などの16民族が台湾政府に認定されている(ほかに未認定の民族もいる)。
現在、彼らが台湾の人口に占める比率は2.6%程度。だが、なんと現地のプロ野球(CPBL)界では、全プレーヤー356人のうち約42%が原住民出身である。彼らは戦闘民族サイヤ人――もとい、アジア有数の"野球民族"とでも呼ぶべき人たちなのだ。
日本のプロ野球(NPB)で名を成した原住民出身の台湾選手も多い。1980年代~90年代の中日の好投手・郭源治(かく・げんじ)、日本ハムと巨人でプレーした好守強打の外野手・陽岱鋼(よう・だいかん)、楽天のセットアッパー・宋家豪(そん・ちゃーほう/いずれもアミ族)らは特に有名である。今シーズンから日本ハムに加入した速球派右腕の古林睿煬(ぐーりん・るえやん/タイヤル族)も期待が大きい。
 練習中の三星国小野球部の小学生たち。ほぼ全員が台湾の原住民である
練習中の三星国小野球部の小学生たち。ほぼ全員が台湾の原住民である
原住民の集落は、宜蘭(イーラン)県、花蓮(ホァリェン)県、台東(タイドン)県など、交通が不便な台湾東海岸(太平洋側)の地域に多い。現地の子供たちは、未来の陽岱鋼や宋家豪となるべく、日々白球を追いかけ続けているという。
原住民野球村。言葉の響きだけでも面白すぎる。早速訪ねてみることにした。
■野球に"全振り"
「漢民族の子供と比べても、みんな運動は好きですね。まずは野球。そしてバスケとマラソン。近年はスマホゲームもはやっていますが、とにかく走り回っている印象ですよ」
そう話すのは、台湾北東部の宜蘭県大同(ダートン)郷にある大同小学校(国小[グォシャ])教師の林(リン)先生だ。この集落は、地元出身の林先生を含めて住民の大部分が原住民のタイヤル族。周囲は山と川に囲まれ、集落唯一のセブン-イレブンは夜10時に閉店してしまう。ゆえに娯楽は限られ、人々の興味はもっぱら野球に向いている。
「教育方針が"野球に全振り"という保護者の方も一部におられまして......。教師としては少し頭の痛いところでもありますが」
事実、休み時間の校内で男子児童がプラスチックバットでボールを打って遊んでいるのを見ると、スイングや投球フォームが妙にダイナミックである。さすが野球大好き集落の小学生だ。
なお、日本の少年野球は地域のチームがほとんどだが、台湾では小学校付属の「部活」として行なわれる。
大同小の野球部もかつては勢いがあり、地域住民の援助で、山奥に巨大な専用球場まで建設。しかし、少子化によって全校生徒が25人になり、さらに資金不足で野球部は同好サークルに格落ちしてしまった。
ゆえに"ガチ"な保護者は、子供を地域の野球名門校に転校させている。近隣の他の原住民集落も同様らしい。
「このへんだと、隣町の三星(サンシン)郷にある三星小学校の野球部に入れる保護者が多いですね」(林先生)
三星小は、昨年のプレミア12の決勝戦に7番セカンドで出場した台湾代表選手・岳東華(ユエ・ドンホァ./タイヤル族)の出身校である。名だたる強豪だ。
「おいおい、高校野球かよっ!」
実際に三星小に行ってみて、いきなりビビった。緑色のネットが張られた野球専用の室内練習場が、校門の隣に鎮座していたからだ。校舎内を見て回ると、使い込まれた大量の金属バットとグラブ、ボール(硬球)。公立校なのに資源を野球に全振りしたかのようなたたずまいである。
 ノックを打つ三星国小野球部の黄郁翔監督。名将として知られる
ノックを打つ三星国小野球部の黄郁翔監督。名将として知られる
ちょうど放課後になり、背中に漢字の名前が書かれたユニフォーム姿の丸刈りの少年たちが、次々と道具を手にグラウンドに出ていった。
「約30人の野球部員のうち、9割は原住民の子供たちです」(黄郁翔[ホアン・ユイシャン]監督)
この地域はもともと木材産業で有名な土地。木の切り出し自体は数十年前に廃れたものの、原住民児童たちの多くは"きこり"の子孫らしい。
山向こうの集落から"プチ野球留学"する子も多く、野球部員には小学生にもかかわらず寮がある。台湾の野球名門校では珍しくない話だという。
三星小野球部の練習は、ひと昔前までは「茶畑を走り続けて鍛える」といった、いかにも台湾ならではの内容だった。だが、近年は球界のトレンドに合わせて、持久力よりもパワーや爆発力を重視する科学的なトレーニングに変わってきている。
「もっとも、今年は小柄な選手が多いので守備重視。地道な基礎練習を重ねる、やや旧来型のスタイルを採るようにしました」
そう話す黄監督自身も三星小野球部出身の原住民だ。大学卒業後にコーチになり、宜蘭県政府から雇用される形で母校に戻って15年ほど。台湾の学校野球部のコーチや監督は"専任"であり、自治体や民間基金団体から雇われる形式が一般的だ。
チームのもうひとりのコーチは、寮の宿直も務める。給料は比較的安く、好きでなければ続かない仕事だ。三星小の野球部は子供から部費や寮費を徴収せず、補助金や募金で運営しているため、資金問題は常に頭が痛い。
「台北(たいぺい)など大都市の子供の場合、親が熱心なら、月に数万円の月謝を払って個人コーチを雇い......といった野球エリート教育が行なわれます。ただ、三星小は経済力が弱い家庭の子も多い。部員たちが寮住まいで培った規律と団結力が勝利の鍵です」(黄監督)
■日本統治下から育まれた野球文化
そもそも、台湾の原住民はなぜ野球が好きなのか?
「日本統治時代、日本側の主導で、花蓮に原住民のチームが結成されたのが起源です」
台北に本部を置く原住民棒球(野球)運動発展協会の創設メンバーである、アミ族出身の鄭幸生(ヂェン・シンション/マンヤオ・イトン)氏はそう話す。
 原住民棒球運動発展協会創設メンバーの鄭幸生(マンヤオ・イトン)氏(右)と筆者
原住民棒球運動発展協会創設メンバーの鄭幸生(マンヤオ・イトン)氏(右)と筆者
戦前の台湾は、50年にわたり日本の統治下に置かれた。当時、映画『KANO 1931海の向こうの甲子園』のモデルにもなった嘉義(かぎ)農林学校をはじめ、台湾の高校が日本本土の甲子園に何度も出場。各チームには原住民選手も含まれており、原住民の野球熱が高まった。
さらに戦後、中華民国の統治下では、中国語ができない原住民たちは不利な環境に置かれた。結果、野球は彼らが熱中できる数少ない娯楽、かつ自己表現の場になった。
「大きな話題になったのが、チーム全員がブヌン族だった台東県の紅葉(ホンイエ)小学校野球部が、68年に日本の関西少年野球選抜チーム(和歌山のチームとも)に圧勝した事件です。私自身、子供時代にこの話を知って野球選手を志したほどで......」(鄭氏)
紅葉小の快挙は、地元に記念館が建てられたほど。資金難でボールが足りず、選手が石を投げて練習した故事も、原住民の間では半ば伝説となっている。
鄭氏自身、現役時代には開幕21試合連続安打の台湾記録を打ち立てた元プロ野球選手だ。彼は原住民選手たちの特徴をこう話す。
「全体的な傾向としては、俊敏性に優れている。活動的でオープンな性格の人が多い。なので、機動力で戦うタイプの野手が多いですね」
野球選手になる原住民はアミ族が多い。漢民族と比較して、アミ族は身体的に無酸素運動に向くとする学術研究も発表されており、短距離走や野球など瞬発力が必要なスポーツに適性があるようだ。
「ただ、自分をストイックに追い込んでいく必要がある先発投手は、原住民選手にはあまり多くない。あえて言えばストッパーのほうが向いています。緻密な配球で攻める捕手も少ないですね。もっとも、次のWBC台湾代表メンバーの高宇杰(ガオ・ユイジェ/アミ族)は頭脳派捕手なのですが(笑)」
原住民棒球運動発展協会は、参加者のほとんどが原住民のプロアマ交流野球大会「関懐杯(グアンホアイペイ)」を毎年開くなど、野球を通じた原住民たちの相互交流と次世代の育成に力を入れている。
ちなみに2005年から使われている台湾ドルの500元(約2200円)紙幣に描かれているのは、1998年に「関懐杯」で優勝した台東県の少年野球チームのメンバーだ。原住民野球大会は、意外と影響力が大きい。
■"口減らし"の受け皿として
選手の話も聞いてみよう。私が訪ねたのは花蓮県光復(グァンフゥ)郷の光復中学校(国中[グオヂョン])野球部である。
同校は2023年のアジアプロ野球チャンピオンシップの台湾代表ショートとして来日した馬傑森(マァ・ジェセン/ブヌン族)をはじめ、過去に20人以上のプロを輩出してきた古豪である。
「僕の両親ですか......。えーと、たまに山で弓を射ています。イノシシを狩るのが趣味なんです」
そう話すのは、4番を打つブヌン族の田楷書(ティエンジェシュー//カイシュ)くん、15歳だ。
彼は中学から野球を始めたにもかかわらず、今年のU-15野球台湾代表にも選出されたパワーヒッター。しばしば場外ホームランを隣の民家に叩き込む。
 光復国中野球部の4番、田楷書(カイシュ)くん。外見どおりの長距離砲だが、肩もいい。ポジションはファースト、サード兼投手
光復国中野球部の4番、田楷書(カイシュ)くん。外見どおりの長距離砲だが、肩もいい。ポジションはファースト、サード兼投手
同校の女性体育教師で元ソフトボール台湾代表でもある杜恵美(ドゥ・フイメイ)監督が「近所への弁償が大変(笑)。でも、彼はプロになれるよ」と太鼓判を押す、期待のスラッガーだ。
「目標とする選手は、台湾代表チームの常連で中信ブラザーズ所属の張志豪外(ヂャン・ヂーハオ)野手(アミ族)。あと、NPBなら甲斐拓也選手(巨人)ですね。日本に野球留学したいけれど、お金の問題がなあ......」
 花蓮の光復国中野球部キャプテンの厳凱祥(サワイ)くん。俊足好守のショート兼投手。有望選手のひとりだ
花蓮の光復国中野球部キャプテンの厳凱祥(サワイ)くん。俊足好守のショート兼投手。有望選手のひとりだ
もうひとり話を聞いたのが、キャプテンでアミ族の厳凱祥(イェン・カイシャン/サワイ)くん、15歳だ。こちらは細身のショートで、好守と「ミサイルのような俊足」(杜監督)が売りの2番打者である。投手も兼任し、フォークボールを投げられる。
「小学校3年生から野球をやっていて、ずっと寮住まい。寮生活は4人1部屋で、けっこう楽しいです。好きな選手は大谷翔平さん。いつかプロになって、日本で野球をするのが夢です」
 打撃練習中の光復国中野球部。蚊が多い地域だが、気にしないでがんばる
打撃練習中の光復国中野球部。蚊が多い地域だが、気にしないでがんばる
光復郷は蚊が多く、空では殺虫剤をまく農業用ドローンが飛び続けていた。そうした現代風の原住民集落で、チームの前監督である江建程(ジャン・ジェンチェン)コーチは「ここの野球も変わってきた」と話す。
「今の子たちはスマホがあるから、自分で大谷翔平のトレーニング方法の動画を調べて『走り込みは不要。ウエイトトレーニングが重要です』とか言い出す(笑)。おかげでスタミナが弱くて、投手が長いイニングを投げられないんだ。肩を守る上では大事でもあるが、時代の変化を感じるよ」
トレーニングが効率的になった一方、スマホの影響で選手の忍耐や集中力が落ちた、保護者が過保護になってきた、と江コーチはボヤく。
 花蓮県原住民文化館の門前にそびえ立つ原住民の像。尚武の気風が野球選手をつくる......のか?
花蓮県原住民文化館の門前にそびえ立つ原住民の像。尚武の気風が野球選手をつくる......のか?
台湾の野球人気は高いものの、少子化によってチーム数や選手数は減少中だ。原住民野球の世界も、わが国と似たような課題に直面しているらしい。もっとも、異なる深刻な問題もある。
「両親の仕事は......。よくわからない。知らないんだ」
そんな選手もいるのだ。
「経済的に厳しい子も多く、両親が出稼ぎをしていて祖父母が子供を見ている家庭や、ひとり親家庭の出身者も珍しくない。小学生から野球部の寮に入ったことで、仕事が何かわからないほど、親と顔を合わせていない子もいる」
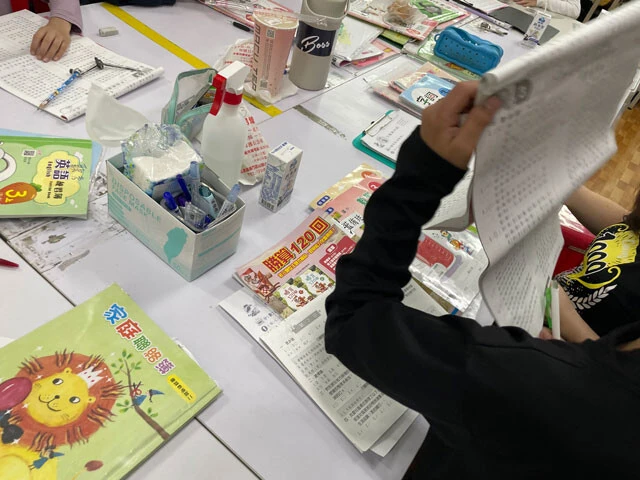 三星小の付近にある、教会が運営する貧困家庭向けの無料塾。原住民の子供たちも多く通う
三星小の付近にある、教会が運営する貧困家庭向けの無料塾。原住民の子供たちも多く通う
小中学校の野球部は、どこも資金繰りが厳しいとはいえ、選手たちは寮に住めば食費や生活費がほとんどかからない。そのため、経済的な理由から子供を野球部に入れる親も多いのだという。
「身体能力が高い子が多い半面、勉強が苦手な子も少なくない。そういう子が野球で身を立てようとするんだ」(江コーチ)
近年、台湾の野球選手は二極化している。中流層以上の家庭出身で、親から道具や個人コーチをたっぷりと準備してもらった都市部の漢民族の選手と、地方の比較的厳しい環境から這い上がる原住民の選手とだ。
1989年に発足した台湾のプロ野球リーグ・CPBLは、選手の低年俸やマフィアの介入による八百長問題などで揺れた時期もあったが、近年は人気が復活した。各球団がアイドル化したチアガールをそろえ、多くの人が球場に足を運ぶようになったのだ。

CPBLでプロのスター選手になれば、年俸は数千万円以上。NPBやメジャーに行けば億単位になる。ゆえに夢を追う原住民の少年たちは後を絶たない。
「しかし、実際はプロになれるのは100人に1人くらいだろう。私は選手によく『自分を客観的に見ろ』と言っている。野球にこだわらない現実的な進路指導が必要だと思っているよ」
アスリートのセカンドキャリアは日本でもよく問題になる。だが、"野球一本"になりがちな台湾の原住民の場合、より深刻な面があるのだ。
■分断した国家を団結させるただひとつのスポーツ
台湾人の野球への思いは極めてアツい。
「台湾にとって、野球は特別なスポーツだ。大げさに言えば『国家の統一』のために必要だとさえ思ってるよ」
そう話すのは、原住民の少年野球の援助を行なっている企業家の40代男性(漢民族)だ。
台湾は民進党と国民党の二大政党制の下、世論の分断が激しい。また、台湾は多民族国家でもある。福建系の多数の台湾人、祖先が中国から来た外省人、客家(はっか/漢民族の方言グループ)、原住民など、人口2300万人ほどの中に異なる言語や文化の人たちを多数抱えているためだ。
「でも、野球の台湾代表戦を見るときだけは、政治や文化の違いを超えて団結できる(笑)。マイノリティの原住民への関心も高まる」
 台北の原住民棒球運動発展協会の事務所に飾られたトロフィーや記念品。野球好きで知られる頼清徳台湾総統のサインボールも!
台北の原住民棒球運動発展協会の事務所に飾られたトロフィーや記念品。野球好きで知られる頼清徳台湾総統のサインボールも!
昨年のプレミア12の優勝も、この風潮に拍車をかけている。野球ファンの頼清徳(らい・せいとく)総統は、台湾ドルの500元紙幣のデザイン変更を約束。紙幣には従来の少年野球チームの絵柄に代わり、台湾代表優勝チームが描かれることになった。
紙幣になってしまうほど、野球は台湾の国民的団結のキーなのだ。
そんな台湾野球の世界を、人口ではわずか2.6%の原住民たちが支えている。そんな事実は、誠に興味深い。
●安田峰俊 Minetoshi YASUDA
1982年生まれ、滋賀県出身。ルポライター。中国の闇から日本の外国人問題、恐竜まで幅広く取材・執筆。第50回大宅壮一ノンフィクション賞、第5回城山三郎賞を受賞した『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』、『「低度」外国人材 移民焼き畑国家、日本』(KADOKAWA)など著書多数。新著は『民族がわかれば中国がわかる 帝国化する大国の実像』(中公新書ラクレ)