 日本人は平和に向いていると語る西村京太郎氏
日本人は平和に向いていると語る西村京太郎氏
この9月に87歳の誕生日を迎える作家・西村京太郎氏の新刊『十五歳の戦争 陸軍幼年学校「最後の生徒」』(集英社新書)は、ご自身の戦中から戦後にかけての体験と、そうした体験を通して得た「日本人は戦争に向いていない」という考えについて書かれている。
「生れてから七年間は平和だった。昭和十二年に盧溝橋事件があって日中戦争になり、昭和二十年まで、八年間延々と戦争が続く。十五歳までである」とあるように、幼少期を丸ごと戦争とともに過ごし、敗戦の年4月には東京陸軍幼年学校に入学、同校の最後の生徒として、短いながらも士官候補生の教育を受けている。
戦争の悲惨さを身をもって知り、戦後70年の一昨年、「安保法案」が国会で可決され、「戦後」が「戦前」の様相を呈してきたことに危機感を覚え、その年末から翌年に刊行された十津川警部シリーズ作品にはどれも戦争、戦後のことを組み入れるなど、戦争体験の風化を押し止めようとしてきた思いの集大成ともいえる本書を書き終えた西村氏にインタビュー前編に続き、お話を伺った。
* * *
─つまり、日本人は戦争に向いていない。
西村 どう考えても向いていない(笑)。現代の戦争というのは、結果的に生き残った兵士の数と、戦車などの兵器の数が多かったほうが勝者になるわけです。ということは、味方の人員なり兵器なりの損失を最小限に抑えなければならない。そう考えれば、特攻という戦法がいかに非合理的かがわかるはずですよ。だって、優秀なパイロットと飛行機のどちらも無駄にしてしまうのですから。
せめて、自動操縦にして人間だけでも死ななくて済むようにしておけばいい。そういうことをなぜ考えなかったのか。結局、死を厭(いと)わずに玉砕することが美学だという間違った考えに取り憑(つ)かれてしまったんです。
あれから70年以上経っているわけだから、さすがに日本人はいくらかは進歩したかと思うじゃないですか。しかし、安保法制以降の一連の動きを見ると、ちょっと首を傾(かし)げざるを得ませんね。今、「戦争はイヤだと思いますか」と訊(き)いたら、おそらく「イヤだ」と答える人のほうが多いだろうとは思いますが、例えば、アメリカが一所懸命やっているのに日本だけが遊んでいちゃ悪いとかいうような、妙に見栄を張るようなところは今でもあるんじゃないですか。
いざとなると親とか郷里のことを考えて、自分ひとりがこんなことをして、親や郷里の人たちに恥をかかせてはいけないとか。あるいは自分だけが助かるのは卑怯だとか。日本人は、卑怯者と思われるのをひどくイヤがりますからね。それと同じで、みんながこぞって賛成している時に、自分だけ反対だというのを嫌いますよね。だから反対とはいわずに黙っている。しかし、黙っていたら、賛成なのか反対なのかわからない。
東京裁判の時に、文官としてただひとり、死刑判決を下された広田弘毅が公判中に沈黙を貫きましたね。彼が無実だと表明すれば死刑は免れたのではないかと言われていますけれど、もし広田自身、自分は無実だと思っていたのなら、そのことを裁判の場できちんと言わなければ、無罪の判決が下るはずがない。それなのに、べらべら言い訳せずに黙っていることを良しとするというところが、日本人にはある。
それに、下手に喋ると、今度の前事務次官の前川さんみたいに叩かれてしまう。まあ、偉そうなことを言っていますが、ぼくだって同じ立場になったら喋りませんけどね(笑)。あれこれ、そういうことを考えると、日本人が本当に変わったのかどうか…。
─本の最後で、「なぜ戦争に反対できないのか」と問われていますね。
西村 そう。太平洋戦争を推進した軍人たちのほとんどが、この戦争に勝てるとは思っていなかった。それなのに誰も反対できずに、途中で引き返そうともしなかった。それは、さっき挙げたような日本人の精神構造が大きく影響しているわけですね。
だから、そういう日本人は戦争をしてはいけないんです。まあ、良くいえば、日本人は平和に向いているということになるんですけどね。
●『十五歳の戦争 陸軍幼年学校「最後の生徒」』(集英社新書 本体760円+税)
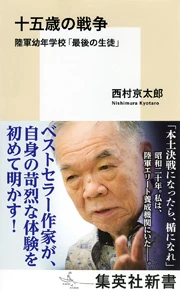
(取材・構成/「青春と読書」編集部 撮影/chihiro.)