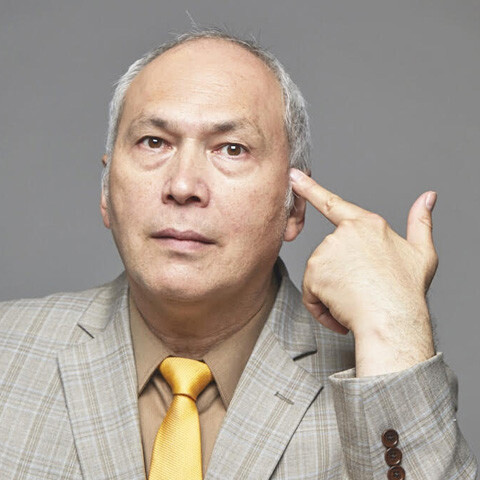
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
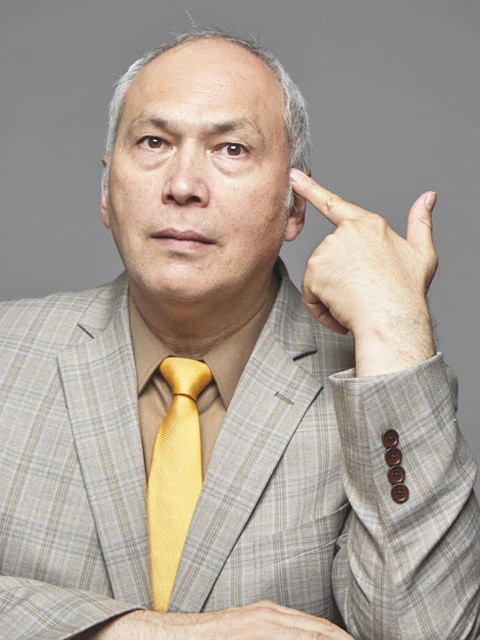 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、米トランプ政権の掲げる過激なアメリカ・ファースト政策がなぜ支持者に受け入れられるのか、その背景を考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、米トランプ政権の掲げる過激なアメリカ・ファースト政策がなぜ支持者に受け入れられるのか、その背景を考察する。
* * *
関税カードの乱発に代表される米トランプ政権の保護主義的な経済政策="アメリカファースト"は、従来の共和党政権が進めてきた新自由主義やネオコン(新保守主義)とはまったく違うものです。いうなれば「アメリカが儲かるなら、世界がどうなろうと知ったことではない」。
しかしながら、その短絡的な政策が本当にアメリカの利益になるかといえば、はなはだ疑問です。
トランプ政権のベッセント財務長官は「経済をデトックス(解毒)する」という言い回しを使います。アメリカ経済は「毒」に侵されており、それを抜くことで健全な状態を取り戻す――と言いたいようですが、肝心の「毒」がいったい何を指すのか、いまひとつ判然としません。
例えば連邦職員の大幅削減。これによる財政支出の削減効果は極めて限定的であり、財政赤字の削減にはほとんど寄与しません。その一方で、社会保障・医療などセーフティネットの弱体化を伴う減税計画が進んでおり、その恩恵を受けるのは富裕層や大企業で、低所得層は直接的な打撃を受けることになります。
トランプ政権の経済ブレーンの多くはアカデミアにおいて主流派から軽視されてきた"異端者"で、従来の経済理論から乖離した政策が進められているとの指摘もあります。主流派の専門家やアナリストからは、景気悪化と物価高が同時進行するスタグフレーションのリスクを指摘する声も聞こえてきます。
ただ、こうなってしまった原因のひとつが「アメリカ人」自身にあるという側面も否めません。
第2次世界大戦以降のアメリカ社会には、自分たちが世界のナンバーワンであるという集団的自意識が広がり、それを前提としたナショナリズムが展開されました。そのため、日本のように敗戦を経験した国や、外交面でしばしば譲歩を余儀なくされる国が自然に持ちえている"謙虚さ"に乏しいのです。
こうした"傲慢さ"はイノベーションのエンジンになる一方、国内問題から目をそらすことへの誘惑にもなりえます。偉大なアメリカがうまくいかないのは誰かがアメリカをおとしめているせいであり、そこを叩けばすべてが解決する――外側に"敵"を作って熱狂を演出するトランプの手法はまるで新興宗教か、あるいは北朝鮮の主体思想のようですが、その"補助剤"となっているのはまさにアメリカ人の傲慢さでしょう。
実際のところ、トランプ政権の経済ブレーンや支持者たちは「アメリカはババを引かされている」と本気で思っているフシもあります。しかし、誰かを責め立てることで問題を解決した気になっている限り、本質的なデトックスなどできるわけがありません。その姿勢こそがアメリカの「毒」にほかならないのですから。
日本に対しても「為替を操作している」「鉄鋼をダンピングしている」などと言いがかりをつけ、安全保障をテコに屈服させようとするトランプ政権の姿勢は、もはやヤクザの恫喝のようです。
この経済政策が機能不全に陥るのは時間の問題であり、いずれ"魔法が解ける"ことにはなるだろうと私はみていますが、そのとき、ボロボロに傷ついたアメリカという国はどのように立ち直るのか、再び上昇できるのか。その過程に注目したいと思っています。
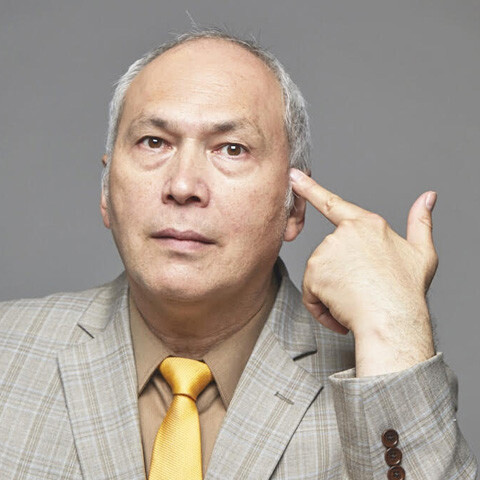
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)