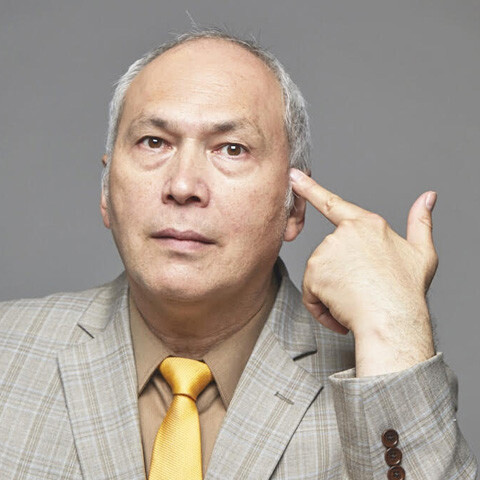
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
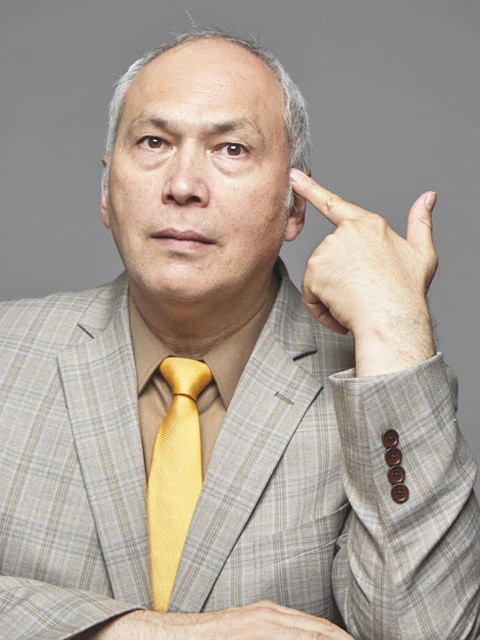 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、これまで「有事」に関する発信に極めて消極的だった日本政府の変化を評価しながら、その次に必要となる国民レベルの議論と心構えについて考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、これまで「有事」に関する発信に極めて消極的だった日本政府の変化を評価しながら、その次に必要となる国民レベルの議論と心構えについて考察する。
* * *
この3月、台湾有事(中国の台湾侵攻)を念頭に置いたとみられる動きが相次ぎました。台湾行政院は、自衛隊の元統合幕僚長(制服組トップ)を政務顧問に任命。一方、日本政府は沖縄・先島諸島の住民や観光客など10万人規模の避難計画を初めて公表しています。
これまで中国を刺激しないことを第一とし、コンティンジェンシー(非常時対応)の「議論」や「検討」を公表することさえ忌避してきた日本政府が、遅ればせながら"もしも"の想定を提示し始めたのは、ある種の変化の兆しでしょう。しかし、実際にどんなリスクが想定されるか、何を優先して何を捨てるか、といった国民レベルの議論はほとんどなされていません。
中国・習近平体制の強硬姿勢、ロシアによるウクライナ侵攻が示した「力による現状変更」の脅威、そしてトランプ米大統領の戦後国際秩序を投げ捨てるような一国主義。以前とは前提そのものが変わってしまっているにもかかわらず、「日本や台湾と中国は経済的に強く結びついているから有事なんてありえない」「世界は経済原理で動いている。危機をあおるのはビジネスを知らない経済オンチだけだ」などと考える"現実派"は少なくありません。
しかし、20世紀末から広がったグローバリズム、とりわけ2001年の中国のWTO(世界貿易機関)加盟以降に進んだ産業の空洞化は、先進国の社会構造を静かに、そして確実に侵食してきました。
その結果、集団的自衛権や経済連携を土台に築かれた「ステータス・クオ(現状維持)」という秩序モデルは、土台自体が弱体化。もはや無条件に機能するわけではなくなっています。
そこに追い打ちをかけたのが、欧米のエリート政治家や研究者、テクノクラート(技術官僚)が数十年かけて積み上げてきた知的枠組みを、一発のSNS投稿で破壊してしまうトランプの存在です。
NATO(北大西洋条約機構)への不信をあおり、関税で世界経済を振り回す。政権内ではシロウトたちが各分野のトップに就き、軍事機密を盛大に漏洩してもどこ吹く風。
そんな現在のアメリカによる"庇護"を前提に日本の国防や憲法を語ったところで、以前のような説得力は生まれません。では、日本は今の「現実」にどう向き合う必要があるのか。
例えば台湾有事が起きたら、欧州の不安定要因となったシリア難民のような規模まではいかずとも、日本は隣接する友好国として、中長期的に台湾から難民を受け入れることが必要になるでしょう。しかしメディアもほとんどの国民も、その「現実」を見ようとはしない。
平時ですら観光客のマナーや外国人居住者のゴミ出しにイライラしている人が多い中で、台湾からの避難民が増え、それと並行して中国資本による不動産購入がさらに加速するような事態となれば、「日本が乗っ取られる」などという陰謀論が勢いを増すのは明白です。
東日本大震災に伴う福島第一原発事故の際、日本社会は強烈なパニックに陥りました。その要因のひとつは知識と議論の欠如です。
せめて想定されることについては考え、議論をしておかなければ、想定外のことに向き合うための"弾力"が社会に備わらず、いざというときに瞬間的な民意に流されてしまうでしょう。
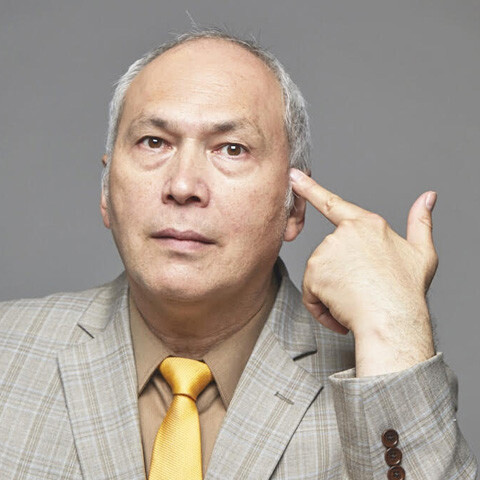
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)