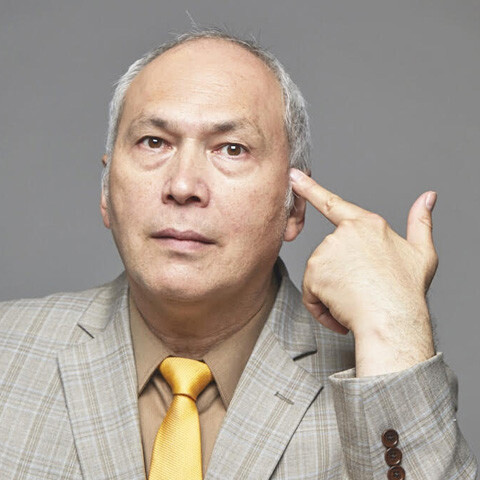
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
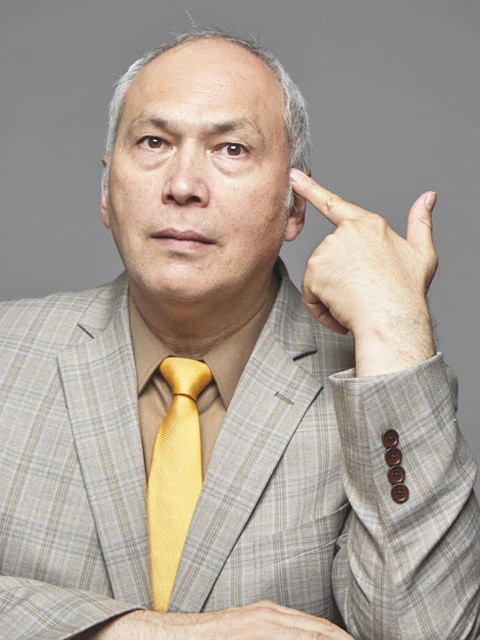 二転三転するアメリカの関税政策に世界が混乱している。『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、"トランプショック"前夜の日本のメディアや専門家の発信について考察する。
二転三転するアメリカの関税政策に世界が混乱している。『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、"トランプショック"前夜の日本のメディアや専門家の発信について考察する。
* * *
3月末、東京の外国為替市場の為替レート表示が、米ニューヨーク市場に比べ0.1〜0.2秒遅れるようになったという経済記事を見ました。アルゴリズム取引が支配する国際金融の世界において"まばたき1回分"の遅延は非常に大きく、国益を損なう恐れもある、と。
確かにそうかもしれないと思いつつ、もっと深刻に考えるべきことがあるのでは、というモヤモヤもありました。
その数日後、米トランプ政権は日本を含むほぼすべての貿易相手国に対して「相互関税」を導入すると発表。世界的な株安が進みました。
その後もトランプ政権の方針は二転三転し、そのたびに金融市場が大きく動き、そしてメディアの分析報道も続いています。ただ、トランプ政権は発足以来、相互関税について繰り返し予告しており、今回のような動きが"青天の霹靂"だったわけではありません。
私が気になったのは、実際に市場が反応する前の、日米のメディアの温度差です。
もちろんどちらの国でも、楽観的な見解から悲観的な見解まで幅広い報道がありました。ただ、自国の政権の動きであるという点を差し引いても、アメリカのほうが現状を危機的な局面だと認識し、強く警鐘を鳴らす媒体が明らかに多かった。
一方、日本のメディアは「通商戦争の一環」「いつものトランプ節」と受け流す論調が目立ち、経済専門の媒体、あるいは経済の専門家も、多くは傍観者のような論評にとどまっていました。
問題は分析や予測の精度ではなく、Attitude(アティテュード:姿勢、態度)の違いです。
欧米の経済専門家たちは自らの見解を明確に述べ、しばしば「〇〇すべきだ」という"べき論"を展開します。超大手証券会社・JPモルガンのCEO、ジェイムズ・ダイモンのような立場ある人物でさえ、世界経済におけるアメリカの立ち位置がどうあるべきか、明快に語ります。
それと比較すると、日本のアナリストや経済人たちは「アメリカがこう言っているから」「マーケットがこう反応したから」といった説明にとどまり、自らの立場や考えを打ち出すことを避けがちなのです。
もちろん慎重さや中立性を矜持としている方もいらっしゃるのでしょう。しかし、今や世界経済は地政学、人権、環境、中国依存など多くの問題と分かち難く絡み合っており、その背景を深く分析する必要があるのみならず、個々の論者の「立ち位置」も重要な議論のファクターです。
専門的な知見を持つ人々が中立性ばかりにとらわれると、社会全体に"現状維持バイアス"が浸透し、目の前に迫った課題に対する理解の遅れ、反応の鈍さを生み出しかねません。自分たちの言葉で語ることを放棄し、波風を避ける――日本の専門家の"それ"は、経済版の事なかれ主義、もしくは平和ボケといえるかもしれません。
この日本と世界の「認知のズレ」は、0.2秒の情報遅延どころではなく、社会を形づくる基盤に関わる深刻な"病"だと思うのです。なぜなら、目の前の危機に気づくのが遅れれば、もしくは気づかないふりをし続ければ、いずれ人々は大きな代償を払うことになるからです。
これは個々の専門家の問題というより、硬派な報道にリソースを割けなくなった日本メディア全体の問題です。"べき論"には目もくれず、狭義の「経済」だけを切り出した報道が主流であること自体が「ズレている」ということを社会的に認知した上で、日本としてどうすべきかを議論することが今は必要なはずです。
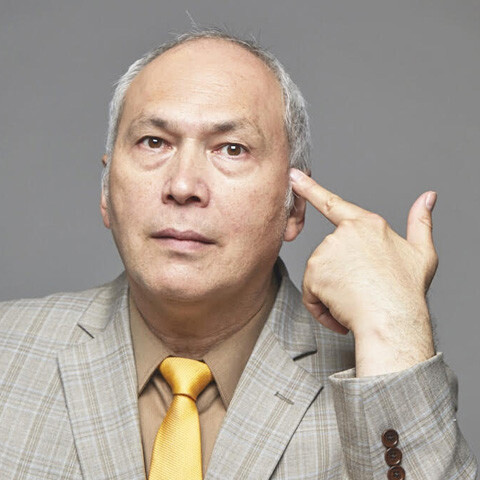
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)