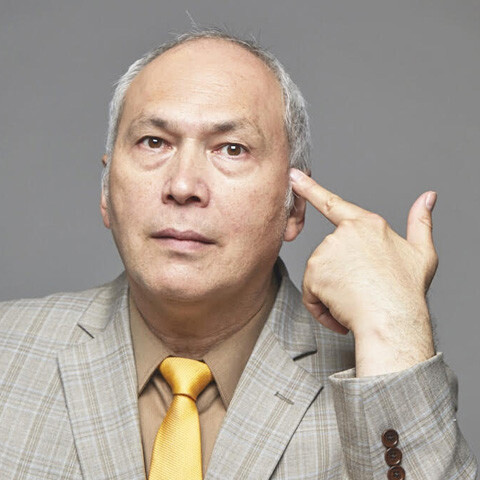
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
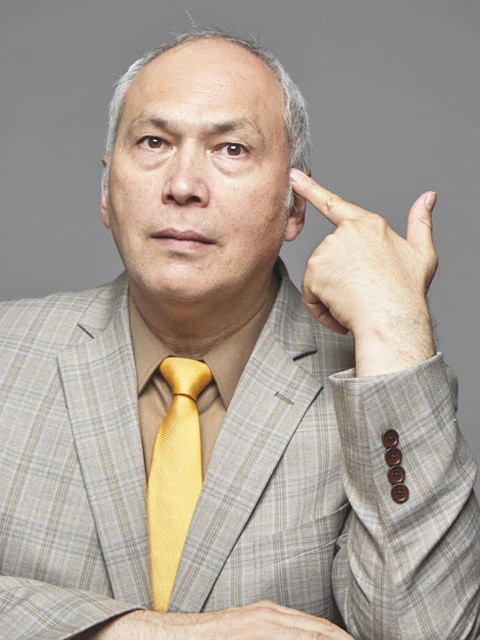 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、国際社会を混乱におとしいれている第2次トランプ政権を生んだアメリカと、どう向き合っていくべきかを考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、国際社会を混乱におとしいれている第2次トランプ政権を生んだアメリカと、どう向き合っていくべきかを考察する。
* * *
1987年9月2日、当時41歳のドナルド・トランプは『ニューヨーク・タイムズ』『ワシントン・ポスト』『ボストン・グローブ』の3紙に、アメリカの外交防衛政策を批判する全面広告を掲載しました(もちろん政界入りする前のことです)。
その中には日本を名指しで激しく非難する内容もありました。いわく、日本はアメリカにただ乗りして自衛のための莫大なコストを回避し、かつてない規模の貿易黒字を生み出し、強力な経済を築いてきた――。
この広告は、日本経済に押されていた当時のアメリカ国民が抱いていた"憤り"を明瞭に代弁したものであり、トランプの「アメリカ・ファースト」的な思想の原点とも言えるものでしょう。
それから約40年、トランプは、今度は同じ発想で全世界を相手にしようとしています。大きな違いは、80年代の単なるパフォーマンスとは違い、今回はアメリカ大統領として実権を振るっていること。
それによって今起きていることは、構造的な変質を伴う新しい"秩序"の始まりととらえるべきであり、おそらく事態は沈静化するどころか、むしろじわじわと悪化し続けていく。当然、その影響は長期にわたるでしょう。
これを一時の混乱に過ぎないととらえ、「嵐が過ぎるのを待つ」姿勢でいることは危険だと私は考えています。その理由は、政治の変化です。
アメリカを含めた世界各地で、政治の舞台における"過激さのインフレ"が進行しています。選挙はエンタメと化し、議論ではなく罵倒と感情のぶつけ合いが主戦場になり、言ってしまえば「下品なほうが勝つ」というポピュリズムの構造がつくられやすくなっているのです。
これが何を意味するか。"過激なアメリカ"がトランプ政権期だけで終わるとは限らないということです。トランプの後には、J・D・ヴァンス大統領(現副大統領)/ピート・ヘグセス副大統領(現国防長官)という、"トランプ政権2.0"とも言える体制が誕生する可能性もある。
だとすれば、「あと3年半耐えればいい」という見方は希望的観測にすぎず、8年、12年という長期スパンで、世界は"熱に浮かされたアメリカ"に振り回され続けることになります。
さらに言えば、仮にアメリカで政権交代が起きたとしても、二極化が進む米社会の現状を考えれば、新政権が「前の政権を全否定する」ような政治状況が続く可能性は高いでしょう。アメリカ政府が一貫性を失って振り子のように動くことで国際社会が負うコスト、リスクは計り知れません。
この"地殻変動"に際して、日本がそこに何を見いだすか、あるいはそこから何を見落としてしまうかは、極めて重要な意味を持ちます。
日本の常套手段だった「様子見」や「我慢」では、取り残されるリスクが格段に上がっています。アメリカの変質を前提に、むしろ新たなチャンスを探すことが重要かもしれません。
例えば、トランプ政権によって大学や研究機関への政治的介入や資金削減が進む中、アメリカ国内の研究者や技術者が国外に活路を見いだす動きも出てきているようです。当然、これは日本にとって優秀な人材を受け入れる好機です。
彼らの知見を生かすための土壌を整え、力を発揮してもらうと同時に、現在のアメリカを日本人が理解するための良きアドバイザーとしても大いに活躍してもらうべきでしょう。
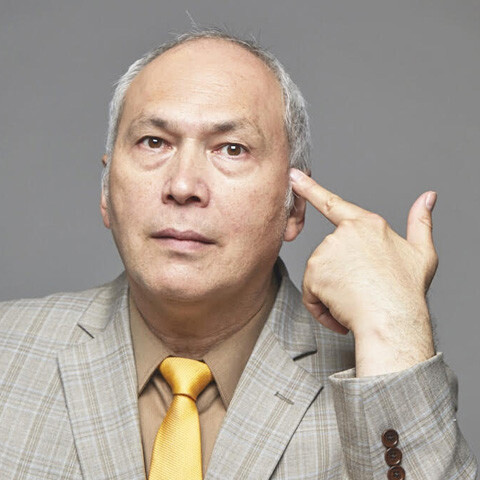
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)