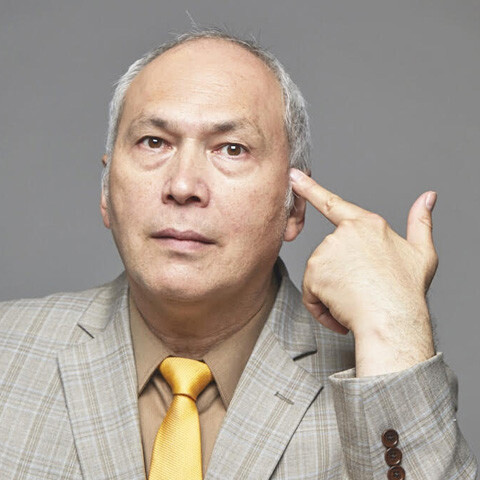
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
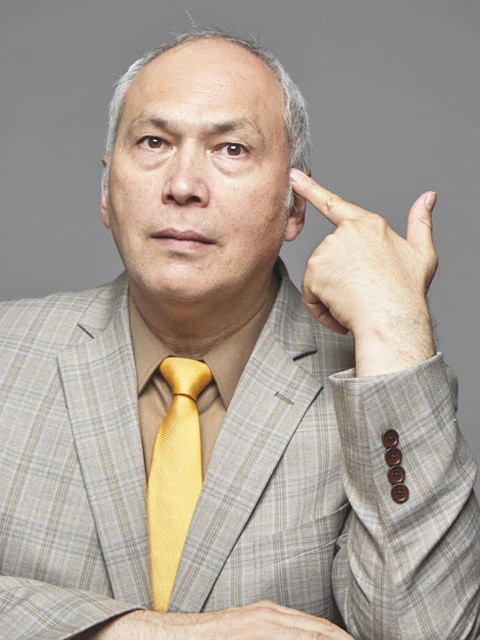 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、トランプを支持する人々、あるいはアメリカ社会に存在する"自己矛盾"の正体と、そこから生まれる危機について考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、トランプを支持する人々、あるいはアメリカ社会に存在する"自己矛盾"の正体と、そこから生まれる危機について考察する。
* * *
「われわれはもはやリベラルな民主主義国家に住んでいるとは言い難い」――ハーバード大学政治学教授のスティーブン・レヴィツキーらがかねて指摘してきたようなアメリカの危機が、誰の目にも明らかになりつつあります。
トランプ政権はDEI(多様性、公平性、包括性)プログラムの排除を加速させ、大学の資金凍結や職員の大量解雇も次々と実行しています。
フランス人研究者がトランプ政権批判が理由とみられる入国拒否に遭ったり(米当局は別の理由を主張)、ユタ州の大学の日本人研究者が過去のごく軽微な法令違反歴を理由に突然ビザを取り消され、家族ごと国外退去を命じられたりといった事態も発生しています。
いずれも後に処分は見直されましたが、DEIを「ムダで有害なもの」と断じ、教育や研究、学問の独立性を脅かす米政府の動きは、一種の思想統制と呼ぶべきものです。
ただし、こうした強権的な動きが進む一方で、MAGA支持層の内部にも早晩、ほころびが生じる可能性は高い。富裕層と低所得層、都市と地方など、異なる背景を持つ人々の利害は本質的には一致していません。
例えばムチャな関税政策を発表した直後、株式市場の混乱でトランプを支持するビリオネアたちの資産は大きく目減りし、低所得層は「ざまあみろ」と留飲を下げました。しかし、高関税が続けばいずれ物価が高騰し、今度は低所得層を生活苦が直撃することは目に見えています。
アメリカ社会が抱えるこの自己矛盾の背後には、独特の"興奮依存症"があります。
キリスト教徒として清貧でありたいと望みながら、欲も全力で満たしたい。特盛りのフレンチフライを頬張りながら、運動することなく痩せ薬に依存する。ネットショップのワンクリックで必要がないものを次々と購入してしまう。抑制より興奮、節制より高揚......。
アメリカ人の「夢を見ろ」「勝者になれ」という欲望は、社会にもたらす副作用を無視した規制緩和を熱狂的に支持してきました。その結果、搾取と格差は加速的に拡大。それでも昨年の大統領選で、社会の約半分がトランプというデマゴーグを再び支持しました。
自分たちの消費行動、選択、責任を直視せず、「誰かが悪い」という物語にすり替え、怒りをまき散らすそのさまは、ある種の"自己免疫不全"のようなものです。
トランプがあおってきた「敵を憎め、叩け」という感情は、状況次第で容易に「向き」を変えます。ということは、トランプ自身も怒りのエネルギーにのみ込まれるリスクを常に抱えている。
半年後か1年後かはわかりませんが、「アメリカを取り戻す」という約束が果たされなければ、支持層の中から「詐欺師だ」「嘘つきだ」といった声が出てくることは避けられないでしょう。
それはすなわち、具体的な問題解決策を提示せず、扇動で突き進んできたMAGA運動の空中分解の始まりです。
ただし、一度火がついた群衆の怒りのエネルギーは簡単には鎮まらない。その対象は「金持ち一般」や「エスタブリッシュメント全体」になっていくかもしれません。
トランプもバイデンも、誰も自分たちを救わなかった......その絶望が、MAGA運動が崩壊したがれきの中から、また新たなデマゴーグを誕生させる可能性も考えておくべきでしょう。
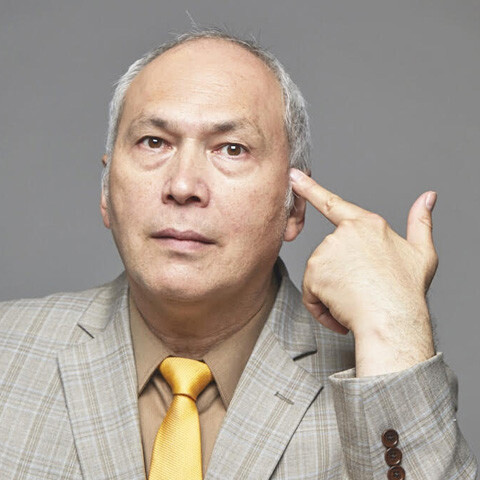
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)