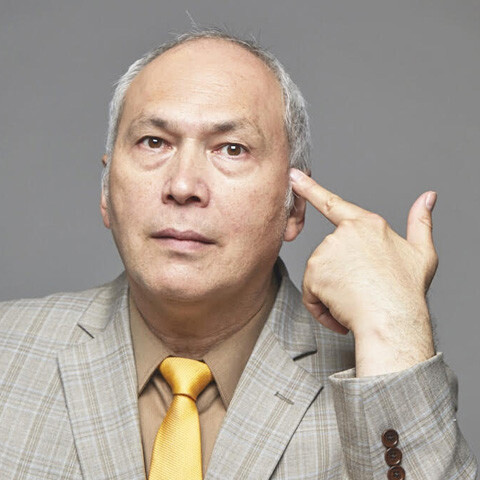
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
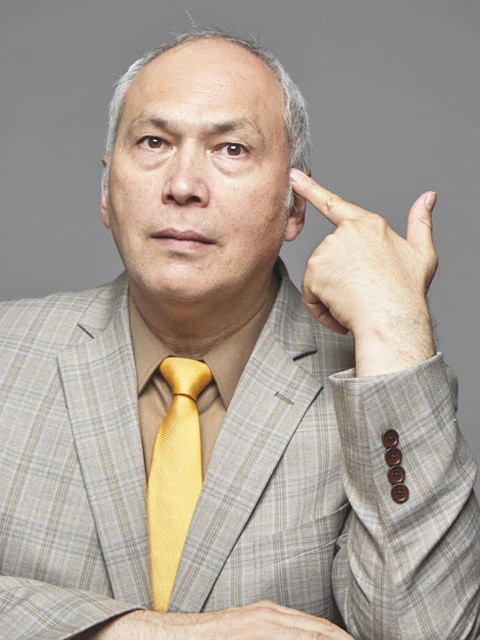 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、かつてドキュメンタリーの巨匠たちの「激論」を目の当たりにした経験から、SNSに過剰な自己演出が飛び交う現代社会の問題点を考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、かつてドキュメンタリーの巨匠たちの「激論」を目の当たりにした経験から、SNSに過剰な自己演出が飛び交う現代社会の問題点を考察する。
* * *
人間が「反応してしまう」ようにカスタマイズされたデジタル環境下の刺激に囲まれた現代人は、"アテンション・スパン(集中持続時間)"が短くなっている――そんな指摘があります。確かに、SNSなどで「ツカミが強い」「すぐに注意を引く」ようなサムネや見出しをクリックし、アルゴリズムが提案する"次のオススメ"をまたクリックし......ということを繰り返す生活習慣の副作用として、体感的にも納得できる論点です。
私なりにこの潮流を言い換えるなら、「退屈に対する耐性」や「興味の外にあるものへの受容性」の低下、といったところでしょうか。
少し昔話をさせてください。私はハーバード大学在学中に専攻を変更し、映像について学びました。当時、大学はドキュメンタリーに力を入れていましたが、私にとっては関心外でした。芸術系の映像制作を志向しており、「リアル」の追求に意味を見いだせなかったのです。
あるとき、映画監督の今村昌平さんと記録映像作家の姫田忠義さんが日本から来て、1週間にわたり特別講義をされ、私が同時通訳を務めることになりました。その中で、姫田さんが代表作『越後奥三面――山に生かされた日々』の裏話をした際、ふたりの巨匠が対立する場面がありました。
ある村がダム建設によって「閉村」するまでの4年間を追った同作の撮影中、姫田さんはその山村に入り込み、カメラを回しながら村人と生活を共にし、ダム建設反対運動にコミットしていったそうです。しかしそのスタイルを、今村さんは「作品の中にそこまで入ってはダメだ」と批判。白熱する議論、丁々発止のやりとりを、私は必死で英訳しました。
当然の話ですが、いかなる「ドキュメンタリー」でも撮る側と撮られる側がいます。そしてカメラを構えた時点で、「それ以前の状況」がそのまま維持されることは絶対にない。撮影者が状況に介入すれば客観性が損なわれるのはもちろん、そうでなくとも、カメラを向けられた時点で相手が"自己演出"を始めることも多々あるからです。
量子力学において量子を観測しようとすると、観測という行為によって量子の状態が変わってしまうのと同じように、撮影という行為自体が現実を変えてしまうわけです。今村さんと姫田さんはスタンスこそ違うものの、そうした構造的問題と向き合い、悩みながら多くの作品を残してきた――その生々しい現実を知り、私はドキュメンタリーに興味を持つようになりました。
誰もがスマホでインスタントに映像を撮れる現代は、過剰な"自己演出"の時代です。悪い言い方をすれば、撮る側が見せたい自分、信じさせたい物語に、受け取る側が自分好みのエモさや正義を投影し、勝手に感動している。これはかなり危険なことではないでしょうか。
映えないもの、退屈なものを辛抱強く深掘りすること。耳の痛い話を"ノイキャン"しないこと。気にも留めない、時間の無駄だからスルーする、という反応をする方が大半かもしれませんが、アルゴリズムに支配された瞬間的な反応の繰り返しばかりに日々を費やすことと、どちらが健全でしょうか。
一見つまらなそうなものでも「掘れば何かあるかもしれない」と関心領域を拡張していくことが、人生を面白くする上で大切なことだと私は思います。
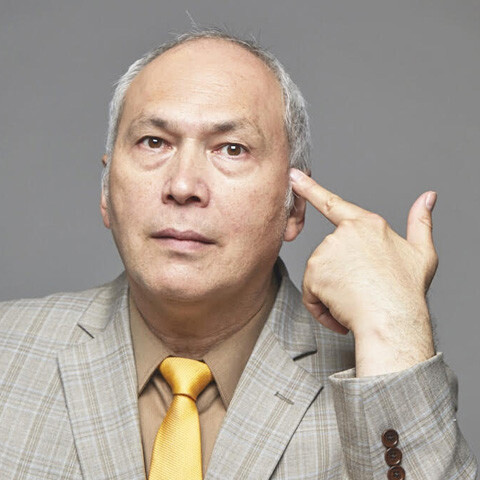
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)