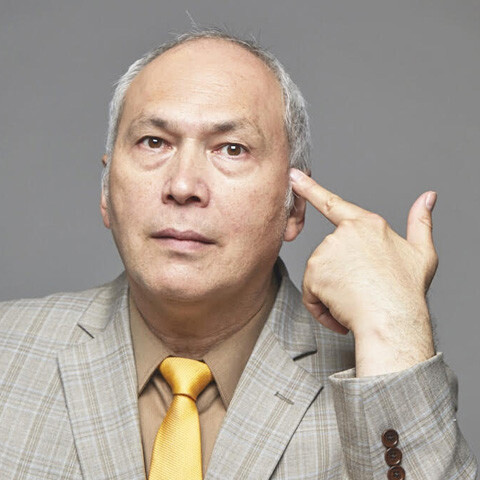
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
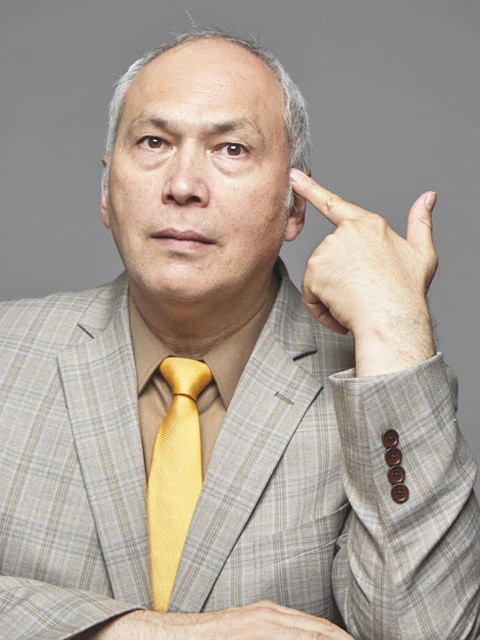 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、いまだに「暗記と定石の応用」を評価の中心軸としている日本の教育に対ついて考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、いまだに「暗記と定石の応用」を評価の中心軸としている日本の教育に対ついて考察する。
* * *
日本ではまさに今が大学入試シーズンですが、入試というと、私はアメリカの大学進学適性試験「SAT」を巡って起きた1982年の"事件"を思い出します。ある数学の問題に欠陥があり、全米規模の大ニュースとなったのです。
【小さな円と、半径がその3倍の大きな円が接しています。大きな円の円周に沿って小さな円を元の位置に戻るまで転がしていったとき、小さな円は何回転するでしょうか?】
多くの受験者は、半径が3倍なら円周の長さも当然3倍だということから「3回」と答えました。そして、当初は出題側もそれを正解としました。ところが――後日、3人の受験生が「正解は4回である」と異議を唱えました。「円周の長さは確かに3倍だが、それに加え、小さな円が大きな円の円周上を転がる動作そのものによってさらに1回転する」というのです。
あらためて出題側が検証すると、確かに正解は「4回」であることが判明しました(まったく同じ大きさの硬貨ふたつを使ってこの動きを再現してみると、同様の理由で「2回転」することがわかります)。この"スキャンダル"はニューヨーク・タイムズなどにも報じられ、試験システムの信頼性に一石を投じることになりました。
出題側が"試験テクニックの常識"にとらわれて詳細な検証をせず、間違った解答を設定したこと。そして、今まで習ったルールの延長線上にはないその"わな"を見破った3人が、いずれも単なる詰め込み型ではない高等な理数教育を受けていたこと――これらの事実は、「教育とは何か?」という根本的な問いを投げかけているように思います。
これは40年以上も前の事件ですが、おそらく今でも、日本の旧態依然とした教育構造からは、このような問題の前提そのものを疑い、"新しい正解"を探そうとする子は出てこないのではないでしょうか。
ハーバード大学のマイケル・サンデル教授(政治哲学)は近年、「能力主義」の問題点を指摘し続けています。能力主義の前提には「公平な競争」があるはずだが、実際には多くの場合、現代における「成功」は格差が固定化された社会構造の結果に過ぎない。こうした能力主義は社会に分断を生む上、失敗した人々を「努力が足りないだけ」と不当な自己責任論に追い込んでいる――と。
サンデル教授の主眼はアメリカの白人エリート層への警鐘ですが、日本でも、受験に成功した人ほどそれを完全に「自分の努力の結果」だと思いがちでしょう。成功の背後に、家庭環境や生まれ育った地域など、努力以外のさまざまなファクターがあることを無意識のうちに切り捨ててしまうのです。
能力主義がグローバリズムと結びつきつつある現代社会では、地球規模での競争がますます激化するはずです。そんな中で、日本の教育が旧態依然とした、暗記と定石中心の応用力を評価するシステムにとどまっていいのか。また、改革を進めるにしても、そこに能力主義以外の価値観をどう埋め込んでいくのか。
未来の教育とは「未知の課題に挑む力」を養うものであるべきですが、その理想にどうすれば近づけるのか。これは極めて難題であり、しかし、決して避けては通れない問題であるといえるでしょう。
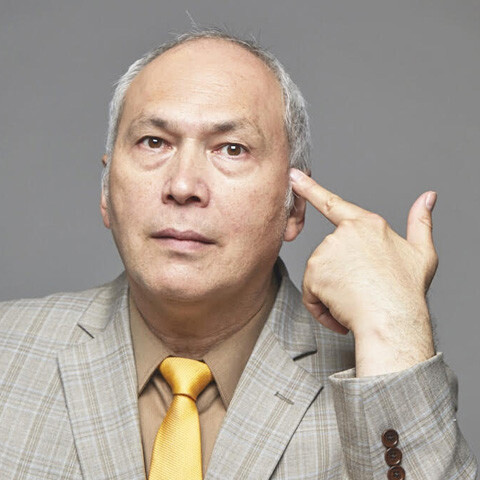
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)