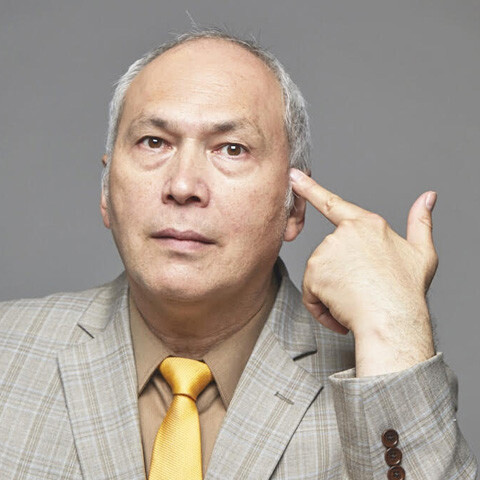
モーリー・ロバートソンMorley Robertson
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)
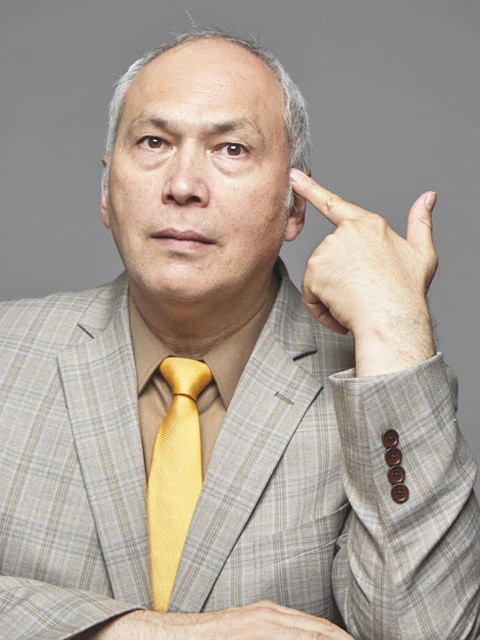 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、沖縄の米軍基地に隣接する街を訪れた経験から、日本社会が前進するための「常識の転換」について考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、沖縄の米軍基地に隣接する街を訪れた経験から、日本社会が前進するための「常識の転換」について考察する。
* * *
先日、テレビ番組のロケで沖縄県のコザ(沖縄市中心部)を訪れました。広大な米空軍嘉手納(かでな)飛行場に隣接し、1970年には米施政への怒りから民衆が米軍関係車両や施設を焼き打ちにした「コザ騒動」があったことでも知られる土地です。
街を歩いて感じたのは、基地問題への賛否を超えて米兵と共に暮らす人々の生活、歴史、文化が交差する混沌(カオス)から生まれたストリートの"リアル"です。"アメラジアン"と呼ばれることもある、米兵と現地住民の間に生まれたであろう若い世代の人たちともあちこちですれ違いました。
彼ら・彼女らの多くは、日本語の合間に無意識のうちに英語が交ざり込むような、独特な話し方をします。もちろん「地元」やインターナショナルスクールなどの環境にうまく溶け込む人も大勢いる一方、アイデンティティや言語の壁の問題から同世代のコミュニティで孤立してしまうケースもあり、中には自己肯定感を持てないまま生きている人もいると聞きました。
時代も環境も違うので簡単に「同じ」とは言えませんが、アメリカ人の父と日本人の母を持つ私も「標準」とは異なるバックボーンを持ち、アイデンティティに揺れる少年時代を過ごしました。その記憶をたどりつつ、日本社会がいまだに均質化・標準化を求める構造を維持していることをあらためて認識しました。
また一方で、近代以降、日本政府が"同化"を求め続けた歴史もあり、沖縄の土着の言語である「うちなーぐち」を日常的に話す若者が急激に減っているという現状もあります。異質なものを許容しない日本社会の問題として、アメラジアンの子供が居場所を見つけづらいことと通底する構造があるように思えました。
経済合理性のために求めた同化、すなわち「標準化」は、戦後の日本が欧米先進国(当時の戦勝国)にキャッチアップする環境下ではプラスに作用し、高度経済成長期に国力を押し上げる効果を持ちました。しかし、今の時代において「標準化」を進めることは、30億人を超える母数の新興国の人々と同一線上で競争に立つことを意味します。
均質な社会で受動的な仕事に励み、変化や「出る杭」に対して潔癖であることは、付加価値を生むどころかイノベーションを阻害する方向に作用してしまいます。これが昨今の日本の「衰退」を後押ししている主要因だと思います。
政治や教育がこの環境、時代の変化と向き合わず、「波風を立てず、なおかつ自助努力でイノベーションを起こせ」と言うのは虫がよすぎる話でしょう。
新しい価値観や文化の魅力、そこから派生する新しい経済は、現在の社会に対して従順な"行儀のいい人たち"からは生まれません。
1年半ほど前にこのコラムでもご紹介したアメリカの新世代の黒人女性ラッパー、Sexxy Red(セクシー・レッド)はその後、ヒップホップコミュニティのニュースターという枠を優に飛び越え、今年1月にはブルーノ・マーズとのコラボ楽曲を発表。そのMVにはレディー・ガガも出演しました。また、ルイ・ヴィトンやグッチといったハイブランドも、かつてなら考えられないほど広告モデルに起用する人物の「幅」を広げています。
強めの感情移入も込みで言わせていただきます。これからの時代、アメラジアンはアメラジアンの言葉、アメラジアンの自分のままで生きたほうがいい。この話は沖縄に限ったことではありません。日本中で「主流」から外れて寂しい思いをしている人は、まず今一度あるがままの自分に手応えを見出した上で、あらためてどう社会と付き合うかを選んだ方がいい。
その結果、これまで「主流」だったものが「アメラジアン化」するような混沌(カオス)が生まれたほうが、むしろ社会は活性化し、前に進むことになるでしょう。
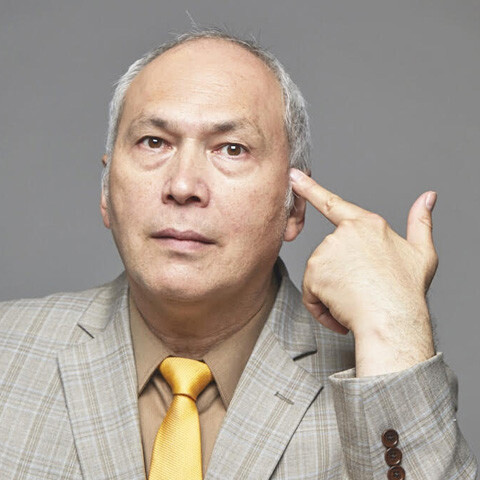
国際ジャーナリスト、ミュージシャン。1963年生まれ、米ニューヨーク出身。ニュース解説、コメンテーターなどでのメディア出演多数。最新刊は『日本、ヤバい。「いいね」と「コスパ」を捨てる新しい生き方のススメ』(文藝春秋)