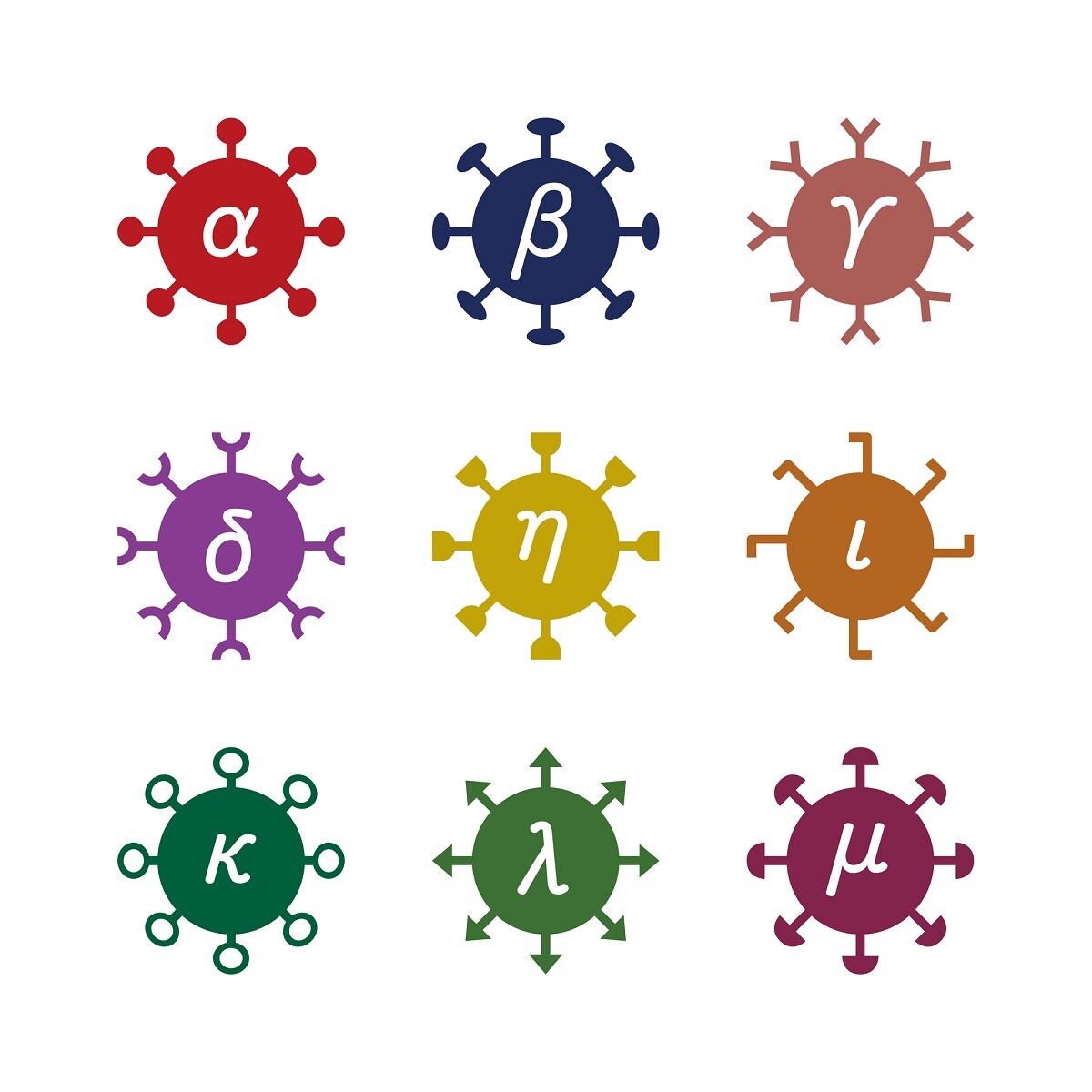アルファ株、ベータ株、ガンマ株......。2021年の春、世界保健機関(WHO)は、流行拡大する変異株にギリシャ文字の名前をつけることを決めた
アルファ株、ベータ株、ガンマ株......。2021年の春、世界保健機関(WHO)は、流行拡大する変異株にギリシャ文字の名前をつけることを決めた
連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第45話
これまで新型コロナ研究で数々の成果を上げてきたG2P-Japan。しかし、そのすべてが順風満帆に進んだわけではない。今回は、数ある中でも筆者の印象に残っている「ラムダ株」と「ミュー株」の研究を振り返り、そこから得た教訓について述べる。
* * *
■「ラムダ株」と「ミュー株」
この連載コラムではこれまで、新型コロナ研究コンソーシアム「G2P-Japan」の成功例ばかりをフィーチャーして紹介してきた。しかしもちろん、研究というのはそんなに順風満帆なことばかりではない。
平時の(通常の)研究活動というのは、時間をかけても研究対象の真実を追求することに執心するのが基本スタンスである。それに対し、「新型コロナパンデミックの中での新型コロナ変異株の研究」のような有事の研究活動は、「ある変異株の特性・性質」という研究対象が、社会の関心とオーバーラップすることによって発生する。
そのため、その研究対象に社会の関心が集まっている場合にのみ、それを解明することの社会的インパクトが高まる。30話では、このような平時の研究と有事の研究のスタンスの違いを、それぞれ「カーリングとボッチャ」というスポーツに喩えて紹介した。
「ポッチャというスポーツをカーリングのルールでプレーしてはいけない」、つまり、「有事の研究に平時の研究のノリで取り組んではいけない」ということなのだが、今回のコラムでは、この切り替えに失敗した「ラムダ株」の研究の話と、その逆に大成功を収めた「ミュー株」の研究の話を紹介する。
ラムダ株とミュー株は、どちらも2021年夏頃に出現した、「注目すべき変異株(VOI: variant of interest)」に分類された変異株である。
2021年の春、世界保健機関(WHO)が、流行拡大する変異株にギリシャ文字の名前をつけることを決めた。アルファ株、ベータ株、ガンマ株。すでに見つかっていた"ヤバいやつら"にはすぐに名前がつけられた。
そして、名前がつけられた株は、その流行規模や流行ポテンシャルなどからクラス分けされ、パンデミック(世界的大流行)を起こしている、もしくはその可能性がある株を、最高ランクである「懸念すべき変異株(VOC: variant of concern)」として分類した。一方、ある国や地域での限定した流行であるが、将来パンデミックを引き起こす可能性がある株を、「パンデミック予備軍」として「注目すべき変異株(VOI: variant of interest)」に分類した。
余談だが、思い返せばこの命名ルールも、結局は基準がよくわからずじまいであった。6話で紹介した、G2P-Japanの処女作の研究対象となった、当時「カリフォルニア株」と呼んでいた株には、「イプシロン株」というオフィシャルネームがつけられ、これは一時VOIにランクづけされた。
それと時期をほぼ同じくして、アメリカ(特にニューヨーク)などでたくさん見つかっていた変異株たちに、片っ端からゼータ株、イータ株、シータ株、イオタ株、と立て続けに名前がついた。そしてその年の初夏にインドで見つかったのが、VOIに分類されたカッパ株と、VOCに分類され、その後世界中に広がってパンデミックを引き起こしたデルタ株である。
この頃には、ギリシャ文字の名前がつくと、世界中の研究者が注目して研究を開始する、という空気が生まれていたと記憶している。そして、2021年6月14日、WHOは、南米の、特にペルーやエクアドルで流行拡大していた株に、「ラムダ株」という名前をつけた。これによってこの株に世界中の研究者の注目が一斉に集まり、研究競争が始まる。
■泥沼にはまった「ラムダ株」
われわれG2P-Japanもその例に漏れず、ラムダ株の研究を開始する。しかし、実験結果があまり判然としない。これといった特徴がないのである。VOIに分類されるほどの株であるのだから、なにかしらコレという特徴があるはずであるが、それがどうにも見つからない。それはいったいなぜか? 着眼点がよくないのか? 他の切り口はないのか?
...と、別の切り口から検証できることがないかをいろいろ考える中で、ふとあることを思い出した。
2020年春の新型コロナの最初の研究で連携したことがある、パウル・カルデナス(Paul Cardenas)という研究者がたしか、エクアドルにいたはずだ(38話に登場)。事前情報によれば、ラムダ株は、エクアドルを含めた南米の国々で流行拡大しているという。エクアドルにいる彼ならば、研究の役に立つ何かを持っているのではないかと思い、およそ1年ぶりに、パウルにメールを送ってみた。いろいろと相談する中で、ラムダ株に感染した人の検体提供を頼んでみることにした。
しかし、エクアドルから臨床検体を輸出するためのハードルは想像以上に高く、エクアドル政府からその承認を得るために、いろいろな書類を集めるハメになった。たとえば、「東京大学が国立の教育機関であることを証明する書類」を要求されたり(ちなみにこれは、文科省に事情を説明して、証明書を作ってもらうことができた)。
これらの事務手続きにかなり時間と手間を取られてしまい、ラムダ株のプロジェクトは、泥沼に脚がはまったように身動きがとれなくなってしまう。
この頃にはまだ、「カーリングとボッチャの切り替え」という発想がなかった。「急いだ方が良いが、科学論文にはインパクトも必要。そのためには、多少なりとも腰を据えることもやむを得ない――」。そういう、カーリングともボッチャともつかない曖昧なスタンスで進めてしまったラムダ株の研究は、結局コレというパンチに欠けたまま時間だけが過ぎてしまい、論文としての「旬」を逃してしまった。
もちろん最終的には、ひとつの論文として研究成果をまとめることはできた。しかし、G2P-Japanの処女作の研究対象となったイプシロン株(6話)や、ラムダ株とほぼ同時に研究を開始して、トップジャーナルである『ネイチャー』に発表したデルタ株の研究のインパクトに比べると、それらの影に霞む形となってしまった。
■「ミュー株」の研究で得た教訓
しかし、ラムダ株の研究を進めたことで得られた僥倖もあった。ラムダ株の次にVOIに認定されたのは、これまた南米で流行を広げていたミュー株である。この株は、8月30日にWHOによって命名された。そしてこれまでの例に漏れず、この日から世界中で研究競争の幕が切って落とされた訳である。
しかしわれわれは、WHOが命名したわずか6日後の9月5日に、ミュー株についての研究成果をプレプリント(査読前論文)として公表した。それをツイッター(現X)で拡散すると、世界中からものすごい反響があった。それはそうである。なぜなら、ミュー株の研究に取り組もうと準備していた世界中の研究者の99.9%は、まだ研究に必要な実験材料の準備さえできていなかっただろうから。
それならばなぜ、われわれはそんなことができたのか? 数日必要な実験ステップがいくつかあるので、いくら頑張っても、研究開始から6日で論文をまとめることは原理的に不可能である。その鍵は、実はラムダ株の研究の中にあった。
このコラムの冒頭で述べた通り、私はラムダ株についての情報収集のために、エクアドルのサンフランシスコ・デ・キト大学というところに在籍する、パウル・カルデナス医師にコンタクトを取っていた。彼とやりとりをする中で、パウルは私に、こんなことを教えてくれたのである。
「ケイ、ラムダ株が気になるのもわかるが、実はこっちでは、まだギリシャ文字のオフィシャルネームがついていない変異株の流行が進んでいる。その変異株の研究の準備を進めておいた方が良い――」。
パウルからこの情報を得たのが7月24日。その変異株には、「B.1.621」というコードネームがついていた。パウルのアドバイスにしたがって、翌日の25日には、B.1.621株の実験材料を揃え始めた。そしてそれからひと月ほどが経った8月29日に、この実験を担当していた大学院生(当時)のUが、私のところに実験結果の報告に来る。
「先生、この株(B.1.621株)に、ワクチン接種者の中和抗体が全然効きません――」。
奇しくも、WHOがB.1.621株に「ミュー」と名前をつけたのは、その翌日のことであった。つまりわれわれは、WHOが命名する前日に、この株についての実験結果をすでに得ていたのである。あとはその結果を追試して確認し、論文にまとめるだけだった。
これが、今でも巷で語り継がれる、「ミュー株」の神速論文の顛末である。この論文は査読も順調に進み、9月28日に、医学雑誌の最高峰である『ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディスン』に採択された。
ここで得られた教訓はこうである。パンデミックという世界的な有事に取り組むためには、研究を遂行するスピードやモチベーションはもちろん大事だが、それだけでは解決できないこともある。
それは、パウルがB.1.621株(のちのミュー株)のことを私に私信してくれたように、世界のいろいろな国とつながりを持つことである。パウルとは面識もないし、オンラインで話したこともないが、不思議な縁でつながることができたことにとても感謝している。
★不定期連載『「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常』記事一覧★