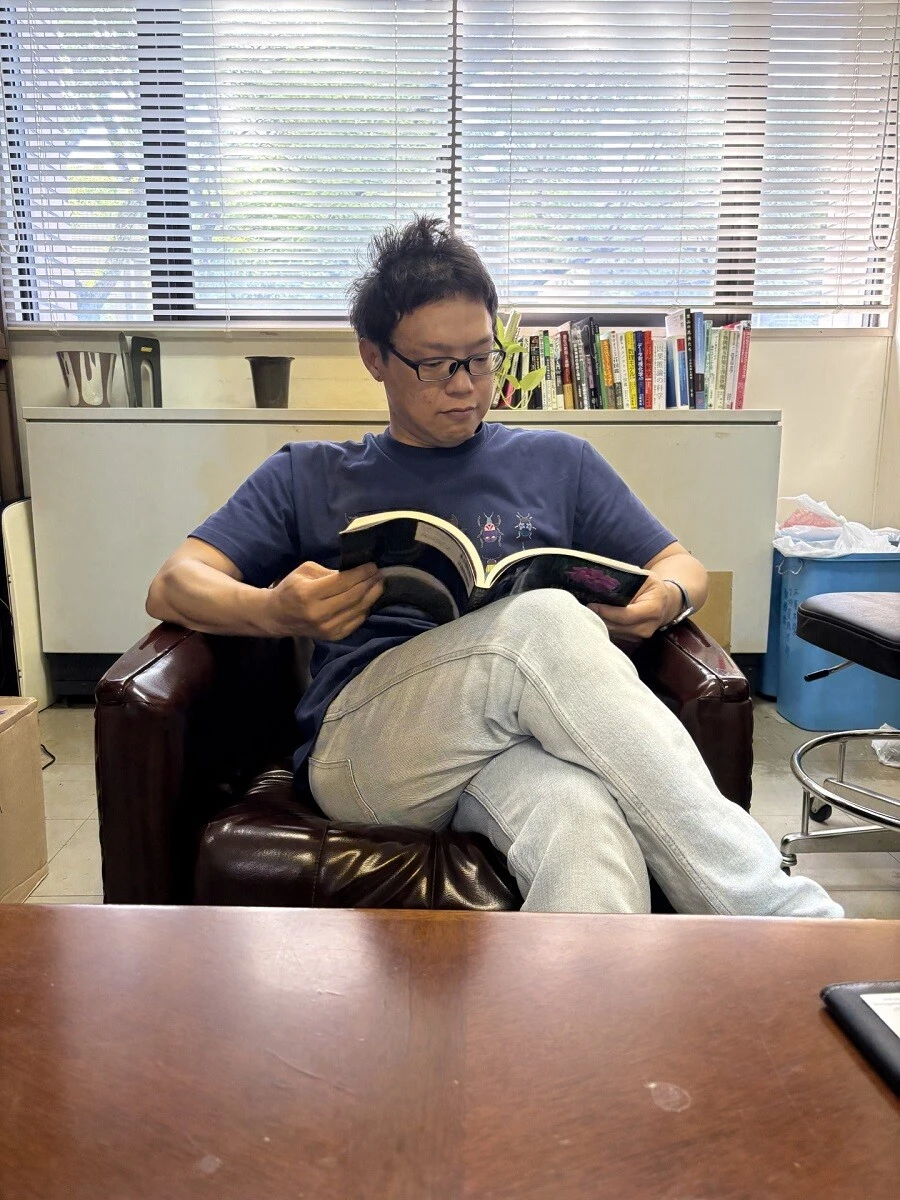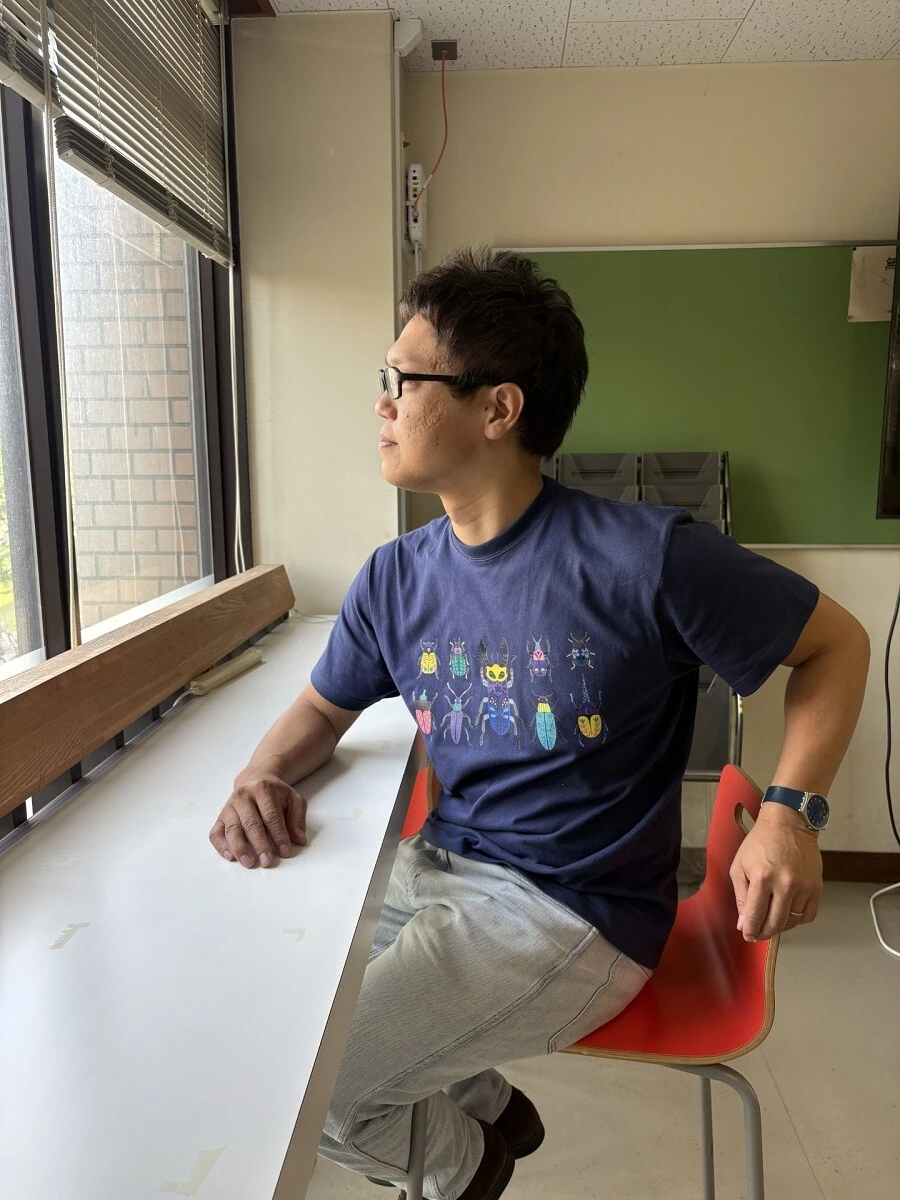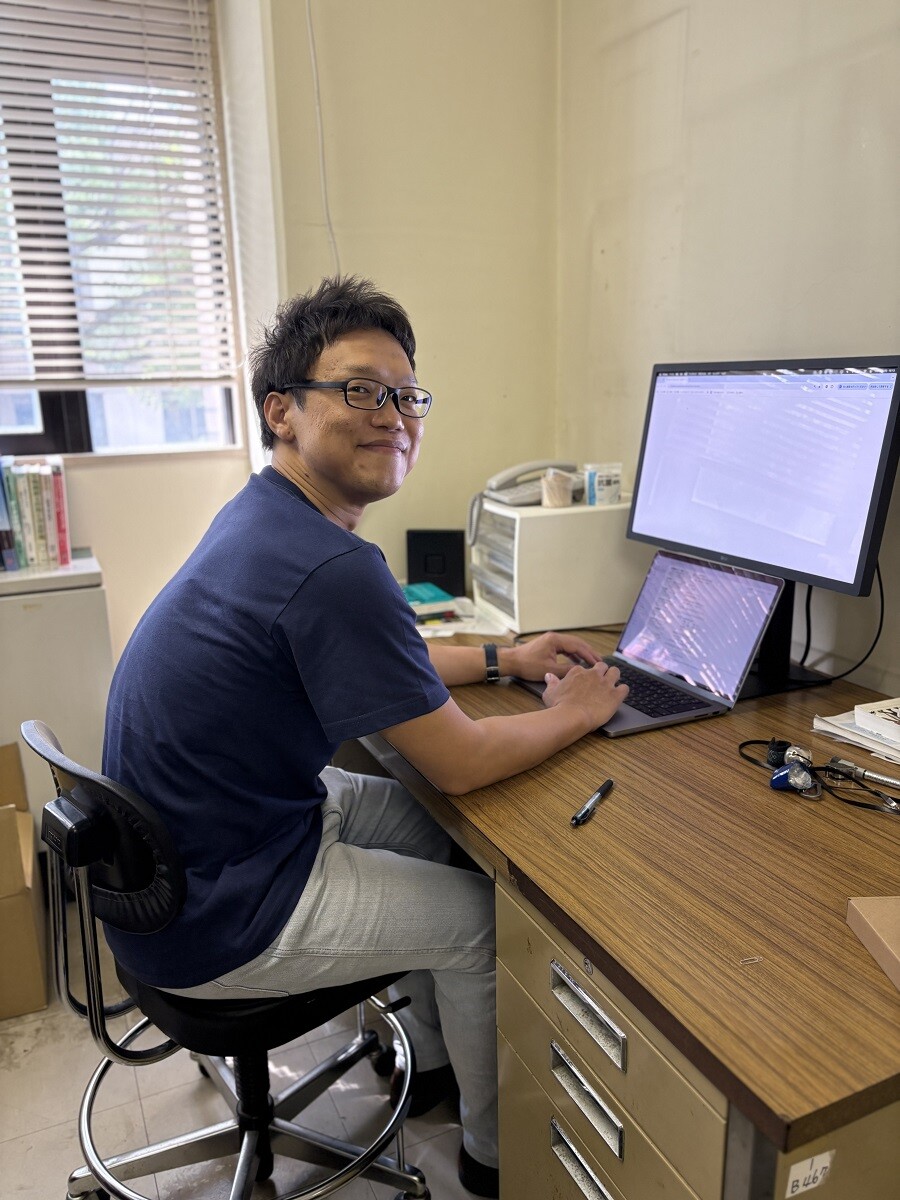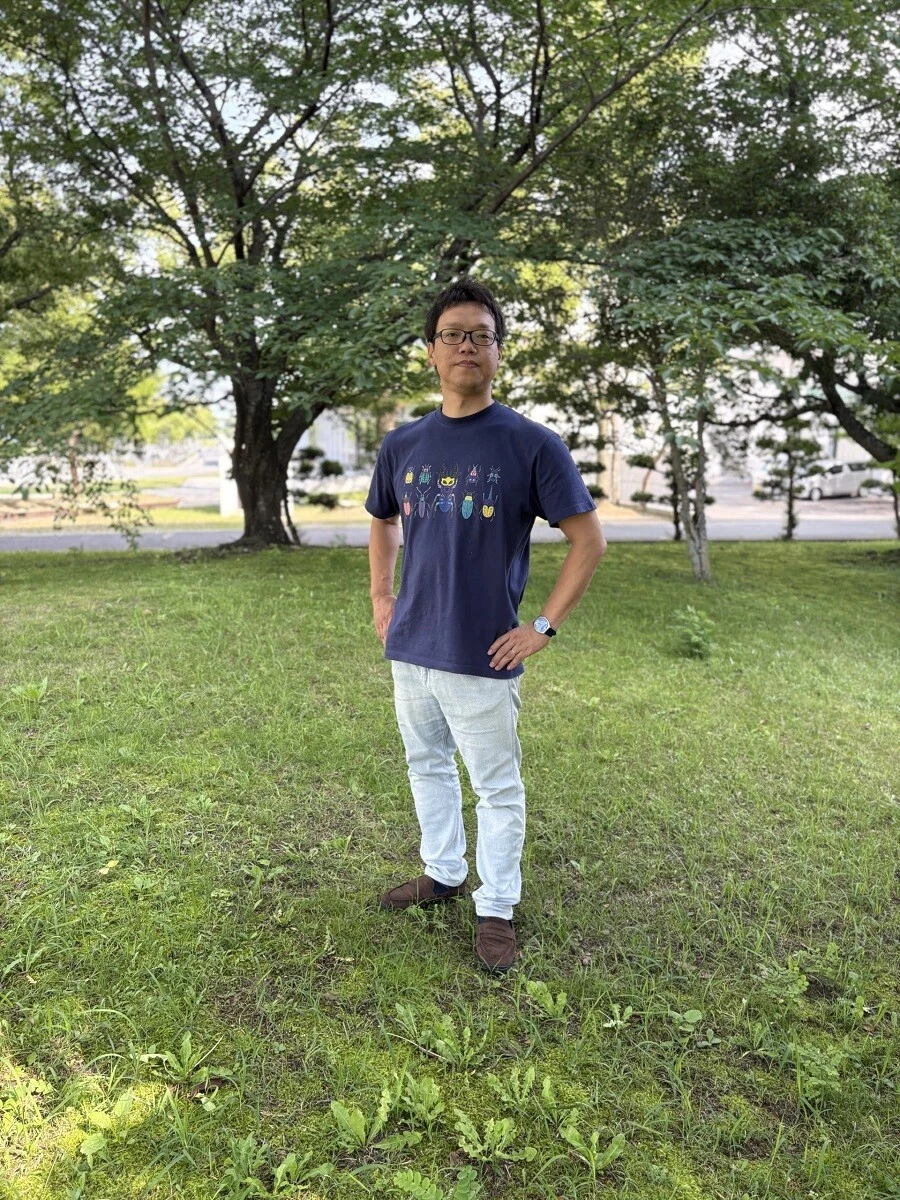ひろゆき (西村博之)
にしむら・ひろゆき
ひろゆき (西村博之)の記事一覧
1976年生まれ、神奈川県出身。元『2ちゃんねる』管理人。近著に『生か、死か、お金か』(共著、集英社インターナショナル)など
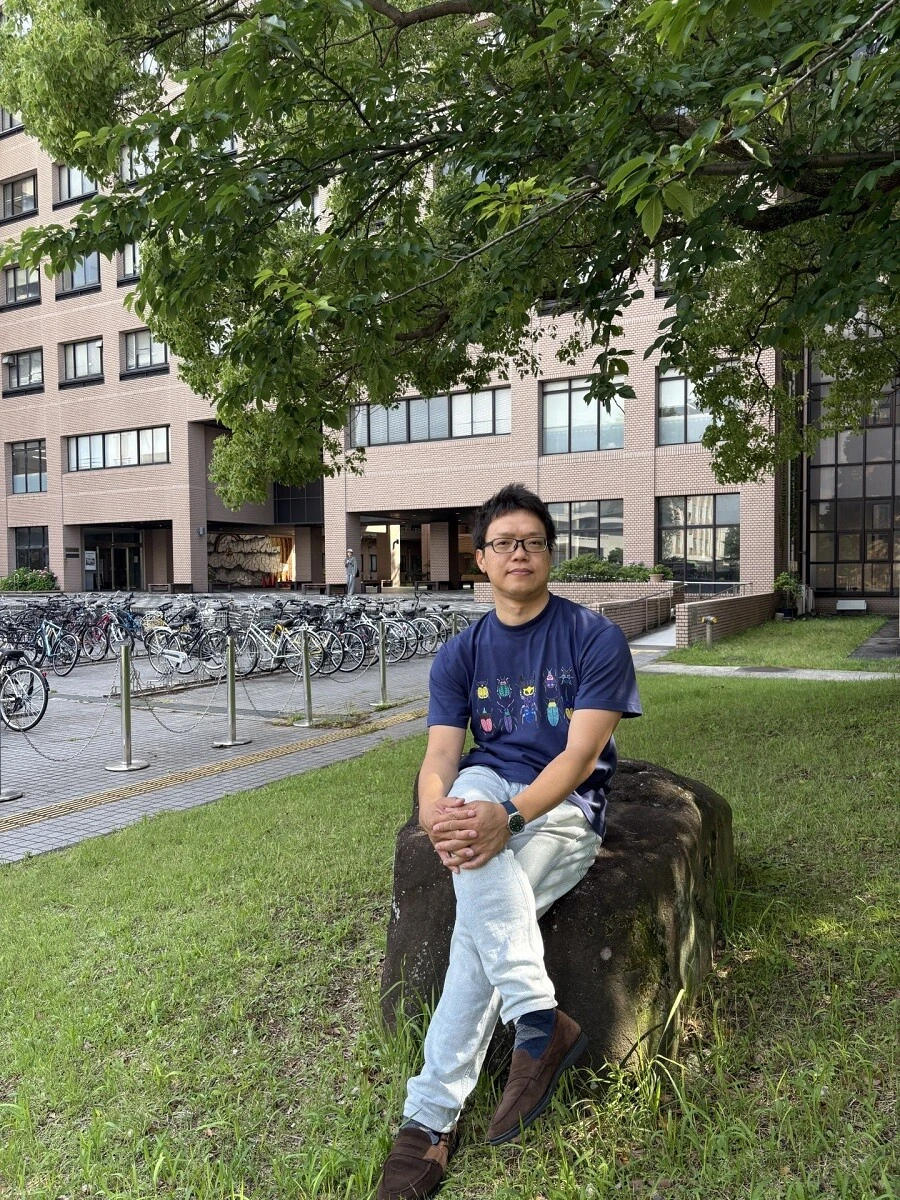 「ダーウィンが進化論の根幹を成す『自然選択説』を思いついたのは、20代後半から30代前半です。」そう語る鈴木紀之先生
「ダーウィンが進化論の根幹を成す『自然選択説』を思いついたのは、20代後半から30代前半です。」そう語る鈴木紀之先生
ひろゆきがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。進化生態学者の鈴木紀之先生をゲストに迎えた11回目も、前回に引き続き〝進化論の父〟ダーウィンについてです。
今となっては当然のことのように思いますが、ダーウィンはいつ頃、どのようにして進化論という考え方を思いついたのでしょうか。知られざるダーウィンの人生を教えてもらいました。
***
ひろゆき(以下、ひろ) ダーウィンはどうやって進化論にたどり着いたんですか? よく「ガラパゴス諸島のフィンチという鳥のくちばし」がきっかけだったといわれますよね。
鈴木紀之(以下、鈴木) まず、その有名なガラパゴスフィンチの話からご説明しますね。ガラパゴス諸島には十数種類のフィンチがいて、住む島や食べるエサの違いによって、くちばしの形や大きさが変わっているんです。硬い実を食べる種は太いくちばし。花の蜜を吸う種は細長いくちばしといった具合です。
ひろ はいはい。
鈴木 今の研究でわかっているのは、元は1種類の祖先から始まって、島ごとの環境に適応するうちに十数種類へと分かれていったということ。これは「種の分化」の典型例として、生物学の教科書に必ず載るものです。「ダーウィンフィンチ」という愛称で呼ばれ、ニュートンのリンゴのように科学史のアイコンになっています。ところが、ダーウィン自身はガラパゴス滞在中にフィンチを熱心に研究したわけではないんですよ。
ひろ え、そうなんですか!?
鈴木 それどころか、彼が書いた『種の起源』には、フィンチに関する記述はほとんど登場しません。当時の記録を調べると、彼は島ごとにくちばしの形が違うという重要な事実にさえ気づいていなかったようです。その事実に気づいたのは、ビーグル号の航海を終えてイギリスに帰国した後でした。持ち帰った標本を鳥類学者に見せたところ「これらはすべてフィンチの仲間だが、島ごとに驚くほど多様な種が存在する」と指摘され、初めてその重要性を認識しました。
ひろ 本人はリアルタイムで気づいていなかったんだ(笑)。
鈴木 現在のようにダーウィンフィンチが進化論の象徴となったのはダーウィンの死後、多くの研究者たちがガラパゴスで研究を重ね、その重要性を明らかにした結果です。ですから、「ダーウィンフィンチ」という名前も後世の研究者たちが名づけたものです。
ひろ じゃあ、ダーウィンが進化論のアイデアをひらめいた瞬間っていつなんですか?
鈴木 「この瞬間」と言えるタイミングはないと思います。ビーグル号の世界一周航海は約5年に及びましたが、ガラパゴス諸島に立ち寄ったのは出発から3年ほど経過した頃で、滞在期間もわずかでした。航海の大部分は南米大陸の沿岸調査に費やされていたんです。
ひろ ガラパゴス諸島に上陸したダーウィンが雷に打たれたように進化論を思いついた......みたいなエピソードだったらドラマチックなんですけどね(笑)。
鈴木 実際はもっと複雑です。そもそも進化論というのは、ひとつの発見で成立するような単純な理論ではありません。地質学、古生物学、比較解剖学、発生学など無数の証拠によって支えられた巨大な枠組みなんです。
ひろ じゃあ、ニュートンが「落ちるリンゴを見て万有引力の法則をひらめいた」みたいな決定的なタイミングはないんですね。
鈴木 ええ。「いつ完成したのか」という問いに答えるのは非常に難しいです。
ひろ もうひとつ気になるのは、ダーウィンのモチベーションです。そこまで徹底的に科学的な業績にこだわった理由ってなんですか? 世間からチヤホヤされたいなら、裕福な家の出身ですし社交界に顔を出せばよかったはず。
鈴木 むしろ彼は、生涯のほとんどをロンドン郊外の自宅で研究に没頭して過ごしました。
ひろ だとすると、承認欲求とは違うもっと別の動機があったと。
鈴木 そうだと思います。彼には「純粋に真理を探究したい」という研究者としての本能的な欲求があったと思います。
ひろ でも、「自分だけが真理を理解していればいい」という考え方だってありますよね。
鈴木 ここでも面白い話があるんです。ダーウィンが進化論の根幹を成す「自然選択説」というアイデアを思いついたのは、航海から戻った後の20代後半から30代前半の頃でした。しかし、その理論は当時絶対的な権威を持っていたキリスト教の「万物は神が創造した」という創造論を根底から覆すものです。
ひろ 社会を敵に回すようなものですよね。
鈴木 だから、発表することは長年ためらっていたみたいです。原稿の要約は書き上げていたものの、それは家の中にしまい込まれ、「自分が死んだ後に出版してくれればいい」とさえ考えていたようです。
ところが事態は急変します。ダーウィンが50歳になろうかという頃、彼より1世代若いアルフレッド・ラッセル・ウォレスという学者が、ダーウィンとまったく同じ進化のメカニズムを独自に思いついたんです。
ひろ ダーウィンは焦ったんじゃないですか(笑)。
鈴木 しかも、すでに科学者として有名だったダーウィンに意見を求めるため、その理論をまとめた論文を郵送してきた。科学の世界では誰が最初に発見や発表をしたかが重要視されます。
ひろ このままでは、自分が20年間温めてきた理論がウォレスのものになってしまうと。
鈴木 そこで彼は急遽、自身の理論を発表する準備を始めました。
ひろ でも、ウォレスからすれば、たまったものじゃないですよね。自分の発見について相談した相手が、30年分のとんでもない研究成果を後から出してきたわけですから(笑)。
鈴木 ここが非常にドラマチックな場面です。ダーウィンはすでにイギリスの科学界で重鎮としての地位を確立していましたが、一方のウォレスはまだ無名の若手研究者。そこでダーウィンは、ウォレスの論文と自分が過去に書いていた論考を同時に発表するという方法を取りました。どちらか一方が抜け駆けしたという形にならないよう配慮したんです。これが、進化論が世に出た公式の瞬間となります。
ひろ ほうほう。
鈴木 しかし、その直後にダーウィンは、長年の研究をまとめた大著『種の起源』を出版します。この圧倒的なボリュームと緻密な論証の前にウォレスの功績はかすんでしまいました。ただ、当のウォレス本人はダーウィンを深く尊敬していたので、特に不満を持ちませんでした。
ひろ まあ、ダーウィンですら発表をためらっていたわけで、若手の自分がひとりで発表してキリスト教や社会を敵に回すよりも、「偉大なダーウィン先生が支持してくれるなら心強い」と考えたのかもですね。
鈴木 ただダーウィン自身はウォレスに対して負い目を感じていたみたいです。ウォレスは富裕層の出身ではなかったので常に生活費に困っていました。そこでダーウィンは政府に働きかけてウォレスに終身年金が給付されるよう取り計らうなど経済的な支援をしていたんです。
ひろ じゃあ、結果的にはウォレスにとってもいい形で歴史に名が残ったんですね。
鈴木 そう言えると思います。
***
■西村博之(Hiroyuki NISHIMURA)
元『2ちゃんねる』管理人。近著に『生か、死か、お金か』(共著、集英社インターナショナル)など
■鈴木紀之(Noriyuki SUZUKI)
1984年生まれ。進化生態学者。三重大学准教授。主な著書に「すごい進化『一見すると不合理』の謎を解く」「ダーウィン『進化論の父』の大いなる遺産」(共に中公新書)などがある。公式Xは「@fvgnoriyuki」