
加藤ジャンプかとうじゃんぷ
文筆家。コの字酒場探検家、ポテサラ探求家、ソース研究家。1971年生まれ、東京都出身。東南アジアと横浜育ち。一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。出版社勤務を経てフリーに。著書に『コの字酒場はワンダーランド』『今夜はコの字で 完全版』(土山しげる・画)などがある。BSテレ東のドラマ「今夜はコの字で」の原作をつとめる。これまでに訪れたコの字酒場は数百軒。集英社インターナショナルのnoteで「今夜はコの字で~全国コの字酒場漂流記~」連載中。
公式X@katojump
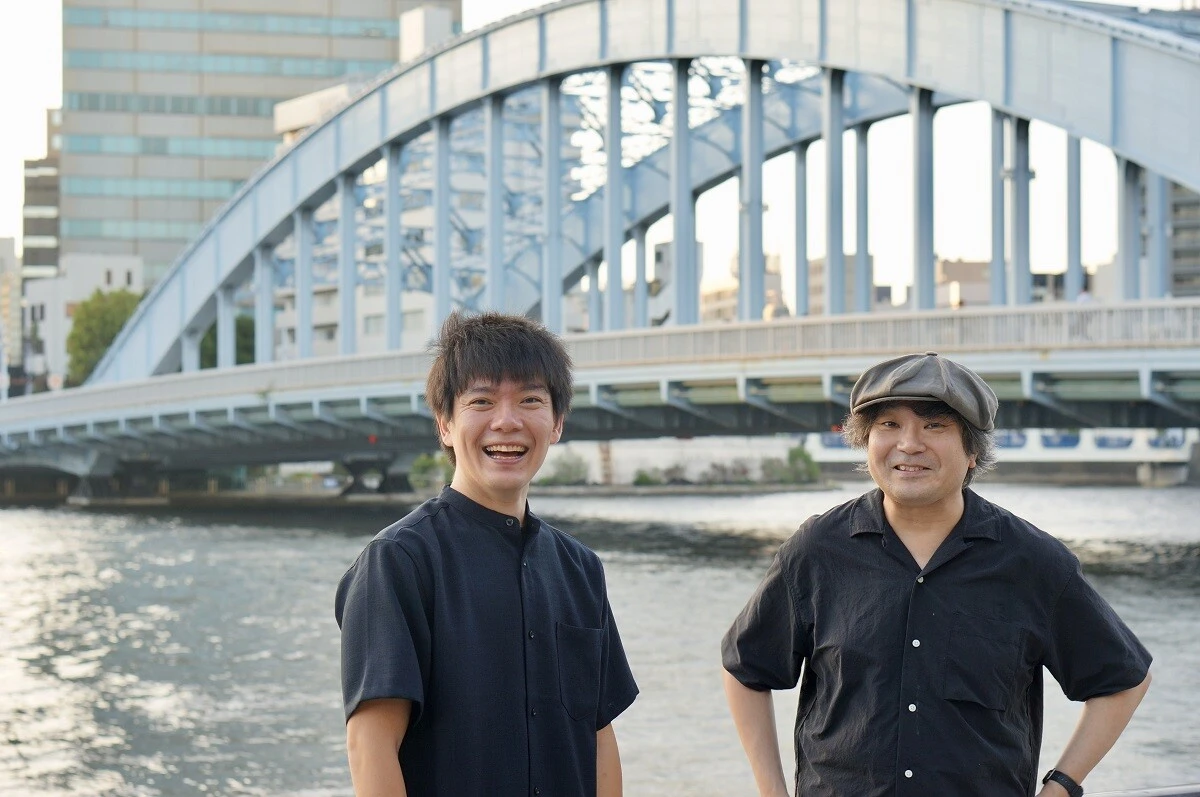 東京・門前仲町にある「創作居酒屋たつや」の店主、佐藤猛さん(左)と加藤ジャンプさん
東京・門前仲町にある「創作居酒屋たつや」の店主、佐藤猛さん(左)と加藤ジャンプさん
客たちの心を癒す天国のような飲食店。そんな名店を切り盛りする大将、女将、もとい店主たちは、どんな店で自分たちを癒しているのか? 店主たちが愛する店はきっと旨いだけの店じゃない。
コの字酒場探検家、ポテサラ探求家などの肩書きで知られ、酒と料理をこよなく愛する文筆家の加藤ジャンプ氏が、名店の店主たち行きつけの店で、店主たちと酒を酌み交わしながらライフヒストリーを聞く連載「店主の休日」。
そこには、知られざる店主たちの半生記と、誰しもが聞きたかった人生のヒントがある......。
* * *
たかさんと待ち合わせたのは永代橋(えいたいばし)の東のたもと、永代公園だった。もう、とうに秋めいていいはずの10月だというのに、やけに暑い夕方。東京メトロの門前仲町(もんぜんなかちょう)駅から、平坦な道を10分ほど歩いただけなのに、待ち合わせの場所に着く頃には汗だくになっていた。
たかさんは、門前仲町駅近くの「創作居酒屋たつや」の二代目だ。「たつや」は間もなく創業20年をむかえる。門前仲町駅周辺、地名でいえば富岡(とみおか)、深川(ふかがわ)、永代、古石場(ふるいしば)界隈は古い店も少なくないが、それでも近頃はチェーン店や入れ替わりの激しい店が増えた。
「たつや」は、そのなかで20年つづいている、旨い居酒屋である。その店の味とサービスをささえているのが若き二代目のたかさんだ。まだ33歳だけれど、この店に出入りするようになってすでに18年のキャリアがある。
「たつや」はここ数年、酒好きの間でめきめきと評判をあげている店だ。それは二代目のたかさんが店の要についたのと、ちょうど轍を一つにする。
定番のメニューはもちろん、いつ行っても新しいメニューがあり、これが、おしなべて、普通の居酒屋のソレの数段上を行く仕上がり。和洋中はおろか、そのほかエスニックなものまで、こだわりなく素材も調理法もとりいれ、結果、しびれるように旨い酒、それもきちっと日本酒のアテに仕上げる。
そういう酒場だから、いつも店は大盛況。お忍びで訪れる著名人もいるとかいないとか。居酒屋好きは知っている、居酒屋好きでなくても聞いたことはある、そんな店なのである。
毎度、この連載の待ち合わせは、主人公たる名店の店主自身が選んだ場所へとおもむく。良い店を切り盛りする店主が選ぶ店。絶対に良い店だし、そこで店主のライフストーリーを聞けば、おのずと口は滑らかになるし、そういう場だからこそ、店主たちから、人生、時々どん詰まりな中年オジサンがもとめている生きるヒントに出会えると思うからだ。
ただ、今回の店主は初めての30代。私よりも20歳近く若い人、下手をしたら息子と父親という年齢差である。店でよく顔をあわせているとはいえ、いざプライベートとなったら、たとえ店主自身のホームグラウンドだとしても、遠慮させてしまうかもしれない。
ならば、待ち合わせのタイミングでは、いつも以上に腰を低く、土下座すれすれくらいの気持ちで会おう......そんな、心の準備をしながら待ち合わせ場所へと急いでいたところ、「たつや」さんは、待ち合わせのはるか前から待ち構えていたらしく、いきなり永代公園の植え込みのかげから出てきて、とびきりの笑顔で手をふって出迎えてくれた。土下座のタイミングは全然なかった。
「いやあ、遠いところまで、ほんとにすみません。でも、(このインタビューに出ることについて)ほんとに僕でいいんですか」
声も顔も滅法明るい。こういう人は、歳の差ぐらいのことで、つまらない遠慮はしない。いや、むしろ、そこにきちっとリスペクトがあるし、言葉遣いも綺麗だから、堂々とはきはき明るくふるまえるのだろう。

〈たかさんに案内されて向かったのは、永代橋の東のたもとにほど近い店「一徹」。たかさんが10年以上通う店である。麻布十番の名店で修行した大将と気さくな女将が営む和食の店である。その夜は、アラカルトでいろいろつまむことにした。ビールで乾杯してカツオの塩たたきをいただく。身質のしっかりとつまったカツオは、丁寧に藁焼きされ香ばしい。塩で食べるから一層、カツオの身の細胞の奥底にひそむ旨みが際立つ。こういう刺身を食べているから、たかさんの、「たつや」の刺身も旨いのだと膝を叩いた〉
いい店だけれど、「一徹」は二十歳の財布にはちょっと敷居が高いような気がしたら、
「若いときから小遣いをためてから、ここぞというときに来てるんです」
という。それを聞き大いに反省した。なにしろスキあらば呑まんという姿勢だから、時折、欲望に負けてふらふらのれんをくぐってしまい、どうにもならない店に行き当たることもある。安いうちだから、その一回のキズは浅くても、積み重ねればそれなりに大怪我である。
飲兵衛にもかかわらず、たかさんのように若くして、ちまちま無駄遣いせず良いうちでしっかり呑むという、きりっとした姿勢をたもてるのは、もはや才覚である。
たかさんの本当の名前は佐藤猛(さとう・たか)さんという。初めて名刺をいただいたときには、タケシだと思ったが、タカと読む。1990年の生まれだ。早生まれだから学年は平成元年組にあたる。生まれは木場(きば)で、育ったのも、この門前仲町界隈。
祖父の代も東京なので江戸っ子である。父は江戸川区育ちで、母は中国の哈爾賓(ハルビン)の出身なので、幼いころから「(中国語は)聞くのはわかるんですけど、話すのはおいつかないくらいに」。
バイリンガルである。近隣には海外から来た子どもたちも暮らしていて、皆いりまじって元気に育った。小学校と中学校は地元の公立校に通い、高校に進学。そのとき、事件がおこった。
「父は築地(つきじ)で仲卸、母は中国から来て蕎麦屋さんに勤めていたんです。それがある日、突然、「今度、店をやるから」って父が言い出したんです。え、ってなって。ぼくが高校一年のときでした」
2005年だった。たかさんは、まだ15歳だった。一体なぜ、父が店を開いたのか、たかさんにも本当の理由はよくわからないらしい。
父は長年、仲卸しに勤めていたので、良い魚を仕入れるルートはできていた。母は、長年、飲食店にいた経験がある。じゅうぶんに勝算があっての開業だったのだろうが、すでにバブルはとうに崩壊。飲食業、なかでも居酒屋と呼ばれる業態の店は前年よりも数を減らし、飲食につかう金額も減少していた時代だった。
居酒屋もカジュアル化が盛んにいわれるようになり、ファミリー層の利用などが増え、酒よりも食に比重がおかれ始めた時代だ。
そんななかで、完全に酒好きをターゲットにした、言ってみれば昭和のスタイルの居酒屋である「たつや」の船出について、たかさんは今でも厳しい。
「いやあ、もう、景気もよくないのに開いて、ただでさえ厳しい状況だというのに、当時のうちの店は、ほんとうに素人の店だったんですよ。お料理だって品数もすくないし、遅いし、接客も全然不慣れ。もちろん市場とのつながりがあるから、たしかに材料は揃っていたから、なんとなく、そこで打ち消せるところはあったと思います。でも、当たり前だけど材料だけじゃなだめなんですよ」
そんな状況ではあったが、まだ高校生のたかさんは、とりあえず高校生活を満喫していた。いや、サッカー部に所属して、これから満喫しようとしていたところ、
「いきなり父に、店、掃除して、みたいに言われまして。もっと高校生活に没頭したかったですけど、あの頃の店を見たら、とてもそんな気にはなれなかったというか......。父に言われて、そういうことか、と、異論なんて言える余地ないなと思いました。それでサッカー部は半年休部すると伝えて、放課後は店を手伝うようになったんです。それが、店とのかかわりのスタートですね」
ーーそれでサッカーはどうなったんですか?
「そのまま戻りませんでした。ずっと休部です」
たかさんは笑ってふりかえるが、否応なく家業を手伝うことになった高校生の、やるせない思いはいかほどだったろうか。ただ、家業を手伝ったことで、プライベートで良いこともあった。
「部活はできなくなっちゃったんですけど、その頃、同級生の女の子と仲良くなりまして。彼女の実家も江戸川区で古くから青果業を営んでいたんで、いろいろ話が合ったんですよね。当時から、うちの店にごはんを食べに来てくれたりして。で、いまは妻です」
たかさん。苦境のなかでも、おさえるところは、ちゃんとおさえていた。
さて、部活をやめ本格的に店を手伝いはじめたたかさんだったが、当時をふりかえって、
「いや、もう、最初の数年はほんとうにひどかったんですよ。仕組みができあがらないというか、板前さんはいても、なんとなく、覇気の無いメニューで。接客もずっと腰がひけている。十代の僕でもわかるくらい、自信をもってやれていない店だったんですよね」
〈「一徹」の大将は、店名にすこし似て、あまり口数は多くない。カウンターの奥で黙々と料理をしている光景が美しいが、客の目にそう映るのは、女将が店内を行き来しつつ、ほどよい距離感を保ちながら接客していることも理由のひとつだろう。ふたりの「プロ」の存在感だ。おそらく、これは、昔の「たつや」の正反対の状況だ......そんなことを考えていると、真鯛刺の焼松茸巻き、が出てきた。歯触りのよい、全身出汁の塊のような真鯛に塩をちょっとつけてスダチをしぼる。そこに、香り高い薄切りの松茸をくるりと巻いてパクリ。スター二人組は喧嘩することなく、美味しい共演を舌の上でくり広げる。松茸とスダチの香り、真鯛の淡白な旨みと松茸の野趣、それぞれが強力に結びつく。旨い〉
素材のたしかさと立地など、「たつや」をめぐる条件自体は悪くはなかった。だから、たかさんいわく"地味に営業がつづいていた"「たつや」だった。お客は来ていたけれど、今のような人気はまったくなかった。たかさんは不安だった。この店、このままどうなるのだろうかーー。
そんなとき、前から勤めていた板前が辞め、厨房に新しい人が入った。そのことで店がちょっと変わった。地味な店に一本筋がとおった......と、たかさんは感じた。ヒゲのおっちゃんという板前だった。おっちゃんというよりは、おじいちゃんという年齢にさしかかった高齢の料理人が「たつや」にやってきたのである。
ヒゲのおっちゃんにつられたのだろうか、たかさんも仕事に熱が入った。ただ、一度、店を継ぐか迷ったことがある。ホールでの 熱心な仕事ぶりは、客の目をひいたのだろう。会計を学んでいた大学も、そろそろ卒業という時期。贔屓にしてくれていた、大企業に勤める常連客から誘われたのだ。
「卒業したら、うちで働かないか、って言ってくださって。収入も安定感も抜群なお話だったんですよね。迷ったんですけど」
何日も悩んでいたが、ある日、ほかの常連客がこう言った。
「サラリーマンとして勤めるのも大変だけど、一から料理を学んで、こういう店を切り盛りすることのほうがずっと大変だし、面白いよ」
店を継ごうという心もちは芽生えていたものの、まだ、どこかパッとしない店の状態に、たかさんも不安をおぼえていた。だから、客からの思わぬリクルーティングには、決まりかけていた気持ちがぐらついていた。でも、「サラリーマンより面白いよ」という一言ですっと心が軽くなったらしい。就職の話は、きっちりと断った。
これで、すっかり晴れやかに店を継いだ......と思いきや、もやもやはつづいた。大学を卒業して正式に「たつや」のスタッフになったものの、ずっとホールの補助、接客の補助などをしていた。
「それが大事なのはわかるんですが、僕としては、厨房で早くヒゲのおっちゃんに教わりたかったんですよね。やっぱり居酒屋の良し悪しは厨房で決まる。そのためには、早く厨房に入りたかったんですよ。もう、おっちゃんも歳もとっていたし、時間がないって」
なにしろヒゲのおっちゃん、は経験豊富な人だった。
「キャバレーのボーイさんから板前まで、飲食のいろんなことをやってきた人で、仙人みたいなヒゲを生やしていました。ヒゲのおっちゃん、って呼んでいたんですが、それまで自分の小料理屋をやっていたのを畳んだそうで、縁あって、うちの板前になったんですよね」
たしかに、この人がやってきて「たつや」は変わった。いや、たかさんも変わった。ヒゲのおっちゃんの仕事ぶりを見て、自分が板前になって、この店を継ぐ、というビジョンがはっきりしたのだ。それなのに、厨房は満席。たかさんが入り込む余地はなかった。じりじりとしつつ、ホールの仕事に励む日々がつづいた。気づけば25歳になっていた。
そんなとき、ヒゲのおっちゃんの補佐役だった板前が店をやめた。今しかない、と思った。チャンスだ。たかさんは、その板前が辞めたその日、築地へと急いだ。むかったのは、道具店。そこで三本の包丁を買った。そして、父のもとにむかった。父をつかまえて、たかさんははっきりと言った。手には三本の包丁を持っていた。不退転の決意を告げたのだ。
 十数年前のたつやの看板。当時は「龍家」だった。現在の店名は、平仮名で「たつや」となっている。写真:佐藤氏提供
十数年前のたつやの看板。当時は「龍家」だった。現在の店名は、平仮名で「たつや」となっている。写真:佐藤氏提供
「店を継ぐ、これからは僕がやる、と夕飯を食べているときに宣言したんです」
ーーお父様の反応は?
「調子にのんな、一人親方になったつもりか、と言われました」
ーーそれで、どうされたんですか?
「父の話はとりあえず胸にしまって、翌日からホールの手伝いはやめて、厨房に腰を据えました」
こうして、ようやくたかさんは「たつや」の厨房に入ることができた。とにかくヒゲのおっちゃんから学ばなくてはならない。意気込むたかさんの目に狂いはなかった。おっちゃんは、やはり只者ではなかったらしい。
「初めて、うちにプロがやってきたんですよね。まあ、なんというか、なんでもプロだったんですよ。ぼくは、お酒も、釣りも、競馬もぜんぶ、ヒゲのおっちゃんに教えてもらったんです。そういうことはつるつる教えてくれるんですけど......」
ーー料理は?
「あんまりはっきりは教えてくれないんですよね。やっぱり昭和の板前なんですよ。でも、そんなこと言ってられないじゃないですか。うちは、材料はよかったから、刺身はそれで、なんとかもっていた。でも、それだけしかない店は、いつか飽きられちゃうんですよね。刺身だってもちろん常に進化しているから、それを見せて実践できれば飽きられないでしょうが、おっちゃんが来るまで、それが無かったんです。
 ヒゲのおっちゃんと共に働いていた8年前のたかさん。写真:佐藤氏提供
ヒゲのおっちゃんと共に働いていた8年前のたかさん。写真:佐藤氏提供
ところが、ヒゲのおっちゃんの包丁さばきを見て、こういうことなんだよな、と圧倒されて。盛り付け一つとっても、同じ刺身でこんなに違うのか、って、あらためて目の前で見せられたんですよね。これはぜったい、この人がいてくれるうちに、誰かが吸収しないといけない。じゃあ誰が吸収するんだといったら、僕しかいない。決して、手取り足取り教えてくれる人じゃなかったけど、僕はもう遠慮なく、ガンガン質問攻めにして、追いかけ回してました」
ヒゲのおっちゃんとの修行の日々は充実していた。初めはたかさんが一方的に積極的だったようだが、弟子の才能に気づいた師匠は、終業時間外にもたかさんに料理の手ほどきをした。さらに、休日にたかさんは、
「どこかで、店を離れて他の店で修行したい気持ちもあったんですよ。でも無理だな、というのもわかってました。だって、ヒゲのおっちゃんも若くないし、いつまでいてくれるかわからない。その状態で店を開けて、もどるまでにガタガタになったら本末転倒ですよね。
 たつやに入社してからお酒の勉強を本格的に始めた。写真:佐藤氏提供
たつやに入社してからお酒の勉強を本格的に始めた。写真:佐藤氏提供
だったら、という気持ちで、時間があれば良い店と言われている店に行って味をたしかめ、自分なりに分析してました。今でも、休みがあったら、他所の店にいって、とにかく旨い肴をためして、いいところを取り入れるようにしてます。教えてくれそうな人には、これどうやってるんですか、って聞いちゃうこともあります」
 今は子どもが小さく以前とは同じようにいかないが、休みの日など時間があれば、奥さん(左)といろいろな店に食べに行って、自分なりの分析、研究をして、良いところは取り入れるようにしている。写真:佐藤氏提供
今は子どもが小さく以前とは同じようにいかないが、休みの日など時間があれば、奥さん(左)といろいろな店に食べに行って、自分なりの分析、研究をして、良いところは取り入れるようにしている。写真:佐藤氏提供
〈そう笑って、たかさんは「一徹」のご主人を見た。「一徹」も、たかさんが勉強を重ねてきた店の一つだ。たしかに、ここは教わりたいメニューだらけだ。たとえばわさびポテトサラダ。マッシュして真っ白に仕上がったジャガイモは一見、シンプル。さりながら一口ふくめば、爽やかなわさびが効きつつ、濃いコクのあるポテトサラダになっている。素材の面白味を活かす手口は、たとえば同じジャガイモでも和牛すき焼きコロッケでは、ほどよく香ばしく、汁気たっぷりに仕立てられた牛肉の、品良い脂を際立たせるのに、ジャガイモが役立っている〉
 コロッケを割ると、中から「すき焼き」が現れる。温泉卵につけていただく
コロッケを割ると、中から「すき焼き」が現れる。温泉卵につけていただく
「煮物を大事にしろ。旨い店っていうのは、刺身より、そこだから」
ヒゲのおっちゃんには、そんなことも言われた。出汁から砂糖の使いかた、素材を活かすことを、あらためて教わった。
「カウンターには一本の川が流れてるんだよ、なんて言われたのもその頃です。客と店の間には、妥協してはいけない、確固たる一線がある、っていう意味だったみたいです。馴れ合いになってはいけないって」
馴れ合いはいけない。お客さんに甘えて、技術が足りないものを出したりしてはいけない、という戒めだったのだろう。それは、まさに、かつて、たかさんが感じた「たつや」からの脱却を示唆した言葉だった。だが、ヒゲのおっちゃんは、こうも言ってくれたという。
「時間がかかってもいいから、ちゃんと学べ。急いでいいことなんかないから、って。これはありがたかったですね。料理に関してちゃんと学ぶこと、って。なんというか、ヒゲのおっちゃんからは、技術そのものも学びましたが、店にかかわる者の姿勢を逐一言葉にしてくれたことが一番の財産だと思います」
そうしてめきめきと腕をあげたたかさん 。ヒゲのおっちゃんが入って個性をもちはじめた店は、たかさんが腕を振るうようになり、完全に覚醒した。かつて「刺身は旨いけれど」という印象の店だったのが、「品数豊富なうえに刺身がとびきり旨い」という店になっていった。
私は地味だったころに一度この店を訪れ、それから数年して店を訪れて驚いた。すでにたかさんがメインになっていた。まるで別の店だった。店には活気があふれ、料理が旨い。代替わりをしてダメになる、という話の多くは単なる先入観だが、ここまで代替わりして劇的に旨くなる店もそうはない。
それにつれ、店全体が活気があるのに、一段落ち着いた空気になっているのにも驚いた。店と客の間に、甘えはない。さりとて、厳しいわけではない。良き距離感の店になっている。
〈「一徹」は、店名のとおりストイックに旨い料理を拵える店だ。だが、決してユーモアがないわけではない。たとえば、この店のスペシャリテと呼ぶべき一品は、プリン体アラモードという。その名のとおり、魚卵に貝類など、痛風一直線とも言える珍味の面々が一堂に介した逸品だ。それぞれが、それなりに主張の強い素材なのに、お互いを消すことなく絶妙なバランスで盛り込まれている。ウニが勝つこともなく、キャビアが負けることもない。旨いものが、束になってかかってくる。それに、うなぎの北京ダック風という品もまた、面白い。香ばしく焼いた鰻を、北京ダックの皮でくるんでいただくのである。つけるのは、これまたそのままでもアテになりそうに旨い味噌ダレ。どちらも遊び心満載にして旨い。店と客とのやりとりの面白さが、こういうところに集約されている〉
コロナのすこし前、ヒゲのおっちゃんは店を去った。高齢が理由だったが、おそらく、たかさんに伝えることを伝えたという手応えもあっての決断だったのではないだろうか。いま、「たつや」は、たかさんが切り盛りし、予約必須な店になった。そして今や、「たつや」イコールたかさん、になった。
「刺身が注目されて、それが中心なのはいいんですが、大事なのは刺身の脇固めかな、と思っています。刺身を目当てに来てくださるのは嬉しいけれど、それに飽きられたらどうするか、って。季節のもの、新しいもの、刺身以外に、いつも面白がってもらえるものをつくるのが大事だなって。そうすると、かえって刺身も一層大事に丁寧にしたくなるんですよね」
かつてこの店には、入り口近くに水槽があって魚が泳いでいた。久しぶりに行くと、撤去されていた。生き物がいなくなると、どんな空間も寂しくなるものだが、「たつや」は寂しくなるどころか、圧倒的に元気な店になっていた。
「こないだ、7、8年ぶりにいらしたお客さんがいて、その人が、『前よりずっと旨い店になった』と言ってくれたんです。こういうことが、ずっと続く店にしたい、って。大変だと思いますが、進化しつづけたいんです」
屈託なく、熱いことを言えるたかさん。間違いない。今日の「たつや」は昨日の「たつや」より旨いよ、と言いたくなったが、やめておいた。店を継ぐと宣言したときの、たかさんの父親の言葉が、妙にリフレインして、「調子にのっちゃいますから、やめてください」とたかさんに言われそうな気がしたからだ。

文筆家。コの字酒場探検家、ポテサラ探求家、ソース研究家。1971年生まれ、東京都出身。東南アジアと横浜育ち。一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。出版社勤務を経てフリーに。著書に『コの字酒場はワンダーランド』『今夜はコの字で 完全版』(土山しげる・画)などがある。BSテレ東のドラマ「今夜はコの字で」の原作をつとめる。これまでに訪れたコの字酒場は数百軒。集英社インターナショナルのnoteで「今夜はコの字で~全国コの字酒場漂流記~」連載中。
公式X@katojump